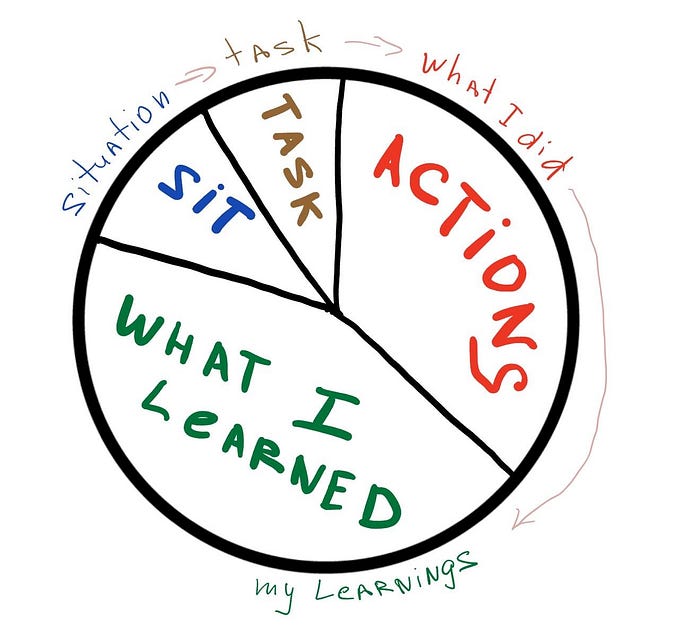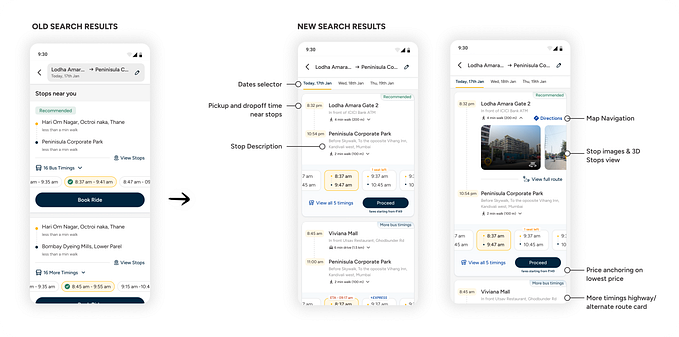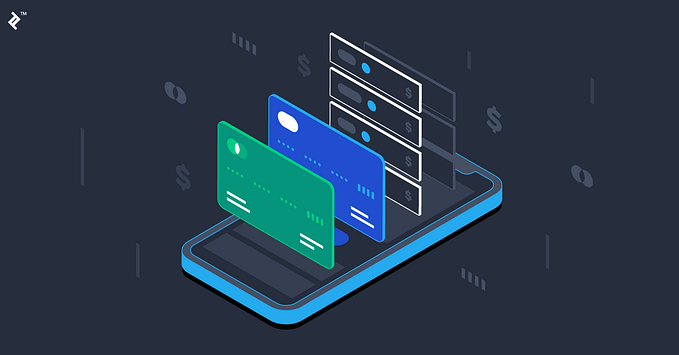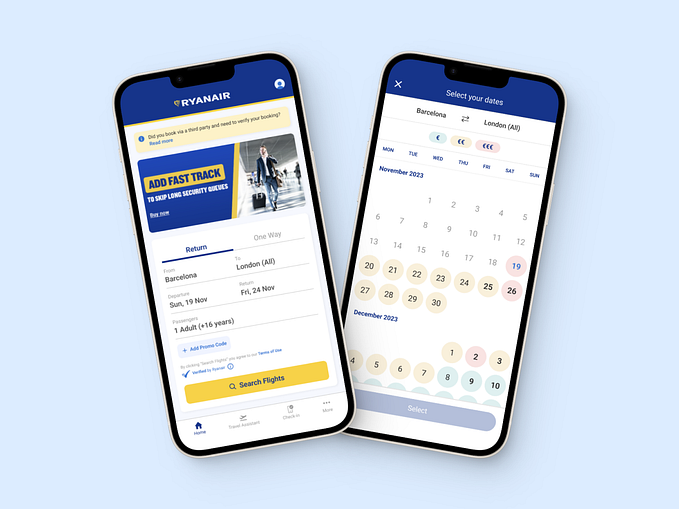建築学概論[第13回/2020.07.23]明治大学建築学科をつくった人
神代雄一郎:彼は建築に何を問おうとしたか。
みなさんお久しぶりです。この授業も終わりに近づいています。皆さんは4月に明治大学に入学したのにいまだにキャンパスにも入れず、友人にも、教員にも実際には会うこともできていませんね。オンライン授業にも疲れているでしょうし、何しろ課題が多いですよね ─── 。うちの娘も「課題が!」とため息をついたり、急に叫んだりしています。
さて今回の講義は、そうした日々を少しだけ遠目から見つめ直すような機会になればと思います。自分が「通っている」、この明治大学建築学科ってどんな学科なんだろうと、そんなことを考えてみるのに役立つ話題になるはずです。
1
戦後、建築学科は急激に「膨張」した
今年は2020年ですね。太平洋戦争の日本敗戦、そして第二次世界大戦の終結から何年たったでしょう。そう、75年。3/4世紀です。その頃、だいたい戦争前から戦争直後までの時期、建築学科に毎年入学する学生さんの数、どれくらいだったと思いますか?
私が前に調べたところでは400人くらいでした。勘違いしないでくださいね、日本全国で、です。現在はどれくらいだと思います? ─── ざっくり2万人です。3/4世紀前の人口は、戦争による出入りがありますが1950年頃で8千万人、現在は1億2千万人ですから、総人口は50%増ですが、建築学科の定員は50倍なんです。「!?」ですよね。これは何かが変わったぞ、という数字です。
ひとつは学制の改革です。教育基本法・学校教育法が1947年春に公布され、高校、大学も含めて、教育機会をひろげていく動きがはじまりました。日本を民主化する大きなプロジェクトの一貫でもありました。私たちの分野でいえば、戦前からの高等工業専門学校(高専)が4年制工業大学になったり、あるいは4年制総合大学の1学部になったりしました。明治大学の建築学科は、1949年、後者のパタンで産声をあげています。戦前からの伝統ある総合大学に、新しく工学部ができた、そのなかに建築学科もつくられた、ということです(理工学部となったのは1989年です)。
もうひとつは社会と産業の変化です。戦後復興から高度経済成長へと、日本の風景が「建設」によってどんどん書き換えられていくのですが、同時に産業構造の転換が進んで、日本全国、どこでも、なんでも、専門的な「会社」(企業)に担われるようになっていきます。親たちも、子どもを企業の社員にしようとしました。建築部門もそうです。実際、1960年代の建築学科はいま振り返ると仰天するほどの学生を受け入れ、建設会社の企業戦士として吐き出しています。明治大学の現在の定員は173ですが、60年代は入学者が300人を超えたこともありますから、本当に驚かされます。
逆にいえば、戦前は大卒の建築家(=建築の専門家)の指導下で企業(ゼネコン)が現場を取り仕切るなんて建物は、ごくひとにぎりでした。乱暴に言ってしまえば、鉄骨造とか鉄筋コンクリート造の建物がとても少なかったんですね。住宅はほぼ100%木造だし、大都市の都心以外では学校だって役所だって何でも木造が基本で、各地方の工務店が担っていたということです。こういう時代に大学の建築学科で学んだ人々は、いわば社会のなかで突出した、都市のなかでそこだけが光り輝いて見えるような、そういう最先端の建物を設計・監督する、超エリートだったのです。
戦後、私たちの明大建築学科とともに全国で産み落とされた建築学科に、教授陣として迎え入れられたのは、この超エリートの人々だったわけですね。建築学科が膨張し、建築の世界と、都市の風景が変貌していくのを、彼らはどう見ていたのでしょうか。もちろん、彼らにたとえ疑問があったとしてもこうした流れ自体は変えられなかったでしょう。しかし、それをどう見ていたかは重要な問題です。
2
明治大学建築学科、草創期の教師陣
明治大学建築学科開設の立役者は堀口捨巳、渡辺要、河野輝夫の3先生です。

堀口捨巳(ほりぐち・すてみ|1895–1984)は、1920年、東京帝国大学建築学科卒業の年に結成された「分離派建築会」というグループの主要メンバーとして、国際的にもよく知られています。日本の建築教育・学術は国家主導ではじまったのですが、分離派は、いわば自律的な個人としての建築家の理念や表現という回路で建築を考えた、日本で最初の人々です。堀口は、その理論的支柱でした。その後も新しい建築表現を探求しようと熱意を燃やす後続の若い世代にとって、堀口は一目置くべき人だった。堀口はまた、没後もなお他の追随を許さない茶室研究者としてあまりにも著名です。1949年(昭和24年)に著書「利休の茶室」で日本建築学会論文賞、1951年には「八勝館みゆきの間」の設計で日本建築学会作品集を受賞するなどしています。いわゆる近代建築(modern architecture)と日本の伝統建築とを接続しながら新しい美学を探求しようとしたたくさんの建築家たちの、静かな思想的指導者だったと考えるとよいのではないでしょうか。その堀口が、研究・設計活動の最盛期に、私たちの建築学科開設に尽力したのです。今でも明治大学の建築学科は「堀口捨己がつくった学科」と言われることが多いので、皆さんもぜひ覚えてください。
渡辺要(わたなべ・かなめ|1902–1971)は、1942年(昭和17年)より東大第二工学部建築学科教授、1950年(昭和25年)より東大生産技術研究所の教授として活躍しました。環境工学の泰斗として知られますが、この分野はかつては「建築計画原論」と呼ばれていました。熱い地域では室内の気積を大きくした方がよいとか、窓はどれくらい開いているとよいといった知識は、建築の計画の基盤になるからです。河野輝夫(こうの・てるお)は日本大学建築学科教授を経て河野建設株式会社社長の職にあり、戦前の建築学会における「柔剛論争」の一方(剛構造派)の論者としても知られる、建築構造学の権威でした。
そして、実際に開設され走りはじめた建築学科の最初の教師陣は、堀口捨巳、河野輝夫、神代雄一郎(こうじろ・ゆういちろう|1922–2000)、徳永勇雄(とくなが・いさお|1922–2003)の4名でした。神代は近代建築史や建築意匠の専門家で、建築批評にも健筆をふるった人です。明大建築学科発足時には27歳前後とたいへん若かった。徳永も同い年で、建築経済の専門家でした。戦後急速に変化していった建築界の産業構造に関する研究で高い評価を築いた人です。
皆さんが身を置いているこの明治大学建築学科の教師陣は、現在、専任20名、特任や客員も含めると30名近い教師陣を擁しています。しかし今日の講義では、明治大学の建築学科をつくった開学時の先生たちのなかから、神代雄一郎をとりあげて、その事績と精神を私なりに皆さんにお伝えしたいと思います。
私が明治大学の教師になったのは12年前ですが、着任後しばらくして、他の先生方に背中をおされ、堀口捨己と神代雄一郎をとりあげた展覧会とシンポジウム「建築家とは何か ── 堀口捨己・神代雄一郎の問い」を企画しました。磯崎新氏から藤村龍至氏までの建築家と、近代建築史や建築批評にかかわる気鋭の方々をお招きしたシンポジウムの記録はウェブマガジン10+1 websiteで読むことができます。これをきっかけに、明治大学建築アーカイブスが学科内に設置され、神代雄一郎先生の旧蔵資料をお預かりすることもできました。これは学科の遺産であり、皆さんの資産でもあります。なお、神代の著作リストは、学科のウェブサイトにまとめておきました(神代雄一郎著作アーカイブ)。
3
若き日の神代雄一郎
最初に神代の若いころのことを簡単にお話しましょう。

堀口と神代は、ふたまわり以上離れています。左の写真はいずれも高齢になってからのものなので、そのあたり何とも伝わらないと思いますが。
先にもお話したとおり、「分離派」というグループが立ち上がったのは、堀口が大学を卒業した1920年のことですが、年齢的には25才でした。これは神代が生まれる2年前のことです。それ以降、さまざまな建築運動が若い人々によって次々に展開されましたが、中国大陸での日本の軍事行動が戦争を引き起こし、また拡大させていくと、やがて太平洋戦争へと、日本は自らを止められなくなっていきました。戦争によって口をあけた社会の暗い穴がどんどん広がり、やがてはあらゆる人々の日常のすべてを飲み込んでしまいます。
神代の日常もそうでした。終戦時に23才ですからね、学生時代はまるごと「戦争」の月日だったということです。友人たちが次々に兵隊に取られていく、自分にもその日が来るだろう ─── 。当時、「日本浪漫派」と呼ばれる思想的傾向が若い人たちのあいだで大きな力を持っていましたが、神代も例外ではありませんでした。とてもロマン主義的な詩や絵を描いています。1年生の皆さんにはちょっとわかりにくい話だと思いますが、自分も戦地で命を落とすに違いないという思いをつのらせる若者たちが、甘美な文学的世界や遥かな古代への美的幻想に浸るようになるのです。逃避的ですが、それでも彼らにとっては切迫したリアリティーがそこにあったのだと思います。すべてが真っ黒な大きな穴に飲み込まれていて、公然と言えるのは戦争という大義名分に適うことだけ。そういう暗い穴のなかで、ナイーブな学生たちが美しい光に満たされた場所を私的に思い描くことを、逃避だと責めることはできません。「戦争」がつくり出してしまう、ブラックホールのような暗鬱な空間 ─── これが非常に強く神代の心のなかに刻みつけられたであろうと私は思います。
彼は建築学生だったのですよね。でも、二十数年前の堀口らのように、あるいはそれに続く15年間くらいのあいだ、つまり「穴」が広がりはじめるまで、建築の表現、美学や文化、あるいは技術と社会などといった問題を議論してきた先輩たちのようなことは、神代にはできませんでした。だからこそ神代は、戦争が終わると、「穴」のなかに「幻」を見ることから抜け出して、分離派に始まる建築思想の息吹をもう一度たどり直し、そのうえで戦後の建築の指針としよう、そんなことを考えはじめます。じつは、戦後まもなくたくさんの建築運動体が復活したり、あるいは新たに誕生したりしたのですが、それらが合流して1947年に NAU (New Architect’s Union) という建築運動団体が立ち上がりました。神代はそこに参加して、建築運動の歴史を調べはじめたのです。神代の文体は、戦中期の私的で詩的なものから打って変わって、固く理論的なものになり、建築家の社会性を問うものになります。
あまり単純な言い方をするのはよくありませんが、戦前は、〈建築 architecture〉は政府、大企業、富裕層のためのものでした。堀口ら以降のさまざまな議論や活動も、建築界全体のなかでは微力でしたし、戦争が激化するともうどうにもならなくなった。対して、敗戦後はかなり局面が変わります。建築界が口をそろえて、「人民のため」「民衆のため」と叫びはじめたのですから。実際、敗戦後には都市は焼け跡の無残な姿をさらし、住宅不足は全国で約40万戸にも達していましたから、建築は文字通り「人民」「民衆」のために再出発するチャンスを手にした、とも言えるのです(実際、それが「住宅」をめぐる戦後の夢や技術につながっていきますが、それは今回の主題ではありません)。
4
現実は違った ─── なし崩しの戦後への失望とアメリカでの気づき
ところが、早くも1950年に朝鮮戦争が始まり、そのおかげで日本は復興が加速し、景気が良くなって高度経済成長へと進みます。敗戦国として打ちひしがれていたのは事実ですが、あれよあれよという間に助走の勢いをつけてもらい、離陸にも成功し、さらには雲の上へと機首を上向きにして飛び続けることができた。50〜60年代にかけて、ビルブームとも呼ばれた都市の建設ラッシュが起き、また各都市のシンボルとして鉄筋コンクリートの神殿のごとき公共建築が建っていきました。その勢いは東京・大阪などの大都市から、地方の中核的な都市へ、さらに周辺の都市へと広がっていきます。
私は前に渋谷の戦後史をざっと調べたことがありますので、ちょっと渋谷を例にしてみましょうか。50年代はじめの渋谷駅周辺は、焼け野原に木造のバラック(仮設的な建物)がひしめくような風景であったのですが、60年代を迎える前にすでに中高層のビルが乱立し、継ぎ接ぎだらけの駅の錯綜もふくめて、非常に混乱した都市景観に変わっています。
少しのち、1964年東京五輪の年に、建築家の磯崎新が書いた文章を引用してみましょう。
たとえば、渋谷駅をみてもいい。国鉄、地下鉄、二本の私鉄、無数のバス路線、放射、環状の各道路がこの凹地めがけてやたらと突っ込み、各種のレベルで重なり合い、その隙間にショッピングセンター、デパート、バスターミナル、劇場、映画館などがはさみこまれている。この相互が微妙で複雑な経路で連絡されているのだ。この関係を一目で図示するなど不可能にちかい。それだけでなく、建物や諸施設は長い間まちまちに建設され異なったファサードを持ち、しかも、その表面や屋上には無数の広告塔が乱立している。
無関係で異質なものが、それでも副都心と言う一点をめがけて、錯綜し合い、重層して、みわたすかぎり不連続な堆積となったわけだ。これだけダイナミックに空間が変動している地区は世界にも類がない。(磯崎新「世界のまち ─── トウキョウ」 (読売新聞 夕刊 1964.10–12)
その頃、50年代末から60年代初期だと、神代はすでに明治大学の教員になって十〜十数年という時期です。建築思潮の歴史を研究しながら、現代建築の評論に筆をふるう、気鋭の建築批評家でしたが、ビルブームのなかでだんだん迷いが出てくる。人民のために、民衆のためにと、戦後あんなに一生懸命に議論していた建築家たちが、実際に景気がよくなって建設ラッシュが起きると、都市を混乱させるような事態に加担しているではないか。
神代の文章に、その戸惑いの現れと思われる文章がありますので引用してみましょう。
わたしは、建築家が都市を混乱させるものだなどとは、実は考えていないのだ。建築家に、もし都市を混乱させうる程の力があったなら、東京はすでに整然とした美しい都市になっていることであろう。……しかしそうだからといって、日本の建築家は気の毒だなどとはいいたくない。……社会問題はみんなの問題である。……こうした深刻な、笑い出したいような諸ムジュン。どうやら建築家は、都市を混乱させるまえに、すでに都市によって混乱させられてしまっているようである。(神代雄一郎「建築家は都市を混乱させている?」建築文化1959.05)
神代が、都市が建築家を混乱させている、というとき、この「都市」とは資本の活動のことでしょう。建築家はお金の動きに従っているだけで、理想など忘れてしまったのではないか、と言っているのです。
先にお話したように、この頃から大学で建築を学ぶ学生は増えていきます。しかし学生が働く建築の世界はこのようなありさま。まるで社会全体で若者たちを「経済戦争」に「動員」しているようではないかと思った ─── 神代はのちにそうふりかえっています。戦争とは、それ以外のことが公然とは言えなくなっていくような、黒い穴が日常の一切を覆っていく事態でした。経済成長のために戦う、それ以外のことは見えなくなってしまう。これはもうひとつの戦争ではないか ─── 。
こうして段々と神代は「スランプ」に陥ります。建築の良し悪しなど批評しても仕方がないのではないか・・・。すでに教師であり研究者、批評家である彼はもういちど「浪曼派」になるわけにもいかない。何も変えられない・・・。

──都市・建築・芸術』
(井上書院、1971)
60年代の半ば、1965年(昭和40)から66年にかけて、神代は在外研究のためアメリカに行きます。彼はこんなことを考えたようです。─── 日本の建築思想はなぜすぐに骨抜きになってしまうのか。それに、あれだけめちゃくちゃに建物が建ち、都市が混乱しているのは「みんなの問題」なのに、なぜ日本の民衆は疑問の声、怒りの声を上げないのか。そもそも「みんなの問題」、つまり自分たちのことを自分たちで考え、意見を出し、決めていこうとする意識 ─── それが民主主義というものだろうけれど、それが日本では希薄なのだろう。ならば、その民主主義を日本に植え付けようとしたアメリカという国の人々はいったいどうなのか?それを見たい。神代はそう思ったようです。

アメリカに行ってみると、大都市はやはり病んでいる、つまり日本もダメだがアメリカもダメだ、というのが神代の観察でした。たとえば高層オフィスビルの表面がベニヤで覆われている風景をみた。それは実はガラスのカーテンウォールがバタバタと落下して人を殺してしまうという事件が起き、応急手当としてベニヤが貼ってあったのですね。あるいはストライキで地下鉄が止まり、停電が起きるとエレベータが止まるので高齢女性が高層階の自室に階段をあがっていく間に心臓麻痺で亡くなる。都市というものが人間を超えてしまい、人間活動を混乱させ、ときには人間を殺してしまう。
みなさんは「おおげさな」と思うかもしれません。今はカーテンウォールは落ちないし、エレベータは代替電源があるから止まらない、つまりテクノロジーが解決する問題だという意見もありえます。しかし大地震に襲われると超高層やタワーマンションはどうなるか・・・。テクノロジーが解決すると言っているだけでは、原発事故のような問題が起きることを避けられません。ちょっと飛躍しましたね。でも資本とテクノロジーが盲目に走ると、人がつくったものなのに、人を襲う。
少なくとも日本の50〜60年代の都市開発の混乱を見て悶々としていた神代の目には、都市が人を殺す、という表現でこそ捉えられる何かがたしかに感じられたのだと思います。そして、日本で疑問に感じはじめていたあの問題は、端的にいえばスケールの問題だと神代は直感したと思います。
他方で、アメリカではこういう積極的な発見もありました。つまり、田舎のコミュニティに行ってみると、そこにはしっかりとした民主主義が息づいている。自分たちの町や村をどうしていくかということについて、人々がみんなで話し合って考え、決めているし、駄目なことがあれば指摘し、批判する。これがグラスルーツ・コミュニティ(草の根の共同体)、グラスルーツ・デモクラシー(草の根の民主主義)だというわけです。これも神代にとっては、「適切なスケール」という問題とかかわっていました。互いに顔がわかり、意思疎通ができるような数の人間集団だからこそ、「わたしたち」という意識を持つことができるし、最終的には「わたしたち」の社会や環境はこうありたいという思いや価値観のために、個人の意見を出し合い、合意する。しかし、巨大都市では人がつながりのない原子みたいにバラバラになってしまうから、「わたしたち(みんな)」という意識も持ちようがない。
5
日本の辺境漁村へ ─── デザイン・サーヴェイ
アメリカでの経験と発見は、神代にとって大きな転機になりました。日本に戻ったら日本のコミュニティを調べ、その「わたしたち」という結合はどんなふうにできているのか、それと集落の空間はどんな関係にあるのか、そういったことがわかれば、それを都市での建築設計にもつなげられるのではないか。「デザイン・サーヴェイ」と呼ばれる調査に着手したのは、神代の場合はそういった経緯と思いからでした。

『コミュニティの崩壊──
建築家に何ができるか』
(井上書院、1973)
神代の場合、と書いたのは、じつは67〜68年頃から、70年代の終わり頃まで、デザインサーヴェイはたくさんの大学の建築学科の研究室や学生グループ、あるいは若手の建築家グループなどを虜にした、一種の熱狂的な運動になっていくからです。その内容はさまざまで、田舎に残っている古きよき集落の風景を実測してその景観の美しさを分析するものから、商店街の看板を集めたりマンホールの蓋の拓本を取るといったものまで、じつに多様です。共通していたのは、建築家の作品ではなく、むしろ無名の人々の営みによって生まれている環境から何かをつかむ、という姿勢です。
神代の場合は、日本の小さなコミュニティの原理を知りたかった。そして、そのために辺境の漁村を調べはじめます。神代研究室が調べた集落のうち、最初の6ヶ所は、1967=女木島(香川県)、1968=伊根(京都府)、1969=壱岐勝本浦(長崎県)、1970=菅島(三重県)、1971=沖ノ島(高知県)、1972=十三(青森県)と小さな漁村ばかりですし、4つは離島です。


45歳頃の神代雄一郎と思われる写真をお見せします(左)。顔があんまりきちんと写っているものがないのですけど、おそらく間違いないだろうとご子息の確認をとりました。女木島で撮ったものです。右の写真は、どこの旅館か分かりませんけれども、女木島調査中の学生さんの合宿の様子ですね。別の写真で、布団がだーっと並べてあるのが分かります。当時院生だった方にお話をうかがったことがありますが、朝早く起きて朝ご飯を食べると、昼飯まで家を2軒ほど実測したそうです。4つか5つぐらいのチームに分かれて進める。院生がトップになって学部生を含めて3、4人のチームで、ものすごい速度で現場の実測図をつくるんですね。1軒2時間ぐらいだったと思われます。昼飯を食べたら、午後は一切仕事をせずに海水浴をしたり、町のおじちゃんやお兄ちゃんたちとお話をするということだったそうです。

8月にそうした調査を2週間ぐらいやって、研究室に帰るとその整理をします。野帳からまず正確な図面におこす。次に、それを書き写しながら清書します。そして、たとえばたくさんの家の実測図をつなぎあわせて集落全体の平面図をつくるといった作業が進められ、雑誌発表用の図面になります。この過程で、大量の図面がつくられます。女木島は最初の年で、海沿いの家々とお堂やお宮さんの実測だけでしたが、翌年からは100〜200軒ぐらいの家々をほぼすべて実測し、平面図をつくっていますから、集落まるごと、全体が屋根を取っ払って間取りがのぞきこめるような、巨大な図をつくるのが神代研のスタイルになりました。


ところで、女木島の東浦集落は、浜から吹き上げる風と山から吹き下ろす風が、潮を巻き上げながらものすごい竜巻のような風を起こすのだそうで、それを「オトシ」と呼びます。オトシから家をまもるために、立派な石積みの壁を海岸に沿って建てており、これは「オーテ」と呼ばれています。神代はこのオーテにも興味をもったようです。


しかし、神代自身が一番興味をもっていたのはお祭りでした。さきほども言ったように、彼はコミュニティの成り立ち、原理を知りたかったからです。普段村を歩いても、村の社会的な組織はよく分からない。ところがお祭りになると、1つの村のなかに、何十軒かでひとつの「組」があり、それぞれが役割を持って協力したり競い合ったりする。そして長老格の人から、若衆、あるいは婦人会まで、いろいろなグループがそれぞれの役割を担う、そういうことがお祭りでは顕在化するわけです。それで、神代研の調査はいつも夏祭りの時期に合わせて行われました。



彼の関心はコミュニティにあったわけですが、ヨーロッパ、アメリカにおけるコミュニティの空間といえば何よりも広場ですね。おそらくそういうこともあったと思いますが、女木島の東浦と西浦が一緒におこなうオオマツリ(大祭)を見ると、その舞台となる東浦集落には5つの重要な広場があり、そこへ神様を担いだ神輿と太鼓台が練り歩いていって、それぞれの広場のところで太鼓台が激しく動き回る行事がおこなわれる。これが住吉神社を出て、ぐるっと集落をめぐり、帰っていく。そういうものがコミュニティの空間のひとつであろうということになる。そういうわけで、神代研が描いた、たくさんの魅力的な図面のうち、立体的に描かれ、人間をたくさん配置して生き生きと表現された図面は、だいたい広場の絵であり、その人々は祭りの意匠をまとい、太鼓をたたいたりしているわけです。

こういう調査をいろいろ重ねていった数年後に、日本のコミュニティの基本構造みたいなものが分かるようになってきたというわけで、原理の把握、モデル化に神代は取り組みました。それが下の図です。

集落の山から海にむかう方向、女木島でいえば鷲ヶ峰から瀬戸内海へのタテ軸が「信仰軸」であり、山が御神体です。それに対する拝所が、(古い時代の話ですが)やがて里に近いところに施設化された神社になってくる。それが「里宮」です。また、神さまがお祭りのときにお休みをする場所もあり、これを「田宮」といいます。一般にいう「御旅所」に相当するものです。御神体―里宮―田宮の3つがどの集落にだいたいあり、これらがタテ軸を構成します。
それに直交するヨコの軸、つまり海に沿った一番低いところ、陸と海の境界のところに、社会と経済の軸ができる。神代たちが調査したのは漁村なので、漁業をする人たちがいくつかの組をつくって、それが並んでいる。組は生産・生業の組織であり、それが共同体のまとまりでもあって、それらが連なり、そこを行き来する交通の軸がある。
このように2つの軸が交差するようにしてできるというのが、日本のコミュニティのひとつの基本であろうということを、神代研究室はまとめたのです。さらにもう1つ、神代がとくに注目したのは、コミュニティがよく機能するためには、それにふさわしい適切な規模というものがあるのだということです。彼らが調べたところでは、だいたい200戸・1,000人という数が共通している。調査が60年代の末から70年代前半にかけて行われていますから、村々では都市部への人口流出、いわゆる過疎化の問題が顕在化していた時期です。集落によってはすでにかなり人口が減ったところもありましたが、少しだけ遡ると、200戸・1000人というサイズが長い時間にわたって安定的な規模であったと神代は言います。この適正規模を大きく超えると、互いの顔が分からなくなり、地域共同体としてのまとまりが働かなくなってしまう。そして距離的にも集落は400メートルぐらいの長さのなかにおさまっているのがよい。調べた集落はだいたいそれに当てはまる。
こういった「知」の打ち出し方は、神代のデザインや造形に向かっていく志向性をよく示しています。たんに社会構造をつかまえるだけでなく、その大きさや、骨格をもつカタチといったことを同時に考えている。神代研のデザインサーヴェイは、コミュニティの造形論、意匠論(デザイン論)、もう少し広くいえば「人が集まる場をデザインするための造形規準」を提示しようとする運動だったのだと、私は受け止めています。
5
「九間論」と「巨大建築論争」
ちょっと話をズラします。といっても、神代の考えたことの本筋をむしろ捉えるためです。
修学院離宮の窮邃亭(きゅうすいてい)は、三間四方、正方形の広間です。1年生の皆さんが相手ですからいちおう説明しておくと、「一間(いっけん)」という言葉は、柱と柱の「あいだ」という意味で使う場合、畳の長辺、つまりは6尺という寸法の意味で使う場合があります。ここでは両者の意味が重なっています。実際に、6尺おきに柱が立っていますからね。また、一間四方(いっけんしほう)は一坪(ひとつぼ)という大きさになりますが、この空間を「一間(ひとま)」と呼びます。ややこしいですね。すると、三間四方の広間というのは、この「一間(ひとま)」✕9つ分に相当しますね。こういうわけで、この広間は「九間(ここのま)」と呼ばれる伝統があります。
神代はこれに着目して、「九間論」という文章を書いています。これは建築史の人だけでなく、建築家からの評価も高い。神代はデザインサーヴェイを通して集落研究のようなこともやっていましたが、学者としてはまず近代建築史・思想史の研究者であり、そして日本建築の意匠(デザイン)の研究者でもありました。「九間論」は、神代の日本建築意匠論の作品のなかで代表的なものです。いや日本建築意匠論の最高の作品のひとつといってもよいでしょう。
ごく簡単に説明します。日本の建築を、古代から現代まで、時空間を疾走するようにスキャンしていくと、中世になって「九間」が現れ、その後もしばしば見いだされる。図のなかに、あるいは古い文書のなかに、「九間」と書かれてもいる。それらは建物のなかで中心的な会合の場所、人が集まって考えや気持ちを交わすのに理想的な空間として位置づけられているらしい。神代はそのことを発見した。それまでほとんど着目されていなかったけれども、歴史を貫いて現れる理念的空間、美しい空間の系譜をぱっと見抜く力、眼力を持った人でした。自分が疾走する時空間のなかに、かすかに白く浮かぶ糸切れのようなものを見出し、それらをつなぎなおしていくことで、むしろ光線のような理想の本流として描き直す、きわめて鮮やかな論文です。
さて、ここで注目すべきは、ここでも大きさ(規模)とかたち(形態)に神代が着目していること。そして、ここでも人が集まり、互いの考えや気持ちを通わせるための空間に目を向けていることです。これはデザインサーヴェイでの神代研究室の見方と通底します。もちろん、「九間論」を書いた神代先生と、デザインサーベイで200戸―1,000人―400メートルという数字を出した神代先生は同じ人物です。時期も同じですしね。
こうして「人が集まる場の造形規準」の重要性を日本の伝統と結びつけて打ち出せることを確信するに至った神代は、1974年(昭和49)、「巨大建築に抗議する」という、よく知られる論文を『新建築』誌に発表します。
巨大開発に協力している建築家たちを公然と批判、糾弾する文章です。この雑誌は、建築家の皆さんが作品を発表する、最もメジャーな雑誌です。そこに他ならぬ建築家を批判する論文を掲載したわけです。発表後、日本で最も大きな組織設計事務所の中心的な建築家(複数)からの批判が、同誌上に掲載されます。逆に、神代を支持する人は、少なくとも公式の言論の場ではひとりも現れませんでした。若い学生さんや、個人で事務所をやっているいわゆるアトリエ系建築家たちは応援してもよさそうなものだと私は思いますが、実際は誰も応援してくれなかった。そして1976年(昭和51)に神代はもう一度筆をとり、私が言いたかったのはこうだということを再度同じ雑誌に書いたのですが、再び批判されます。この時の批判者は、大学の研究者でした。この当時、いわゆるゼネコン(請負建設会社)や大型組織の設計者こそが時代を担っていくのだと考え、そうした言論活動を展開していた歴史家です。戦後、神代は建築運動に参加しながら近代建築の思想史を研究したと言いましたよね。そのときの仲間です。彼の文章が、神代批判の決定打になりました。それは内容への批判ではなく、読むに足らぬということを徹底的に書いた、見るもおぞましい文章でした。そしてやはりほとんど誰も神代を応援しなかった。神代はこれで「断筆」を決めます。まったく書かなくなったわけではなりけれども、現代建築批評に健筆をふるっていた神代が、作品批評の表舞台には姿を見せなくなった。これは建築界全体にとって大きな損失であったと思います。
さきに、若者たちは経済戦争に動員されているのだと神代は感じたのだ、という話をしました。それは、この論争の口火をきった文章のなかで神代自らが実際に書いていることです。先の戦争と同じように、若者たちは ─── と。先の戦争で動員されたのは、他ならぬ神代たちの世代でした。
6
私たちは何を受け継ぐか
この後、神代が信頼できる人たちと静かに議論しつづけたのは、「地域主義」を広め、定着させていくという主題でした。地域に根差し、地域の建築をつくる建築家を、いろいろなかたちで応援しました。
地域主義は、英語ではリージョナリズム(regionalism)といいます。これはもともと政治学の言葉です。要するにそれぞれの地域、コミュニティ、地方、これが自律的に自分たちのことを考え、自分たちのことを決定していく。つまり地方の自治、その前提としての地方分権にかかわる言葉です。民主主義の条件を考えたものだと言ってもよいでしょう。神代は、建築において民主主義や地域主義を考えようとしていたのです。
いわゆる「近代建築」は、地域をこえ、国際的にどこでも同じ思想、同じ技術で設計されるべきであるという国際主義の思想を含みます。思想とは近代的な人間と社会を目指すということであり、技術とは産業革命以後の近代的な技術です。神代は、1970年代後半には、この近代建築に代わる次の潮流を担うのは地域主義であろうと言っています。地域の共同体、コミュニティというものが自律的な力を付け、資本の力に対抗していく。大きくいえば、そういう理念や実践に建築家もコミットしなければならない。そういうことを神代はたぶん考えたと思うのですね。
さて、神代と神代研の学生たちが女木島などの集落を調査してから、半世紀が過ぎました。この半世紀というのは、おそらく日本のコミュニティーにとっては大激変の時間だったと思います。
戦争は都市を破壊しました。でも再生した風景は戦前とつながっていた。むしろそれを一変させたのは高度成長期の開発です。蘇った都市をもう一度壊しながら新しくしていったのですね。学生たちは大学という工場で企業戦士に改造され、その経済的狂乱に動員された ─── 神代はそう捉えて建築に迷いを抱えました。他方、田舎の村々も経済成長と無関係ではありませんでしたが、それは主に若者の流出、ということでした。そりゃそうですね、彼らこそが都市に送り込まれ、企業戦士になったり、労働者になったりしたのですから。その彼らが10〜20年もして立派に家族を養えるようになるまでに、親たちは彼らが帰ってくるかもと家を立派に建て替えるかもしれませんが、しかし自身は高齢化し、村は年寄だけになっている。コミュニティなど解体しており、だから21世紀に入る頃には村々でも“コミュニティ再生”が叫ばれ、なぜか欧米やアジアのアーティストたちがやってきて“芸術祭”が開かれたりするようになります。
女木島もこのような変化を辿ってきました。神代が集落を調べたころ、つまり1967年の女木島ではすでに、かなり多数の人が高松、あるいは神戸、大阪等に流れていってしまうということが起きていましたが、まだ村には長男が残り、結束の強い伝統的コミュニティが生きており、毎年盛大なお祭りができた(この島のオオマツリは昔から男木島と交互にやっているので、正確には2年に1回ですが)。しかし、私たちが生きている2019年(平成31)までのあいだに、若者の流出は止まらず、人口は激減しました。今では集落を歩いてもほとんど子どもに会いません。
神代先生が考えた“コミュニティ”というキーワード、あるいはその規模や形態の規準ということだけでは、もうどうにもならないところまで来ているのだろうと思います。しかし、それは新しい可能性を考える時が来たということでもあるはずです。
同じ女木島の西浦集落をたずねたとき、浜の近くに荒多明神という神社があり、そこにいたおじさんと話をしていたら、面白いことを教えてくれました。「この神社のご神体はやっぱり山ですか」と私が訊ねると、「違うよ」と言って、彼は海を指差したのです(!)。目の前の海の中に、御神体があるんだというわけです。海底の岩がポコっと突起のように盛り上がったところがあり、潮が引くと見えるそうです。その神社の神さまは、地上しか見ていなかった僕らの眼には見えないところにいらっしゃった。直感的に想像したのは、山にもカタチがあるように、昔から瀬戸内の皆さんはきっとこの海の世界の地形を「見る」「読む」ことができた。海面の下がどういう地形になっているか、どの時期にどう潮がどう流れるか、そういうことを読み解く能力があるのだろうと。
つまり、家々の並ぶ集落や人々の結びつきとしてのコミュニティの前に、まずはこの地球がつくった大地のカタチがある。そこに人は寄生し、その特徴を読み取り、少しだけそれを改変して、自分たちが「生存」する方法を組み立ててきた。そういうところから考え直す必要があるのではないかと思いました。
「生活」という言葉を使うとき、私たちは、住宅があって、家族があって、人と話をしながらTVを見たり・・・というイメージをついつい思い描きますが、「生存」はもっとシビアで、しかも人間以外のイキモノや大地、あるいは気象などを見なければなりません。神代は「オーテ」には興味を持ったようですが、それを景観的な要素としてだけでなく、神代も気づいていたはずの「生存」という観点にさかのぼってもう一度読み直してみる必要があります。災害というのは「生活」を壊すものだと私たちは考えがちですが、「生存」とは災害をも組み込んで私たちの生き方を根本から考え、組み立て直すことにつながる言葉だと思います。
地形がある。大地は安定し、かつ動く。大気もまた同様であり、他のあらゆる生物の恵みと危険があり、それを加工しながら人間は生きてきた。そうした環境が、人口流出によって徐々に放棄されてきたんですね。人と自然のバランスが崩れ、本州から海を泳いだイノシシが上陸して繁殖するようになってきている。女木島の田んぼや畑は、もう大半が森に戻ってしまっています。私の感覚では、17世紀から20世紀までの人間社会は自然を技術的に可能なかぎり人間的に再編成してきましたが、いま逆向きに動きはじめている場所がたくさんあります。
しかし、他方では高松と女木島とはフェリーで20分ですから、土地の値段が安く、山や海のある場所で暮らして職場に通うこともできるし、情報技術によって島にいながら仕事だってできる。現に日本各地でそういう仕事の仕方をする人や企業はどんどん増えており、彼らは田舎の良好な環境を選びはじめています。漁業、農業、林業などを選んで田舎に移住する人も増えはじめました。過疎化した、スポンジのような村は、逆にこうした新しい動きを吸収する穴がいっぱい空いている。彼らを迎えた村々が、過去数百年の村とはまったく違う、新しい村へと組み替えられていく可能性を、夢想してみたいと思いませんか。
様々な条件が変わっていくことによって、それらを結びつけて組み立てられるだろう世界の全体性もまた、変わっていく可能性を宿します。それを見つけることは、やはり新しい風景、新しい大きさやカタチを発見することであろうと思います。神代雄一郎先生は、この世界の不気味な穴のようなものを感じ取り、建築に携わる者の倫理を問いかけ、また糾弾するだけでなく、新しい社会と建築との関係を模索しました。当時の学生さんたちも、神代と活動をともにし、時代をともにしていたのだということにも、想像力を馳せてみてください。
いまはまだコロナの嵐が吹き荒れていますが、落ち着いてきたら皆さん、ぜひともひとつひとつの街や村を、生の現場を、どんな場所でもよいから、自分の足で歩き、そして新しいカタチを夢想してください。「建築 architecture」とは何でしたっけ?第1回、第2回の授業を、夏休みを迎える前に、ぜひ読み直してください。