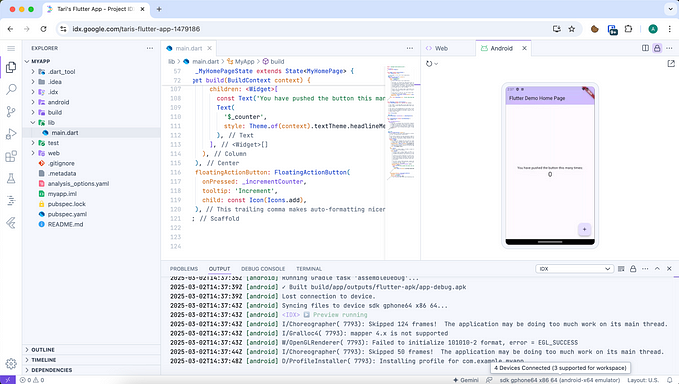リモートワーク・テレワークの始め方(2-2)
見えない・遅れる・表現しきれないリモート
さて、2−1では“当事者として”どう「記録する・比べる」を扱うべきか、事例と新しいツールの紹介で説明させてもらった。ここからは管理者の立場としての「リモートワーク」を話したい。
「記録する」という仕事を徹底させた時点で、更に困った人が出てくる。明らかに「一つの業務にかかる時間が長い」人だ。本人にとっても 他人との比較や本来あるべき姿が「見えない(・遅れる・表現しきれない)」のがリモートワークであり、悪気のないまま継続することがある。
ここで実行すべきが、「比べる」である。
無駄が発生すると思われるだろうが、あえて「同じような仕事を同時期に二人に振る」もしくは「一つの仕事を2分割して二人に振る」ことをしてみる。そうすると、時間の違いだけでなく、その時間の違いを生む「やりかた」の違いが浮き彫りになる。
そしてその「やりかた」の違いをパフォーマンスの悪い側に、共有する。ここまですると、悪意が有るにしろ無いにしろ、本人は変えざる得なくなる。
面倒な話に感じるかもしれないが、リモートワークでの「教育」は、これが一番効率良かったと感じる。結局の所、リモートワークは「見えない・遅れる・表現しきれない」ことを徹底的に削減していくしかないのだ。
さて、前回当事者ツールとして紹介した「リモトレAI」であるが、管理者向けの要素ももちろん入れている。リモートのように「見えない・遅れる・表現しきれない」世界で管理者は、できるだけ俯瞰して「比べる」武器を持たねばならない。

多くの人が「悪気なく」仕事に取り組んでいる。しかし、パフォーマンスの違いを表現しきる必要があるのが 管理者だ。
「リモトレAI」は、マネージャー向けに月に1回のサマリーレポートが付録する。サマリーレポートの一番の機能は「外れ値を見つける」ことになる。つまり、一定レベルまでトークレベルがない人のトークを見つけることが出来る。

上記ページは、一定期間(通常は1ヶ月分)に分析したトークの全特徴パラメータの平均値から、各トークがどのくらい乖離しているかを分析したページである。
右側のオレンジのゲージが大きれば大きいほど、平均から逸脱したトークであることを示しており、一定の範囲を外れているものは具体的に左側にそのトークファイル名が列挙している。
この例では我々の新人のロープレトークのうち、初期の4日間40トーク分の分析結果が出ている。分析の登録がされた順に上から並んでいるため、上のほうのトークほど初期である。
ゲージを見てみれば分かる通り、初期のトークほどゲージが大きい。つまり初期のトークは安定していないことを示している。
さて、我々はあえて1ヶ月毎ではなく、追加のサマリーレポートを作成し、2週目のトークと比較してみた。それが下記の画像である。

サマリーレポートは、それぞれの集合で平均値を取り、その中で一つ一つのトークがどれだけ乖離しているかが比較されている。
一目瞭然だが右側の2週目は、左ほど大きなゲージが出ていない。具体的に列挙された左側にも、1トークのみ検出されている。
これが示すことは、1週目の特に初期は 皆がバラバラなトークをしていたが、2週目になるとおおよそしゃべることが標準化されてきているということだ。
3ページ目以降は、具体的な内容を見ていくページとなる。それぞれ、個別フィードバックレポートの項目と一致している。

例としてわかりやすいのは、8ページ目の質問の検証であるが、これは「自分が発した質問」と「相手が発した質問」について、それぞれ「Yes/Noで答えられる単純なCLOSED質問」と「いつ・なに等を問うOPEN質問」に分けて、トーク内の数をカウントしている。
サマリーレポートでは、その期間の平均値が上方に示され、下方にはそれぞれのサンプルの値がグラフで示されている。
今回の例でいえば、平均値として2週目は明らかに 質問の総数が増えている。特に1週目の後半は「相手からの質問が増」え、2週目は「自分からのOPEN質問」が増えた。つまり、初期の段階(安定していないトーク)の段階では相手から質問をしてもらえることもなかったが、習熟度が高まると相手から質問されることが増え、更に2週目になると自らで情報収集するようなスタイルに変わってきているということだ。
もう1つ、我々の特徴的な分析結果を紹介したい。5ページ目の論点ランキングの検証だ。これは個別フィードバックレポートの表紙に示されているものと一致している。
これは何を表現しているかというと、トークの中で相手の印象に残りやすい(残ったであろう)話題をランキング形式で示したものである。1位にある話題は、その話し合いで一番 記憶に残ったであろう主張として示されている。
「論点ランキング」は我々コグニティ独自の技術ではじき出されている。創業1−2年目の頃 、YouTube動画やWeb上の記事など様々な情報を見聞きしてもらったあと「どの話題が一番記憶・印象に残っているか?」という市場調査を行った。その結果としてスコアの高かった話題が、トークや記事の中でどのような情報構成で成されていたときだったのかを分析したのだ。
情報構成の見分け方は、「リモトレAI」で紹介した我々の独自技術であるCogStructureを使っている。
例えば、一つの話題に対して いくつ補足情報が関係しているとか、何話題以内に同じ情報に戻ってきているとか、多少の懸念情報が付属しているとか、そういった情報構成・情報と情報の関係性として、市場調査スコアが高い話題に対して現れた構成パターンと似ているかどうかでスコアリングし、このランキングを出している。
このページの結果は、数値ではなく単語・文節で出されているので、多少読み取る必要はある。

1週目の前半はほとんど「リモトレAI」の効果や機能を示すフレーズは入っていない(“ご担当の方と打ち合わせさせていただいて”や“研修をやっているか”など、イントロトークが上位に来る)。
だが、中盤に差し掛かると“一人ひとりのトークに対してフィードバック”や“集まらずに研修ができる”などと、商品の概要説明が上位に現れてきている。
そして、1週目の終わりから2週目になると、“実際話したトークを分類分け”や“具体的な説明があるか確認できる”などと、商品の特徴・機能を説明する内容が上位に溢れ始めている。
このように、全体の進化・変化を把握することで習熟度を確認し、平均から逸脱した人(未熟・向いていない等)を早めに見つけて対処を考えることがきる。
このような「俯瞰」するツールは、
1.まずは逸脱しているものを把握する
2.平均値を確認する
3.個別の結果を確認する・平均と比較する
4.推移や変化を確認する
という順に使っていく。
これは何も「リモトレAI」だけの話ではなく、冒頭で出したような「一人ひとりの労働記録」であっても同じだ。複数人の労働記録を見て、他と明らかにおかしいものを見つけ(1)、全体と何が違うのかを見極める(2)。おかしいものの違いが何で構成されているのかを確認し(3)、その内容を本人に伝え改善を促し、一定期間後の変化をまた確認する(4)ということを繰り返す。
リモートワークは、リアルよりも「見えない・遅れる・表現しきれない」もの。いかに見える化して把握するかが管理者の仕事であり、それを表現し、本人に気付かせることが必要になる。できるだけ把握するための武器を増やし、改善までのリードタイムを短くしていくツールが必要になるのがリモートワークと言える。
(3に続く)