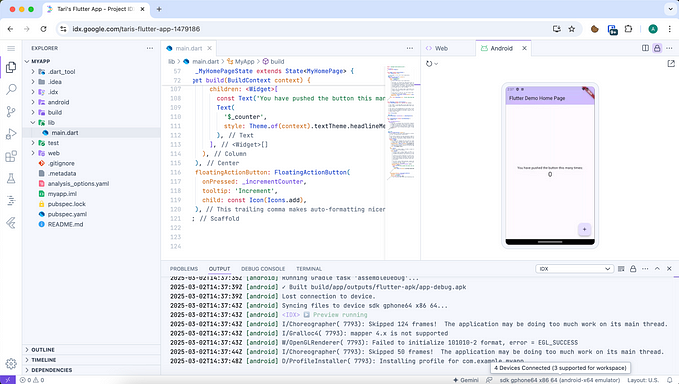うますぎるうまみの魔力
タイ山岳部のアカ族の村では、生活に必要なものを何でも自らの手で作り出す。家財道具は竹を採ってきて作り、食事は山の野草が活躍する。


調味料さえも自家製する。アカ族の台所に欠かせない調味料「アチィ」は、蒸し大豆を発酵させてひき割りにして干した「板干し納豆」だ。発酵と天日干しで増幅したうまみで、淡白な山の野草たちをおいしく料理する。山にあるもので暮らしが成り立っている。


しかし一方、そんな「自給自足」に見える台所で、なくてはならない存在になっている外来品が、味の素(うま味調味料)だった。


塩と同じくらい何にでも入れる。元々この土地になかった工業的製法による調味料という意味では油や砂糖と同じのはずなのに、台所の片隅で出番を待つ油や砂糖に対して、味の素は毎日毎食活躍し、その登場頻度の差は比べるべくもない。アカ族の料理の味付けは、塩・にんにく・唐辛子・アチィくらいしか使わないくらいシンプルなものに、その調味料らと肩を並べて味の素が幅を利かせているのには、なんだか不思議な気持ちになる。

なぜ味の素がこれほどまでに普及し、主役級な調味料として台所に深く浸透したのだろうか。
元々のアカ族の食事を見てみると、そのヒントがあるように思う。
アカ族の料理は、著しくたんぱく質が少ない。山岳部に暮らすため海の魚は食べないし、鶏や豚も絞めたときしか食べられないご馳走だ。元々移動式の生活を送っていた山岳民族なので、昔はそれらの家畜すらなかったかもしれない。生乳も豆類も常食せず、我々日本人の食卓と比べるとたんぱく質は著しく少ない。
たんぱく質が少ないので、その構成物質の一つであるうま味は必然的に少ない。食事の中心は米と野草で、そんな淡白な食卓だからこそ、うま味を生みだすべく板干し納豆アチィが生まれたのではないかと考えられる。何工程もの手間をかけてアチィを作り続けるお母さんの姿からは、アチィが単に味としてではなく栄養的に必要なものであることが察せられる。
そんな少うまみ社会にうまみの結晶が入ってきたら、その衝撃たるや計り知れない。

味の素社がタイに現地工場を作ったのは1961年だ。1950年台に日本からの輸出額が増加し、貿易摩擦解消や外貨節約等を理由に、輸出から現地生産へのシフトが進められた (参考: 味の素グループの100年史)。タイ国内の味の素普及はこの前後で急速に進んだので、きっと山奥のこの村にも1960年台頃に入ってきたのだろう。村人の話では、1970年台にはかなり一般的なものとして普及していたというから、なかなかな普及スピードだ。

うまみ物質は、たんぱく質の一種だ。うまみがあるということは「たんぱく質があるぞ、栄養があるぞ」というサインであり、人が本能的に求める味であるといえる。うまみの結晶が入ってきたら人が飛びつくように受容するのは、栄養的観点から考えても不思議でない。元々うまみが少ない社会においてはなおさら、その反応が極端になるのかもしれない。
伝統的うまみ調味料アチィがあっても追い打ちをかけるように味の素を入れる姿からは、うますぎる味はすべてを凌駕することを感じさせられる。
ところで、台所の女性が味の素を多用する様子に重なる姿が、村にはある。スマホのYouTube画面に釘付けになる子どもの姿だ。

村の大人たちは、食料を得るため毎日のように山に入る。子どもたちもついていき、水遊びをしたり草笛を作ったり、自然を使って遊ぶことを覚える。

しかし自然の中のあそびは穏やかで「やさしい」。能動的に自然に働きかける必要がある。それと比べて、何もしなくても動き続けて常に刺激を与えてくれるYouTubeは、強烈なまでに惹きつけられる。一度スマホを手にした子どもたちは、食い入るように見つめて水遊びも草木遊びも見向きもしない。

自然の中にある村の暮らしは、穏やかでなだらかで「変わりにくいもの」のように一見思える。しかし穏やかで刺激がない分、強すぎる刺激が入って来たときには反動のようにそれを強く受容してしまうのではないだろうか。産業分野では、1950年代に商業作物としてアヘン栽培が急激に普及したのは、それまで特段の産業がなく経済的に貧しい地域だったことが一因にあると言われてもいる。暮らしと産業とを同一視してよいのかは不明だが、やはりなんだか似たような話に聞こえる。
うま味調味料とYouTubeが重なって、物凄い勢いで村の景色を変えていく様子に、自然で当たり前のことなのだけれどなんだかさみしい、行き場のないノスタルジーを感じていた。