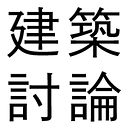ブルネレスキ的建築家について
第2章_ 職能形成期に生じた理論と実践的経験知の葛藤
今回の記事ではP.L.ネルヴィ(1981–1979)が、1913年に卒業してから実務の経験を初めて積むことになる施工会社での職能形成期の話をとりあげる。ネルヴィが同施工会社に所属している期間に書いた雑誌記事と施工管理を行った2本の橋梁から、その当時のネルヴィの設計理念の形成過程を辿ってみる。
ネルヴィは1913年から1923年までセメント建設会社(Società Anonima per Cemento Costruzioni, SACC)に勤務している。その施工会社の創設者は、ボローニャ技師養成学校でネルヴィの指導教官でもあったA.ムッジャであった(図1)。SACCはエヌビック・システムをイタリアで最初期に導入して、技術事務所となった2社の内の1社であった。
ネルヴィはSACCのボローニャ事務所に勤務していたが、第一次世界大戦終戦後の1919年頃からフィレンツェ事務所の配属になっている。ネルヴィはそこで、本格的にRC造の建設を習得しており※1、ネルヴィが最初期に担当した建築物は1921年に竣工したペロタの競技場の屋根であった※2。その球技用競技場の意匠設計者でありローマで活躍した建築家A.コッペデ(1871–1951)と共に、ネルヴィは競技用の空間として必要な約16mの径間にかける屋根の意匠・構造設計の補助と工事管理を担当している※3 。最初期の担当では施工者として、ネルヴィは現場を管理している。
その後、ネルヴィは1922年にチェチナ橋と1923年にペシャ橋を担当する。いずれの設計施工においても設計補助としての関与であったが、ネルヴィが意匠・構造設計から施工監理までを一貫して行った最初期の事例と言える※4。竣工後にネルヴィはチェチナ橋とペシェ橋について『インジェニェーリア』(Ingegneria)という工学雑誌にそれぞれの橋を紹介する記事を投稿している。さらに、別の雑誌の編集者にも掲載を打診するなど、2本の橋梁に対するネルヴィの思い入れの強さを伺い知ることができる。
2–1 アッティリオ・ムッジャとSACCの事績
ムッジャはイタリアでのRC導入時期に活躍したRC建設の第一人者であり、RC建設技術の教育に対する功労者でもある(図1)。ムッジャも前話のカネヴァッジの指導を受け、1885年にボローニャ技師養成学校で土木工学の学位を取得している。彼の卒業計画は新古典主義の劇場であった。それにより1886年に建築のクールランド賞を受賞している※5。その後、芸術学校に通い建築家の資格を取得して、1891年からボローニャ技師養成学校の講師として図式解法などの構造力学や建設技術の講義を行っている※6。そうしたことからC.グレコは、ムッジャを科学と芸術の両立を目指した真のエンジニア・アーキテクトと呼んでいる※7。
1898年にムッジャはイタリアの大学教員として初めてRCについての講演をエンジニア・トスカーナ学会で行なった※8。1904年にもトスカーナの建築家エンジニア会の会長からの依頼でRCについての講演を行なっている。そこではRCの起源と発展についての説明をした。当時モニエ・システムやメラン・システムなど様々なRCの建設方式があったが、ムッジャはその全体像の中でエヌビック・システムの重要性を主張している。その講演内容は「国際新技術報告」に記されている※9。1905年にムッジャはナポリとパレルモの学校で教授職を得て、さらに1912年にボローニャ技師養成学校で教授に選出され、1913年にはネルヴィの卒業設計を指導した。1923年から1927年までムッジャはボローニャ技師養成学校で校長を務めている※10。
ムッジャは建設業も営んでいた。当初「エンジニア・ムッジャ工学建築スタジオ」(Studio di ingegneria e architrttura ing. Muggia)及び「エンジニア・ムッジャ社」(Società Ing. Muggia)を設立し、ボローニャのポルタ・マスカレッラ(Porta Mascarella)に本社を置いている※11。1903年からはフィレンツェのレオネ・ポッジと提携して、エンジニア・ムッジャ&ポッジ社(Società ingg.Muggia e Poggi)を設立している。そして、1908年にボローニャとフィレンツェの建設会社を統合してSACCを設立した。1911年にSACCはトリノの博覧会にRC造の橋梁や階段の一部を出展するなど、イタリアのRC建設を牽引する施工会社となった。
1895年にムッジャはエヌビック社から特許を購入している。最初期にこの特許を利用できたイタリアの建設会社は特許の広告(図2)の通り9社であった。その中で技術事務所であったのは、ムッジャのSACCとポルゲットゥの施工会社の2社だけであった。技術事務所は施工だけでなく、エヌビック社と協働か単独で意匠・構造設計を行うことができた。SACCはその権利を利用して建築や土木に限らず、農業や海洋の施設をRCで建設して行っている※12。
ムッジャの施工会社の設立当初からネルヴィが入社する1913年までのSACC社の業務は、主に石やレンガ造の伝統的素材をRCで代用する建築物が多かった。それまでムッジャは石造の躯体上部に木造の小屋組を架けていたが、屋根架構をRCにすることから導入を始めている。それから、ムッジャはRCを建物の躯体にも利用できると確信すると、支柱や階段などにも利用を始めている。しかし、ムッジャはボローニャ銀行などでは(図3)、RCの躯体をそのまま表面に現すことはせず、モルタルのモールディングで隠している(図4)※13。それは、この当時はまだムッジャの中に石造の名残があり、RCを用いて石造建築として仕上げようとした結果であろう。
一方で工場や倉庫などの建物ではRCの骨組みを露出した表現が試みられている(図5)。そして、RCの特性を活用した建設は橋梁にも展開されていった。1905年にSACC社はマグラ橋を建設している(図6)。これはアーチ支間50mの5連アーチ橋であり1910年には61mの単アーチのサヴィオ橋を建設した※14。図6と図8の接合部を見ると、両橋梁はヒンジを使用しない不静定構造物であることがわかる。
そして、ネルヴィが勤務し始める1913年以降、SACCはそれまでより大きな無柱空間の工場や倉庫を建設し、プレファブ工法などの新しい技術を導入する取り組みを行なう。晩年、ムッジャは1926年から1927年にかけて行わられたジュネーブの国際連盟本部の選考委員にイタリア代表として選ばれている。最終投票時にムッジャは伝統の擁護を主張して、ル・コルビュジエの案に反対票を投じたと言われている※15。そういった面でモダニズムやイタリア合理主義と関連しているネルヴィとムッジャの間に意見の食い違いが生じていた。
2–2 SACCでのネルヴィの橋梁設計
ネルヴィが『インジェニェーリア』誌に寄稿した記事2編は、設計施工を担当したチェチナ橋とぺシェ橋の2本の橋梁に関するものである。それらには橋梁の概要や竣工検査の結果などが記されている。
2–2–1 静定構造物のチェチナ橋(1922)
チェチナ橋はピサ県のサリーネ・ディ・ヴォルテッラとポマランチェの間に位置する県道マッセターナに架けられたもので※16、全長92.798mのRC製3連ローゼ橋である(図9)。SACCのフィレンツェ事務所が意匠・構造設計、施工監理と工事管理を担当した。ネルヴィは『インジェニェーリア』の1922年9月号に「チェチナ川にかかる鉄筋コンクリート製の橋」を寄稿し、載荷試験の検査結果について報告している。橋の構造解析について、ネルヴィは橋桁の構造体をトラス構造として計算したと述べている。つまり、アーチと吊材の接合部に実際は曲げモーメントが発生するが、考慮するほど大きくないとして、理論上では除外して計算したのである※17。これらの記述からネルヴィがチェチナ橋をピン接合として検討していることがわかる。
表1はリソルジメント橋、チェチナ橋とペシャ橋の各要素の概要を整理したものである。チェチナ橋の第1案(図10)はリソルジメント橋のようなスパンに対してライズが低いアーチ橋の検討であるが、実施には至っていない※18。チェチナ橋の第1案から第2案の変更は2点ある※19。1点目はライズを3mから3.15mにより高くしたことである。それは施工性の向上が検討されている。2点目は床版を結ぶ部材をトラスから格子(斜材なし)に変更している※20。さらに、チェチナ橋の第3案(図11)は橋の形状を変えてアーチ橋からボウ・ストリング形のトラス橋に変更となった。そしてライズが7.0mとなり、第1案や第2案に比べて高くなっている ※21。
また、チェチナ橋の第3案と竣工時の写真(図9と図11)を比較すると、つなぎ梁の向きが異なっていることがわかる。RC造の放物線形状の橋桁の中央の垂直部材にかかる斜材の向きが両案で異なっている。第3案では逆V型になっているが、実施案ではV字となっている。そうすることによって、実施案では橋桁中央の垂直材を押し込む方向へ応力が流れるように考慮されている。第3案まではS造で作ることが検討されている。そして、橋の形状は第3案から上路アーチから下路アーチへと変更されている。そして床版と橋桁が一体となり構造的に自立するようになった。それから床版と橋脚・橋台の接合部の全ては剛接合ではなく、片側にローラーが設置されているのがわかる(図12と図13)。
さらに研究者のグレコは、ムッジャが1912年から1913年にチェチナ橋の意匠設計が行われていたと指摘している※22。しかし施工は延期され、第一次世界大戦後にフィレンツェ支社で再度設計されることになった。変更を依頼するムッジャからネルヴィへの指示に関する資料が残っていないため、誰の指示によりこの変更が行われたかは明らかになっていない。しかし、ネルヴィも含めたフィレンツェ支社での設計施工になったことによる大掛かりな変更であろう。また、施工に際して各部材同士の接合部の検討も行なわれたている。最終的なチェチナ橋の構造形式は、不静定構造物にせずに、橋の片側をピン接合として、静定構造物とする設計変更が行われている。
2–2–2 不静定構造物のペシェ橋(1923)
ぺシェ橋はSACCのフィレンツェ事務所がフラテッリ・マルキ(Fratelli Marchi)社のために建設したものである※23。この橋は事業主の肥料工場から最寄り駅までの最短経路を路面電車で輸送するために計画されている。そのため、構造計算上トラックだけではなく路面電車の通過が想定されていた。
ぺシェ橋の形状はフィーレンディール型の4径間ラーメン橋で(図14と図15)、全長は71.1mであった※24。その内の1つの径間には傾斜があり、スパンも16.83mと他よりも短くなっている。ペシャ橋はアーチ橋ではないが、各径間に対する梁せいが低く抑えられている。ネルヴィ達はリソルジメント橋の様なスパンと梁せいの比の低い橋の実現を目指していた※25。そのため床版と川の水面までの距離を確保するために逆梁が採用されている。また、ぺシェ橋の各接合部は剛接合とされ、橋全体は不静定構造物とされた。そのため一体的に荷重に抵抗でき、諸応力に耐える能力に優れていたが、熱膨張による変形に対応する必要が橋台と床版の接合部に生じることとなった。
この問題について、ネルヴィは「温度変化の影響による橋桁の自由な拡張に対する橋脚自体の可塑性を考慮しても、橋脚自体の厚さが薄くそれゆえ抵抗できるモーメントがわずかなので橋脚から桁を解放する可能性を考えなかった」と述べ、熱膨張による変形は無視できると見積もっている※26。逆に「橋桁から橋脚を解放することは橋全体に避けられない弱さをもたらす」として、ローラーの使用を否定している※27。
2–2–3 橋梁の検査方法について
2本の橋梁については載荷試験が行われた※28。チェチナ橋では19トンのローラー車1台を通過させ、その前後の変位が測定されている※29。結果についてネルヴィは「放物線形状の橋桁の最大垂直変位(freccie)は0.4mmであり、評価に値する変形(residuo)は無かった」と述べている。また「床版の縦桁と横桁の骨組みでは0.5mmの変位が見られ、0.1mm未満の変形が測定されたと報告している※30。
ペシャ橋では2台のトラックを連続して通過させ発生する各径間の中央の変位が測定された。2台のトラックの重さは8.2トンと9.0トンで合計17.2トンであった※31。ネルヴィはぺシェ橋の「垂直方向の塑性変形(freccie permanenti)は全体でも各径間でもゼロである。また弾性変形と平均積載量との比率も1/15000以下」であったと述べている※32。また路面電車による負荷については「換算によって考慮される最大の荷重を加えていないが、路面電車の負荷よりも約25%少ないトラックの負荷による、その比率の測定結果がこの構築物の安全性を保証する」と結論づけている※33。以上で述べた2つの橋の測定結果を表2にまとめた。
ネルヴィは数式による構造解析を行うだけではなく、このように建設後に橋の変位を測定することで、構造解析の妥当性を実証している。なお、静定構造物のチェチナ橋にはわずかながら塑性変形が生じている。それにより1923年頃にネルヴィは弾性変形だけでなく塑性変形への関心を持ち、それについて調査をしていたことがわかる。さらに、結果として、剛接合の橋梁の方が、ピン接合の橋梁よりも変形が小さいことをネルヴィは実作を通じて経験することとなった。
2–3 SACC期の雑誌投稿記事
ネルヴィがSACC期に書いた雑誌記事は合計で12編ある(表3)。その全12編の中から航空雑誌『ラエロナウタ』の記事「気球内ガスの部分的浄化の可能性と利益について」(No.1)は、内容が建築・建設以外のことであった。また、その他の11編について※34、内容の類似性から判断して、①職能論(No.2,No.6)、②建設材料と施工技術(No.3–4,No.7)、③フランス雑誌の紹介(No.8,No.10–11)と④橋梁の構造設計と強度試験(No.5,No.9,No.12)という4つのテーマに分けることができる※35。このWeb記事では詳細は扱わないが、SACC期にフランス雑誌の先進技術の紹介をネルヴィが担当していたことは着目に値する。特にRCでのピン接合の施工方法に関する記事には、ネルヴィのその当時の関心が現れていて興味深い。もし、興味を持たれた方は、詳細を拙稿に記しているので参照していただきたい※36。
2–4 まとめ(理論と実践に対するネルヴィの配慮)
本章ではボローニャ技師養成学校の教授で、セメント建設会社(SACC)の創設者であるムッジャの経歴と業績をまず概観して、ネルヴィが1913年から1923年まで勤務したSACCでの業績を確認した。ムッジャはイタリアへエヌビックシステムという新しい建設技術を理論だけではなく、実践した人物であった。その導入期において、ムッジャはRCの構造体が装飾によって被覆されるべきと考えており、後述するネルヴィの設計思想への影響がみられる。
エヌビックシステムの導入当初のムッジャの建築物には、RCの躯体にモルタルでモールディングを施すなどの石造的表現が残っていた。ムッジャは倉庫や橋梁の建設経験を経て、RC独自の表現や建設方法を模索していたと言える。その結果としてマグラ橋やサヴィオ橋では、ヒンジを用いない一枚岩のような不静定構造物のアーチ橋を建設している。エヌビック社から不静定構造物の建設方法が、ムッジャへと引き継がれている。
一方でネルヴィはSACCでコンクリートの素材やS造をRC造で変換する実践を通じて、エヌビック式のRC造の建設方法を習得していった。ネルヴィの橋梁建設の実践として、静定構造物のチェチナ橋と不静定構造物であるぺシェ橋の意匠・構造設計と施工監理がある。チェチナ橋では床版と橋脚の接合の一部にローラーが設置されピン接合として建設されている。またぺシェ橋は接合部が全て剛接合のラーメン橋となっている。ネルヴィは二本の橋梁の竣工検査結果について雑誌記事を書いているが、そこにはチェチナ橋にだけ塑性変形が発生したという結果が記されていた。これはピン接合を持つ静定構造物のRC造橋梁の性能の悪さが示されている。
ネルヴィは静定構造物の建設方法も学びながら、エヌビックシステムを使ったムッジャの不静定構造物の建設方法を経験して、後者の建設方法を習得していった。つまり、RC造の不静定構造物を建設する際に行われるエヌビックの経験主義的設計や建設方法をムッジャから単に受容したわけではなく、実践を通じて不静定構造物の施工上の性能の優位性を確信している。
さらに、ネルヴィは施工者としての建設経験だけに頼らず、科学的実証である計算による構造解析や載荷試験などの安全性の確認が必要であるという考えを形成し、その実践的な方法を模索していった。当時の数学的方法による構造解析の限界をリソルジメント橋の授業で知るだけではなく、橋梁建設の実践で経験主義的な設計施工の危険性を感じ、実証を伴った安全性の確認方法について関心を深めていったのである。
次回の最終章では、ネルヴィが戦後にローマ大学で行った授業内容と、ブルネレス的建築家の今日的意義について見解を述べたい。
第2章註
※1 C.Greco: PIER LUIGI NERVI Dai primi brevetti al Palazzo delle Esposizioni di Torino 1917–1948, Lucerne, 2008, p.39. A.ムッジャだけではなく同事務所の部長L.ポッジ(1877–1953)からの指導もあり、ネルヴィのRC技術の習得については、これらの2人からのその影響がある。
※2 C.Greco, op.cit., p.41
※3 C.Greco, op.cit., pp.40–43. 施工監理をしたのは、A.コッペデである。
※4 C.Greco, op.cit., pp.44–51. 工事管理も同会社のフィレンツェ事務所が行っている。
※5 A.Muggia: Progetto di un Teatro, Tip. Lit. Camila a Bortolero, Tolino, 1892.
※6 C.Greco, op.cit., p.23.
※7 C.Greco, op.cit., p.25.
※8 Ibid.
※9 A.Muggia, Sulle Costruzioni in cemento armato, Nuova Rassegna Tecnica Internazionale, 1904.4.
※10 C.Greco, op.cit., p.23.
※11 C.Greco, op.cit., p.25.
※12 C.Greco, op.cit., p.23.
※13 C.Greco, op.cit., pp.28–35.
※14 C.Greco, op.cit., pp.35–36.
※15 C.Greco, op.cit., p.35.
※16 P.L.Nervi: Ponte in cemento armato sul Cecina tra Pomarance e Saline di Volterra, Ingegneria, n.5, 1922.12, pp.126–127.
※17 Ibid.
※18 C.Greco, op.cit., pp.44–45.
※19 Ibid. チェチナ橋の第2案は図面がないが、上記の既往研究により変更点が明らかになっている。
※20 Ibid.
※21 L. Santarella and E. Miozzi: Ponti Italiani in Cemento Armato, Ulrico Hoepli, Vol.1, pp.139–146, 1924 (同書第2巻に掲載の図24により高さを判断した。)
※22 C.Greco, op.cit., pp.44–45.
※23 P.L.Nervi: Ponte sul Flume Pescia, Ingegneria, n.8, 1923.8, pp.232–233. 建設地はフィレンツェの北西に位置する、ルッカとモンテカティーニテルメの間を流れるペシャ川である。
※24 Ibid.
※25 ペシャ橋に関しても変更を指示する手紙等の証拠が残っていない。しかし、ぺシェ橋の接合部を剛接合とするべきと述べたネルヴィの雑誌記事、リソルジメント橋のライズ/スパン比とぺシェ橋の梁せい/径間比のル類似を考慮すれば、異なる橋の形態ではあるけれども、ぺシェ橋の設計にリソルジメント橋を参照した可能性がある。リソルジメント橋は低ライズのアーチで、ぺシェ橋は梁せいの低いフィーレンディール橋であった。
※26 P.L.Nervi, op.cit(25), 1923.8, p.232.
※27 Ibid., p.233.
※28 P.L.Nervi, op.cit(16), 1922.12, p.127.
※29 Ibid.
※30 Ibid.
※31 P.L.Nervi, op.cit(25), 1923.8, p.233.
※32 Ibid.
※33 Ibid.
※34 P.L.Nervi: Sulla possibilità e convenienza di una parziale depurazione del gas del palloni, L’Aeronauta, 1918, pp.163–169. ネルヴィは第一次世界大戦中にイタリア軍空軍の一員として作業した航空機用水素ガスの供給についての記事を書いている。ネルヴィは技術的にも容易で費用が抑えられる酸素の供給により航空機の内側を洗浄できれば、洗浄用の新しい別のガスを節約できるとした。ネルヴィは航空工学や機械工学に興味があり、戦間期にはモーターの特許を取得している。しかし本論のRC建設の内容と直接関係がないため詳細な分析からは除外している。
※35 C.Greco, op.cit., pp.57–59. この他にもSACC時代に取得したRCに関する特許(同書, pp.54–56)について、ネルヴィが担当しているかは定かではないがSACCのフィレンツェの事務所が担当した他の橋等の建設(同書, pp.50–53)について、そして、ネルヴィが個人で請け負った仕事(同書, pp.56–57)などの紹介がある。
※36 拙稿:ピエル・ルイジ・ネルヴィの形成期における橋梁の建設とその背景,日本建築学会計画系論文集, 82(740), 2017.10, pp.2713–2721.
図註
図1:Claudio Greco: PIER LUIGI NERVI Dai primi brevetti al Palazzo delle Esposizioni di Torino. 1917–1948, Quart Edizioni Lucerna, 2008, p.20.
図2:Tullia Iori: 150 anni di storia del cemento in Italia Le opere, gli uomini, le imprese, Gangemi. Editore, 2011, p.54(1894)
図3: Claudio Greco: PIER LUIGI NERVI Dai primi brevetti al Palazzo delle Esposizioni di Torino. 1917–1948, Quart Edizioni Lucerna, 2008, p.31.
図4:Ibid.
図5:Ibid., p.33.
図6〜図8:Ibid., p.36.
図9:Ibid., p.44.
図10〜図11:Archivio Muggia (L’Ordine degli Architetti di Bologna)より図面を入手
図12〜図13:Archivio Muggia より入手した図面を元に著者が作成
図14〜図15:Claudio Greco: PIER LUIGI NERVI Dai primi brevetti al Palazzo delle Esposizioni di Torino. 1917–1948, Quart Edizioni Lucerna, 2008, p.51.