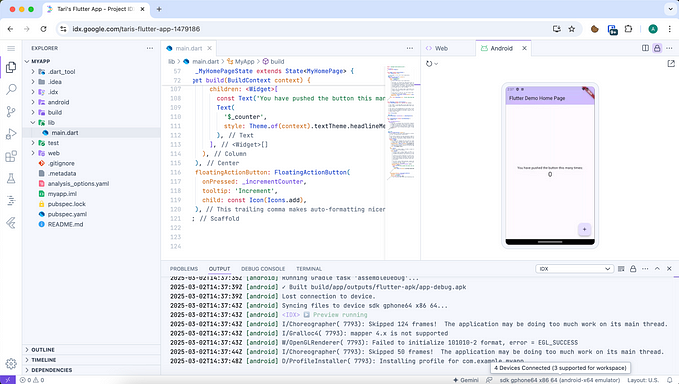ホットスポットでの住民活動
「フクシマ」の過去、現在、未来 10/ Resident Activity in Hot Spot (Radioactive contaminated area) / 菅野昌信
1.はじめに
私の住む福島県伊達市霊山町小国地区は世帯数400余り、人口1400人弱の県中通り阿武隈山系の北部に位置する山里に抱かれた中山間地域である。地区内には小学校が1つ、自治組織は2つで9行政区からなり、自給的な農家が多い地区である。私も家族で食べるだけの米や野菜を栽培している。
『建築討論』のテーマにふさわしいかどうか疑問ではあるが、2011.3.11以降起こった原発事故被害に対応した住民活動を建築士というより地区内の一住民として報告させて頂く。


2.原発事故被害から特定避難勧奨地点の指定
福島第一原発から北西に約55km離れた小国地区にも東日本大震災後の原発事故で大気中に放出された放射性物質が地表に降り落ち、いわゆる“ホットスポット”と呼ばれる高濃度汚染地点が地区内に多数発生した。2011年6月中旬、国は各住戸の玄関先1mと庭先の2箇所の地上50cmと1mそれぞれの放射線の空間線量を測定した。その後、国は事故後1年間の積算放射線量が20msvを超えると推定されるところを「特定避難勧奨地点」として地域的なまとまりではなく世帯単位で指定した。小国地区では同年6月30日に86世帯、11月25日に4世帯が追加指定となり、計90世帯、地区内の約2割の世帯が特定避難勧奨地点として指定となった。ちなみに私の家は比較的線量が高い地区にあり、地区の7割を超える世帯が指定を受けたが私の世帯は指定から外れた。
特定避難勧奨地点に指定されても、一律に避難させられたり事業活動を制限されるものではなく、全て住民の自主的判断に任せられた。指定された世帯には避難する、しないに関わらず精神的な賠償費用(一人に月額10万円支給)のほか、市県民税・固定資産税・国民健康保険税・国民年金保険料などの納税免除、生業補償、避難先の家賃補助、生活家電製品の提供、義援金や支援品の受給など様々な支援策がとられた。一方、それほど空間線量に差はないにも関わらず特定避難勧奨地点に指定されなかった世帯には、福島県内の他の地域と同じような賠償金が出されたのみでそれ以外の支援は何もなかった。
南相馬市では指定基準を明確に公表したが、伊達市は基準を最後まで公開しなかったために指定をめぐる不信感に加え、指定の有無による格差があまりにも大きく、指定をめぐって地区内は大混乱を起こしコミュニティーを崩壊させた。更に、地区住民が困惑したのは、指定を受けても避難せずに今まで通りの生活を継続することができたことにあった。賠償や数々の支援を受けながら従前と変わりなく生活している指定世帯とその隣で何の救済策も受けられない世帯との間では感情的なわだかまりはとても大きいものがあった。顔を見ても挨拶もしたくない、話もしたくない、もちろん酒など一緒には飲めないなど、以前の家族同様の近所づきあいとは雲泥の差となった。
地域住民に対する事前説明にも問題があったように思われる。新聞等で小国地区にも特定避難勧奨地点の指定が近々行われるようだと報道されていたが、市が行った説明会は指定の2日前であった。説明会には地区住民の半数以上が集まった。初めて経験する放射能汚染に対する不安や関心がどれほど大きなものだったか。説明会の会場は異様なほどの熱気に包まれ質疑応答も途切れることはなく、その様子はテレビでも放映された。
特定避難勧奨地点の指定、更には2012年12月に住民不安となる住宅地除染がひとまず完了したとのことで特定避難勧奨地点の指定が全面的に解除されたが、対象世帯に対して説明会の開催は一度もなく、指定も解除も市から一方的な通知書のみであったようだ。


3.住民組織の結成と活動
2011年3月の原発事故以降、国・県などは原発事故汚染の実態調査を数多く行いながら、情報はあまり提供されず地区住民は不安な中での生活を余儀なくされていた。今まで通りこの地で生活できるのか?この地の食べ物は安全か?今後、速やかに詳細な実態調査や有効な対策はしてもらえるのか?様々な不安や疑問があったが行政等から具体的な計画や支援策は何一つなかった。
行政の対応を待っているだけでは何ひとつ解決しないという危機感から2011年9月住民有志による「放射能からきれいな小国を取り戻す会」(以下「取り戻す会」という)を設立した。会員数約300名、約260世帯からなり、地区の約6割の住民が活動に参加した。
無用な外部被爆や内部被爆を受けずにすむことを目的に活動した取り戻す会などの住民組織に私が関わった主な活動について紹介したい。
(1)空間放射線量の測定調査マップの作成、配布
伊達市は2011年9月に市内全域の第一回放射線量測定マップを各戸配布した。小国地区は市内でも最も放射線量が高い地域のひとつとはわかったが、マップが1kmメッシュのため、それがどこの地点のデータなのか実感に乏しく、数値も高いところで毎時3.5μSV以上と示すだけでどこまで高いのかが不明でもあり不安でもあった。
外部被爆をなるべく受けなくて済むよう、この地区にふさわしい空間線量測定マップを作ろうと考えた。山林は平地より汚染が高いと思われたが、測定時の安全面を考慮し測定対象からは外し、通常の生活エリアである住宅地や耕起していない農地・公共用地を対象とした。線量測定は地区内を100mメッシュ毎に区画し、各メッシュ2地点で地上10cmと1mの測定を行った。マップとして採用した値は2地点のうち数値の高い方とし、測定高さ地上10cmと1mの2種類のマップを作成した。100mメッシュにした理由は、それほど個人が特定されずに生活実態として理解される広さであること、更には各行政区内の測定を1週間程度で終えて頂くためであった。第1回の測定地点は533箇所あり、市で測定したマップより100倍以上の精度となり、地区住民にとってもわかり易いマップとなった。
測定の結果、地区内が一様の汚染ではなく地区の南部や北部は比較的線量が低く中心部が高いことが判った。また、高濃度の個所は地区全域の各所に点在していることも判った。特定避難勧奨地点に指定された地域は地区内でも線量が比較的高い地域であることが私たちの測定からも類推できた。地区住民にも汚染の実態を理解してもらうことを願い、測定結果をマップ・印刷し、会員全戸に配布した。
2011年10月に第一回測定調査、11月に会員世帯に全戸配布、以後毎春に測定、マップ配布を継続し、2017年7月で第7回調査・配布となった。




(2)食品測定所の開設
自分たちが作り、口にする食べ物は安心か、無用な内部被爆を受けないように食品測定を行いたいと思った。自給的な農家が多く、地区内に留まって生活するにはそこから採れる農産物の安全確認は重要である。
(株)カタログハウスが全国の読者に義援金を募り、それで購入した食品測定器(応用光研工業製FNF-401)を私の知人がボランティアをしていた福島市の市民放射能測定所の計らいで小国にも設置する事ができた。2011年11月末に1台、さらに12月末にもう1台と合計2台が市所有の地区公民館の中に場所を借り、取り戻す会の下部組織「おぐに市民放射能測定所」として運営した。設置当時、2011年産米の出荷時期と重なり、2台フル稼働の状態で地区内の玄米を測定し始めた。測定のなかで、当時の暫定基準値に近い430Bq/kgの玄米がでた。同時期、福島県から小国地区でも基準値越えの米が出たとの報道がなされ、2012年には米の作付制限の対象地区となった。
地区で採れた農産物を食品測定器で数多く測ることにより汚染の実態把握に努めた。その数値は会員間で情報共有・公開を原則とし、食品による内部被曝の危険回避を図る願いがあった。測定データは地区以外にも公開を原則とし、測定所内の閲覧の他、ネットワーク測定所のホームページ上でも公開した。地区内の住民事情もあり、紙ベースの測定所だよりを月1回程度発行し、最新話題の提供を行った。
これまで計測してきた結果だが、畑で採れる野菜にはセシウムの移行が大変低いことがわかり、今では検出限界以下である。米も栽培前のカリウム散布の効果でセシウムが抑制されるようになり、県で行っている全量全袋調査の後、当測定所で再度測っても検出限界以下となっている。
2017年10月現在、食品の出荷制限となっているものは、原木シイタケ、野生のキノコ類、タケノコ、ワサビ、こごみ、コシアブラ、タラノメ、フキノトウ、ワラビ、栗となっている。
出荷制限の食品数は少しずつ減ってきてはいるものの、依然として山菜、キノコ類や山の果実は数値的に高いものが多い。時間経過に関わらず相変わらず高いままのものもあるため食品測定を継続していく必要性を感じている。


(3)研究機関(東京大学・福島大学・日本女子大学等)との連携・協力
2012年小国地区が米の作付制限になったことを受けて、その原因究明と営農意欲の継続のために伊達市政アドバイザーの東京大学大学院根本圭介教授が中心なり福島大学はじめ多くの大学の協力を得ながら、福島県内でも唯一例年通りの栽培管理で行う米の試験栽培を小国地区で行った。米へのセシウムの移行がどのようなメカニズムで起こるのか用水や地域性があるのかなど地区の問題解明のために取り戻す会としても協力した。地区内を満遍なくサンプリングできるように試験圃場(41筆60枚、地権者34名)の選定や栽培協力者の取り纏めを行い、各圃場での試験栽培の作業協力も行った。小国地区で行った試験栽培の成果もあり、2013年にはセシウム抑制のため栽培前のカリウム散布を条件に米の作付制限が解除された。
2011年春、福島県が圃場調査のために行った4kmメッシュの土壌分析のサンプリング調査から小国地区が外れたこともあり、地区内の農家は農地土壌の汚染度に不安を持っていた。2012年東京大学や東京農業大学の尽力で地区内の田畑の土壌分析調査をしてもらえることになり、500箇所を超える土壌サンプル採取を取り戻す会で行った。分析調査の結果は大学から全て地元農家に還元され、2013年以降の営農再開の貴重な資料となった。
また、2012年9月以降、日本女子大学との共同研究として、大学と取り戻す会の主に女性会員が協力しながら、調理法に依る食物のセシウム低減対策や外部被曝を防止する被服の研究を行っている。2017年、それらの功績で取り戻す会の担当委員会が日本女子大学第10回家政学部賞特別賞を受賞した。


(4)復興プラン提案委員会の参画
伊達市としては小国地区の原発事故被害に対応したいが、具体的な案が浮かばないので地元から提案して欲しいとの要請があった。2013年12月地区内有志により小国地区復興プラン提案委員会を設立した。会の活動は農業振興、福祉健康、生活環境の3分科会からなり、それぞれの分科会には福島大学の先生にも顧問として数多く参加して頂いた。各分科会ではそれぞれのテーマで住民アンケート調査を行った。質問項目の選定は各分科会で行ったが、プライバシー保護の観点からアンケートの開封・集計・分析まで全て福島大学にお願いした。
私は事務局次長の立場で、主に生活環境分科会での活動を行った。住民アンケート調査のほか地区内の実態調査を福大の先生と共に行った。当時、伊達市ではまだ防火水槽は除染対象とはしていなかったが、地区内10数か所の底泥や水を採取し福大で分析してもらうと、かなり高濃度の放射線量が計測された。そこで、それらの測定データをもとに市議会議員を通して市へ働きかけをしてもらった。その結果、小国地区のみならず市内の比較的高線量と思われる地区にある防火水槽の除染が実施されることになった。
2013年4月小国地区の上水道拡張整備計画の説明会が市からあった。市の計画では小国地区全域ではなく、最南部の山間の約60世帯弱は対象エリアから外れていた。この地区は周辺が山に囲まれているが、山が浅く昔から水量に不安を持つ地区である。各世帯では井戸を頼りにしているが、殆どが浅井戸で水量と水質に不安があり、なかには沢水を利用している世帯もあった。原発事故以降、地区内では飲料水に対する不安が高まり、上水道利用の希望が大きくなっていた。
上水道拡張整備の対象エリアが地区全域でないことに違和感を覚え、2014年6月福島復興局で福島再生加速化交付金の内容説明を聞いた。メニューの一つに水道施設整備事業があり、対象地区としてあえて特定避難勧奨地点を加えていることを知った。ちょうどその時準備していた生活環境分科会のアンケート調査に上水道拡張整備エリアから外れた地区を対象に上水道整備に関する調査項目を急遽加えた。集計してみると殆どの世帯が上水道の必要性を感じていた。アンケート結果をもとに市へ地区全域を上水道拡張整備にするよう要望を行った。殆どの世帯が熱望しているという数字が市を動かしたのか、2016年地区全域に上水道整備エリアが広がり、現在工事が進められ今春には終える予定となっている。
(5)損害賠償の証拠資料となった空間線量測定マップ
特定避難勧奨地点に指定されなかった小国の住民の殆どは、線量の差がわずかなのだから地区全域を指定して欲しいとの要望書を2011年7月に国に出したが、国からの反応は何もなった。そこで、取り戻す会とは別組織の小国地区復興委員会(会員は殆ど重複している)が設立され、原子力損害賠償紛争解決センターに精神的慰謝料を求めるADR(裁判外紛争解決手続き)の集団申立てを2013年2月に行った。申立人は297世帯、910人となり、指定されなかった世帯の約9割にのぼった。
2013年12月に同センターから一人月額7万円の慰謝料を賠償することの和解案が出され、2014年2月東京電力が和解案を受諾し、地区住民との和解が成立した。和解案の理由は伊達市内の他の地域に比べ明らかに高線量の傾向があり、放射線被爆への恐怖や不安は現実的かつ具体的で、しかも格段に大きい。特定避難勧奨地点の居住者と同一生活圏で活動している申立人についても指定された居住者に準じた生活上の様々な制限・制約が生じており、特定避難勧奨地点の居住者に準じて賠償されるべき損害と考えられるとのことであった。
申立ての途中で、被災者弁護団から取り戻す会が作った第1回空間線量調査測定マップや測定データを提出して欲しいとの依頼があり、資料提供を行った。その資料が原発事故後7ヶ月経た地区の汚染を証明する決定的かつ重要な証拠となったことを後日伺った。
4.むすびに
特定避難勧奨地点の指定の有無をめぐって感情的にまでなった住民間のわだかまりは、2014年2月ADR申立ての和解以降、徐々に緩和されてきている。市の自治組織に対する方針もあり2015年4月に2つの区民会が統合し、夏祭りをはじめとした統一的な行事も数多く開催され、地区内の融和が進みだしている。
事故後に転出された方も、依然として地区外で避難生活を続けている方もいるが、ある程度の世帯は戻ってこられ、Uターンした住民や放射能の低減を計るため建替えを選んだ住宅新築、その他既存住宅の増改築やリフォームも増えてきている。
謝辞
不安がなくなったわけではありませんが、 地区の復興が少しずつ形になり住民も落ち着いてきているのを感じ、これまでの活動が少しでも地域に役立ったのであればうれしく思います。私がしてきたのは、企画・立案とコーディネートそれに少しだけ皆さんの前で想いを口にしただけです。賛同し協力して頂いた地区の人達の持つポテンシャルの高さや行動力に、そして家族に随分と助けられました。また、原発事故以降、心配して頂いた大学の先生はじめ本当に多くの人達に助言やご協力を頂き、なんとか活動を続けてくることができました。原発事故がなければ一生お会いすることもなかったかもしれない多くの人達のご支援に支えられ、背中を押して頂きました。目に見えない、色も匂いもない放射性物質を測定するために必要な機器(食品測定器や空間線量測定器)を貸して頂いている(株)カタログハウスにも大変助けられました。改めてこの場をお借りし、ご支援ご協力を頂いたすべての皆様に感謝申し上げます。