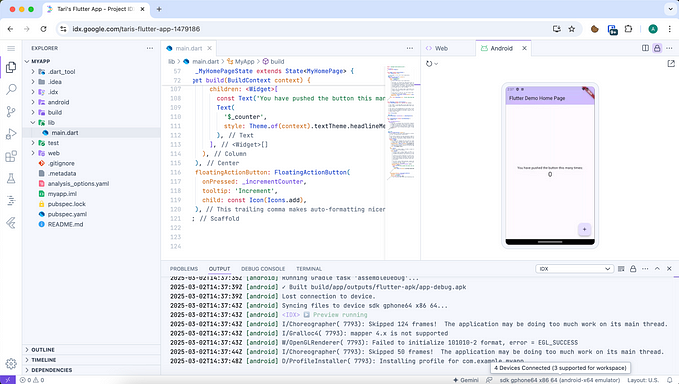奈良県立図書情報館概要
http://www.library.pref.nara.jp/
1995年(平成7年)3月に新奈良県立図書館整備基本構想を策定。2001年(平成13年)3月、施設基本設計を完了。建物の着工は、2003年(平成15年)3月18日で竣工は2005年(平成17年)3月31日。鉄骨鉄筋コンクリート造で地下1階、地上3階建て。敷地面積は、31,638平方メートル、延床面積12,123.17平方メートル。建物1階の北側と西側に駐車場スペース(普通車311台、障害者用6台、バス5台)を設置。設計は、株式会社日本設計と株式会社桝谷設計の共同体。施工は、株式会社奥村組、株式会社淺沼組、村本建設株式会社、株式会社浅川組、中村建設株式会社、株式会社尾田組の共同企業体による。
当然のことながら、公共施設に限らず、建築物には、大なり小なり「構想―計画―設計-建設(施工)」というプロセスを経て、完成―供用されるという道筋をたどる。そのようなプロセスに携わっていると、自身の到達点も完成、開館という点に収斂されてしまうが、私自身は、建設準備室在籍の6年間に加え、開館後も引き続き施設運営に携わることになり、計画段階で見ていたものと完成後に見えてきたものを同時進行的に経験することになり、現在に至っている。
施主側が提示する構想や計画と設計者・建築家の想定の間には、プロポザールなどのプロセスを経てもなおそこには相克、齟齬、交雑、相応、了解など複雑な要素が絡み合い、そうして建築物の体が整えられていく。だから例えば、照明ひとつをとってみても、照明色や照度は、図書館で本を読むとか資料を閲覧するという与件が明白であるにもかかわらず、設計という場では、空間デザインや建築物そのものの外観や内観デザインに寄りかかってしまう。出来上がってみると、雰囲気はともかく、与件を満たせているか「?マーク」がつくようなことも散見されるのである。もちろん、逆に、どんな空間をつくれば、コンセプトを満たすことができるかを、設計やデザインがうまく実現する例も多々ある。私の経験上、実はこちらの方が多いように思う。建設準備中のいろいろな提案で、設計デザインの力や魅力を感じることも多かったからである。


例えば、正面からの外観は低層の2階建て(庭園側からは3階建ての吉野建て)ながら、内観は中央部の吹き抜けと大階段によって立体感が際立ち、視覚的にも体感としても余裕のある空間構成となっている。
図書館という「場」の新たな一面
完成時は、施主と設計・施工者との関係性のなかで様々な懸案がとりあえずは完結する。そして、施設の開館後は、そのような関係性には全く関わらない人々、一般の利用者との関係性へと引き継がれていくのである。ここからは、完成までの関係性のなかでは予想できない評価軸が生まれていくことになる。また、一般的には、完成後は「引き渡され」るので、引き渡された建物には、運営する人間の評価も当然ながら加わっていくことになる。つまり、想定された目的空間が、運営の過程で変化し、別の空間へと変化していくようなことが起こることになる。ここには、計画時の社会情勢や要請から運営開始後の情勢や要請の変化も考慮されなければならないことは言うまでもない。そのような、多様な変化のなかで、あるコンセプトのもとにつくられた施設はそのような事態に対応できるのかどうか。

当館の例でいえば、正面玄関を入ると、ガラス張りの広いエントランスホールがあり、明るい開放的な空間となっている。図書館エリアの前庭のようでもあり、そこにインフォメーションカウンターやカフェなども設置されている。当初、ポスター掲示板やベンチを置くだけの想定であったが、開館を記念した一連の行事のなかで、トークとフルート演奏の夕べ(フルートは元文化庁長官の故河合隼雄氏)の特設会場としたことがきっかけとなって、この空間は、イベントや企画展示などの会場として大きな変化を遂げることになった。


そのような新たな企画をかたちにする空間は、従来の図書館機能を超えた、図書館への新たなインセンティブを生む空間へと変化した。これまで図書館という施設に目が向かなかった人々が訪れる契機になり、好奇心や興味・関心と本をはじめとする図書館資料との出合いや参加者同士の交流のきっかけにもなる「場」となった。正面玄関を入った大きな空間は、大多数の来館者が通る動線上にあり、そこでのイベントは、ちょうど街角でおこなわれているような状態となる。それを目的に来た人が集まる一方、たまたま通った人が足を止める、そんな偶然の出会いも生まれる。それが図書館という「場」の新たな一面となり、交流と出会いの空間になったのである。
ポータル的な機能を持つ「場」
図書館本体を目的としない新たな利用者の開拓は、一見目的外的なイレギュラーな印象を持たれるかもしれないが、図書館という施設の意味を脱構築あるいは拡張する可能性を秘めていると考えられる。もちろん、読書する場、調査研究の場、勉強する場、あるいは居場所としての場といった従来の機能は相変わらずではあるが、このたびのコロナ禍がいみじくも明らかにしたように、そのような従来の図書館利用が、そんなに多くはなかった、つまり大多数の人にとって、図書館は不要不急の施設だったと改めて思い知らされたところである(ただし、不要不急は無駄の意ではないことに注意する必要がある)。
だとするならば、そのような状況のなかで、公共施設として、その大多数のうちの幾人かにでも有意味な機能をつくり、新たな利用を促すことは、先の機能の脱構築や拡張といった新たな動きを考えることでもあると思われる。それは、「場」としての図書館の可能性を考えることでもある。多様な分野の知的好奇心をかたちにすること、そのための多様なはたらきかけと出会いの「場」を図書館の持つリソースとリンクさせながらプロデュースすること、そこに拡張の可能性がある。

ポストコロナやウイズコロナといった議論も喧しいが、図書館にとっては、それらのあり方ではなく、それをきっかけとした発想の転換が求められている。リアルな「場」に代わるオンラインやウエッブをはじめとする非来館サービスといった狭義の発想ではなく、「場」という概念の拡張が求められるだろう。その意味で、多様なメディアを活用したさまざまな情報発信をプロデュースするポータル的な機能が求められると思われる。
あるいは、そのような機能構築に参加する人々が集まり、活動する「場」、実験し、試行し、社会の様々な分野と連携できるような「場」が求められるのではないだろうか。それは、従来からの図書をはじめ、多様な資料の収集・蓄積と連動するかたちで、人とその活動が生み出す多様な結果や成果物がさまざまなメディアのかたちで蓄積され、アーカイブされ、新たな利用へと繋がっていくのである。そのような「場」は、リアルな場であったりネット上であったりとその時々の条件によりロケーションが変わっていくだろう。そんな変貌自在な「場」としての(ポータルとしての)図書館である。
新たな展開を生むフレキシビリティ>
そこでもう一つのキーワードが加わることになる。それは「再編集」である。集積された多様な資料や情報を、どのような切り口で編集し発信できるのか?その手法もリアルな場からだけではなく、多様なメディアによって発信することで、人や情報の繋がりと循環が生まれるのである。
個人が活用し駆使できるメディアが多種多様で容易に目的を達成できる昨今の状況のなかで、従来の図書館機能への依存度はどんどん低下していることは事実であろう。しかしそれをネガティブに捉えるよりは、そのことを正面から見据えながら、新たな「場」の創出に注力することが肝要ではないかと思うのである。ただし、ここでも注意を要することは、依存度の低下が不要とイコールではないということである。

ではそのようななかで、建築にはどのような観点が求められるのだろうか。建設計画時の設計与件を満たしながら、開館後の運営のなかでの変化にどのように対応することができるのか、ということである。強固なコンセプトは説得的であり、完成度も高いかもしれない。しかし、そうであればあるほど、完成時の完結性が、そこから始まる施設の道筋の手足を縛ることにもなるのである。このことは、ソフト面でも同様であることは言うまでもないが、つくってしまったものを改変するエネルギーは相当なハードルになる。その意味で、建築設計においては、ハード面のフレキシビリティというか代替可能性(Substitutability)のような仕掛けが必要ではないかと思われる。フレキシビリティが開館後の新たな展開を生む契機となり、ハード自らがハードの更新を支えるという事態は、中長期的な施設運用にとってもプラスとなるはずである。収容能力の増設など、そのような対応では難しい要素があることも事実であるが。
書物に例えると、ある書物はもちろんそれ自体で完結しているが、それを読む人が、めいめい傍線を引いたり、付箋を貼ったり、余白に書き込みをすることによって元の本の完結性を超え、場合によっては、元の書物に新たな意味を与え、あるいは新たなページを加え、進化するようなイメージである。さまざまな働きかけがオープンに共有化され、利害得失が介在しない「場」。そのようないわば共生空間とでもいった「場」として、ハード面においてもソフト面においても、マルジナリア(余白・脚注)の可能性を持つ必要があるとでも言うべきであろうか。