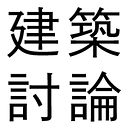桑田光平/田口仁/吉野良祐・編『東京時影 1964/202X』
今でも新たに感染する人はいるものの、街にあふれる外国人観光客の姿にコロナ前の状況を思い出し、ようやく世の中が動き始めたことを実感する。すると今度は、人どおりが消え、電車がガラガラだったあのころの風景がみるみる上書きされてしまいそうで、焦りを覚える。そんなとき、コロナ禍の3年間の空気感を封じ込めた本に出会った。
本書は東京大学大学院総合文化研究科桑田光平ゼミでの2019年度のリサーチが基礎となっている。当初は2つのオリンピック開催年1964/2020における東京とその文化の比較分析の試みだったが、パンデミックを受けて2020は202Xとなった。音楽、マンガ、映画、文学、建築などにおける東京の表象をめぐる、9名の執筆者(執筆者名を太字とする)による12編の論考と1編のエッセイから成る。1960年代を論じつつも、執筆期間はまるごとコロナ禍の時間だった。一冊の本そのものがまるでコロナの時間にひたって沈思する空間のような、不思議なまとまりをもっている。各論を行きつ戻りつ読み込むと、共通するキーワードが注意深く埋め込まれ、響き合っていることに気づく。執筆途中で互いの原稿を読み合い、論評し合ったという。執筆者が複数名であることが、東京という多面的な存在に切り込むには最適だと教えてくれる。
奥深く資料を渉猟し潜行した骨太い各論考に加えて読みごたえのあるまえがき、序文、あとがき、膨大な註、さらにエッセイ(「捏造のランデブー」平居香子)も時間を自在に行き来する本書の特長を際立たせているが、ここでは各論相互の響き合いを、いくつか紹介したい。
「コロナ禍という緊急事態における東京の風景は、そもそも都市というものが、複数の異なるレイヤーが重なり合うことで構成される空間であったことを思い出させた。不可視のレイヤーとして全世界を覆ったウイルスが可視化したのは、それまでのっぺりとして見えていた東京という都市の複層性だった。」(陰山涼、p.96)
1964から202Xへの東京の変貌の様子を、本書はしばしば「のっぺり(p.37、p.96、p.326)」と形容する。高部遼はこれを都市の眠りに着目して解く。1960年代、東京の街で暮らすフーテンたちは山手線の車両での寝泊まりを「山手ホテル」と呼んで利用していた。しかし、今や山手線内での堂々とした寝姿はタグ付けしてツイートされてしまい、すべて表面の世界へと剝き出しになっている(p.129)、と高部は言う。表面の世界は単層のレイヤーとなり、他は覆い隠されて見えない。陰山涼はフーテンたちが昼夜堂々と寝たおしていた頃の山手線を描いたマンガ(『フーテン』永島慎二)を取り上げ、さらに車窓からの風景に「段差」を発見する。そこには川を渡る高架の線路の向こうに真新しい高層ビル群、川岸に古びた低層住宅、両者をつなぐ移動手段としての鉄道、と、複数のレイヤーが存在する(p.98)。2023年現在でも山手線沿いには低層住宅が建っているが、大規模な密集地はなくなった。また、ビル群も新旧多種多様になったせいか、『フーテン』に描かれたようなくっきりとしたレイヤーは見えない。そして、「RAYARD MIYASHITA PARK」(2020年開業)の暗渠下に流れる渋谷川のように、レイヤーは地下へと覆い隠されていく(陰山、p.96)。
一方、渋谷駅の南側では「渋谷ストリーム」(2018年開業)の登場とともに渋谷川が開かれた。伊澤拓人はその「少々きつい川の臭い」に反応する(p.233)。他の執筆者たちも60年の隔たりを超えて「都市を嗅ぐ」。レイヤーが複数存在したかつての東京は、もっと強い臭いを放っていた。小林紗由里は安部公房による失踪三部作のひとつ『燃えつきた地図』での「臭気という生理的な感覚に基づく都市の描写」(p.242)を捉える。平居は、超多作超ベストセラー作家源氏鶏太の『愛しき哉』において、主人公が浮気相手とともに向かう千駄ヶ谷近辺エリアに立ち並ぶ旅館街は違法増改築が繰り返され、オリンピックに向けた機運が高まるまで浄化運動がなかなか実らなかったと記す(p.292)。また桑田は、近年販売された昭和30年代を振り返るノスタルジックな写真集からは東京の悪臭が伝わってこないと看破する(p.26)。これらの指摘は当時を知る世代が映画『ALWAYS 三丁目の夕日』に感じとった嘘臭さとも符合する★1。「臭い」を手がかりに執筆者たちは1964/202Xの東京を行き来する。
60年を経て、無臭で衛生的な東京。渋谷ストリームで「渋谷川を嗅ぐ経験は、東京という肉体の遍歴を身体的なレベルで実感させる」(伊澤、p.234)。歩く、眠る、嗅ぐ。本書には随所に身体的な実感のこもった記述が現れる。「日本中の鼻という鼻が不織布にさえぎられてい」(伊澤、p.234)たコロナの時間、「〈触れる=群れる〉という生身の体験」(吉野良祐、p.323)が制限されるなかで執筆者たちの身体感覚が研ぎ澄まされた様子がうかがえる。
日本中がマスクをしているあいだにも、日本橋に空を取り戻す首都高速の地下化工事が着工し(p.114, p.329)、「段差」解消が進んだ。シンボリックな建築なき東京は「堆積した凹凸(吉野、p.326)」となって複数のレイヤーは溶け合い、ますます「のっぺり」していく。同時に東京は、地形の起伏に何層もの駅舎と高架橋が重なる「膨大な上下動を要求する無際限な都市」(平居、p.169)として、特異な存在であり続けるだろう。そこには、今後どのような姿が立ち現れるだろうか。私たちはどのような東京を見ようとするだろうか。
まず、「のっぺり」の行く末について。「のっぺり」化が始まった1960年代、高部が取り上げる「全てがよく見えすぎてしまう「純粋な表面」と化した東京」を描いた映画(『日本脱出』吉田喜重、p.129)と、西川ゆきえが論じる「ずらりと並んだ数棟の共同住宅を暗闇に浮かび上がるような形でやや左上からの俯瞰で捉え」た写真(『団地』東松照明、p.173)に共通するのは「外から眺める視線」(p.174)だった。その視線は、伊澤が見出した「白くて「ぴかぴか光」るさまざまな製品に彩られ」た団地内部の生活を描いた文学(『私的生活』後藤明生、p.223)の描写にもつながっていく。すべて内部空間で展開するこの小説において、団地は主人公の「過去が塗り込められ葬られた」「墓場」である(p.223)。外部と内部、それぞれがのっぺりしていくのだが、伊澤によれば、それは進行するそばからほつれを見せる。「グロテスクな身体をもつ東京、その過去の記憶が埋もれる灰色の壁は、全てを塗りこめることに成功したわけではない。そこには「穴」があり、「傷」があり、文学作品はそれを見逃さないからである」(p.226)。すなわち、都市ののっぺり化は完成に至らず、必ず傷や穴が生まれる。実際に吉野は「ブックカフェ槐多」との出会いを通じて「マッスな都市のあちこちにあるはずの裂け目」(p.334)を体験する。本書表紙の装画が都市の表面に生じた穴や裂け目に見えてくる。
次に、その先の風景はどうか。執筆者たちが挙げる作品には、コロナ禍の風景を予言したかのような「静まりかえった空間」(小林、p.252)の姿がある。誰もいない東京を写した写真作品(中野正貴《TOKYO NOBODY》、p.171)、再開発の更地の下に既存の町がそのまま残されたマンガ「新しい土地」(panpanya 『おむすびの転がる町』、p.109)、マンモス団地の住民たちが現代の失踪者として登場する文学(柴崎友香『千の扉』、p.251)。かつてはディストピアと結びつけられがちだった風景だが、コロナの時間を通過した執筆者たちは、単純な悲嘆や勇ましい憤りを示したりはしない。異なる時間を行きかい、外側と内側、近景と遠景、相互の視線をかよわせる。「見る人をイメージ世界における閉鎖的な自己充足からひと時解き放ち」(西川、p.189)、「何でもない日常の景色が(一見してわからなくとも)繊細で複雑な要素から成り立っていること」(桑田、p.37)に注視する。桑田のこの記述はマンガ『散歩もの』(久住昌弘原作・谷口ジロー画)の制作手法に向けられたものだが、panpanyaが描く地下の町も同じように濃厚だ。ポスト、カーブミラー、壁を這う配管、ランダムに重なる微細な要素が丹念に描き込まれる。薄い単線の人物像やすっきりした新築マンションの描写とは対照的ながら、両者に優劣はない。「のっぺり」と「傷や穴」の双方を等価に眺めているかのようだ。
各論の締めくくり方はさまざまだが、例えば小林が述べる『千の扉』の主人公、千歳の視線はコロナを経た東京の「その先の風景」のひとつを差し示している。
(千歳は)「「地図に載っているが見ることのできない」異なる時間や他者の視線を通して知ることのできる東京の景色に、新たな回路を開く可能性を見ようとする。それらの回路は、いつも見ようと思えば明瞭に見えるものではなく、浮かんでは消えるように明滅する点線にすぎないかもしれない。しかしながら、千歳はその明滅に関心を向けることによって、刻々と形を変えるような可塑的地図を描き出そうとするのである。」(小林 、p.253) ・・・「今までの社会関係の枠組みでは目に見えない存在を描き出すことで、新たな連帯の方法を模索することが目指されているのである。」(小林、p.254)
各論に添えられている「後記」は、本論の執筆後しばらく経った時期に書かれた。まだコロナの時間は続いていたものの、本論とは若干のズレがある。田口仁による序論にも時期をずらして2回の付記があって、年ごとに前年が「昨日の世界」と思えるほどだと、心理的認識的変化の大きさを記録している(p.18)。高部は、「純粋な表面」の世界にあっても、ある流れのスピードからズレることによって別のリズムを生きる可能性を説く(p.133)。その言葉のとおり、執筆・編集された期間内における微妙なリズムのゆらぎもまた、本書にはズレとして慎重に刻印されていて、3年間の空気感を濃密に追体験できる仕掛けとなっている。
_
注
★1 映画『ALWAYS三丁目の夕日』がヒットしたころの記者コラムにはこのような記述がある。「昭和30年代に物心がついた身としては、そのころの「明」の部分を懐かしく思わないでもないが、「暗」の方はいやである。過去に葬り去ってよかったと、心底思う。その筆頭は、トイレである。」大上朝美 2005年12月16日付 朝日新聞夕刊
_
書誌
編者:桑田光平/田口仁/吉野良祐
出版社:羽鳥書店
出版年月:2023年3月