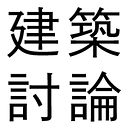二元論の「壁」を越えて:分断の場から創造の場へ
稲垣拓/Beyond the dichotomy over the “Wall” : From a scene of division to a site of creation / Taku Inagaki
国境壁をめぐる二元論
現代は、かつて見ない速度で「壁」が建設され、国境が強化される時代である。欧州の移民危機をきっかけとした国境の閉鎖、イスラエルによるパレスチナ自治区の分離壁、モロッコによる西サハラの砂の壁★1 、少し時代を遡ればベルリンの壁と、枚挙にいとまがない。アメリカとメキシコの国境に壁を建てることを公約に掲げたドナルド・トランプが2016年米大統領選で当選を果たしたことは、国境の強化という方向性を決定づける事件であった。地続きの国境を持たない日本においては実感しづらいが、ケベック大学のエリザベス・バレらの研究★2 によると、1945年以降に世界に建てられた国境壁の総延長は約18,000kmから約41,000kmにも及び、特に2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件以降、急速に長さを延ばしているという。グローバリズムの進展によって一度は効力を弱めてきた境界が、2010年代半ば以降のナショナリズムの復権によって再び強化されつつあるといえるだろう。
主権国家による社会が続く限り、国境はひかれ、国境壁はつねに人やモノの移動を制限する装置としての意義を失うことはないように思える。そして、グローバリズムとナショナリズムの共存状態が続く限り、その構造が生み出す軋轢や矛盾は、国境壁における悲劇的な事件として起こり続けるだろう。社会がこのような構造的矛盾を抱える時代だからこそ、「壁を建てる」対「壁を建てない」、国境を「開く」対「閉じる」、「グローバリズム」対「ナショナリズム」、「善」対「悪」といった二元論的なレトリックを越え、国境壁のあり方を変える柔軟な視点と想像力が求められるのではないだろうか。こういった視点から建築・都市的な視点から国境壁に、ではどのようにアプローチすればよいのか、そのヒントを探っていきたい。
コミュニティから「壁」を考える
トランプが米大統領に就任して以来、アメリカとメキシコの国境を舞台に、さまざまな建築家やアーティストが以前にもまして精力的な活動を展開している。なかでも既に国境に建てられたフェンスや壁を現実として受け入れたうえで、それをコミュニティの交流の場として捉え直したり、空間的、社会的な意味を変えようとしたりする試みが目を引く。
例えば、カリフォルニアをベースとする建築家ロナルド・ラエルは、著書『建築としての国境壁:アメリカとメキシコの国境のためのマニフェスト』(未邦訳)★3 のなかで、詳細なフィールドワークを通して、アメリカとメキシコの国境地帯が持つ多様性の把握とそれぞれのコンテクストにあわせた具体的な提案を交えつつ、国境壁を問い直している。3,000kmにも及ぶ両国の境界がもつ環境的、文化的、物理的な多様性の認識なしに国境壁のあり方を語ることは空想論に陥りがちである、というラエルの指摘は、今日の政治的情勢に対して示唆的である。例えば国境フェンスひとつをとっても、形態や高さでのタイポロジーが13種類もがあるという(なかには軽々と乗り越えられるようなものもある)。国境壁は決して一様ではなく、そのヴァリエーションによって、壁が生む空間的、視覚的体験も異なるのだ。
2019年にラエルは、アメリカのサンランドパーク市とメキシコのシウダー・フアレス市を隔てる国境沿いに、既存フェンスをまたぐシーソーのインスタレーションを実現している。国境警備の介入により、たった30分で打ち切られてしまったものの、このプロジェクトはわずかな時間のなかで、隔たれた二つのコミュニティのための遊びの場をつくり、コミュニケーションを生む装置として国境フェンスを捉え直すことに成功したと言えるだろう。このように異なる文化、言語、民族が近接するという国境壁の状況を逆手に取り、「分断」を「コミュニティ」の場に転換する手法は、国境のあり方をアップデートする上で大きなヒントになるだろう。
観光から「壁」を考える
観光という観点からも国境壁を考えてみたい。観光と聞くと表層的で商業的なイメージを連想する方も多いかもしれない。東浩紀の『ゲンロン0 観光客の哲学』★4 は、このいささか否定的なニュアンスを持つかもしれない「観光客」という言葉を、グローバリズムとナショナリズムの二項対立を超える概念として再解釈を試みた著書である。東は観光客という存在を、グローバリズムとナショナリズムの二重構造を横断的に行き来しながら、偶然性を生み出す主体として扱い、現代の閉塞感に風穴を開ける可能性を見出している。
『ゲンロン0』が出版された2017年は、奇しくもバンクシーがパレスチナ自治区のベツレヘムに「世界一眺めの悪いホテル」といわれる《ウォールド・オフ・ホテル》を開業した年でもある。イスラエルは、パレスチナ自治区を囲い込むように分離壁の建設を続けているが、それが1949年に制定された停戦ラインを超えていることや、またイスラエル人が入植活動を続けていることについて、パレスチナの自治権および民族的自決権を損なうものとして、国際的非難が集まっている。その分離壁に面して建てられたこのホテルは、分断と抑圧の現場にツーリズムとアートを通して光をあてるプロジェクトでもある。ホテルに泊まる観光客は、日常生活と政治的な壁が併置されていることを客室の窓から体感するとともに、ホテルのショップで購入できるスプレー缶とステンシルを使って自ら壁にグラフィティを残すことが出来る。
バンクシーのアプローチが、現地住民の感情を軽視した「悲劇の商業利用」として批判を受けることも当然理解できる。しかし、度重なる国際社会の非難にも関わらず50年以上も続く政治的、宗教的、民族的な抑圧に対し「他者の視点」を通して変革をもたらそうとする試みを、商業主義の一言で一蹴するのはもったいないように思える。エルサレムを含む多くの場所への交通手段を制限され、地理的に隔離されているパレスチナの人々にとって、観光客は世界とのつながりを見出せる数少ない「他者」であることを忘れてはいけない。
東が観光客を、共同体のあいだに「誤配」を生む他者の視点として評価したことと、バンクシーのホテルの開業が時期を同じくしたことは、歴史の偶然ではなく、政治、民族、宗教が生み出す膠着状態に対して時代が要請するムーブメントの現れに思えてならない。
ヴォイドから「壁」を考える
やや時代を遡るが、レム・コールハースがAAスクールに在籍していた1970年代初頭は、「壁」の意味が様々なコンテクストにおいて再考される時代でもあった。ピーター・アリソンによる《ロンドンのための壁》(1971)や、アーキズームによるベルリンに巨大な透明壁を幾重にも配した《ベルリンの並行地区》(1969)といった作品は、壁が再考の対象として注目を浴びていた時代背景をよく表している。
コールハースはAAスクールの調査記録課題のために1971年にベルリンを訪れた際に、二つの発見をしている。ひとつはベルリンの壁が西ベルリンを取り囲むように建てられていることで、その「自由」を確保しているという逆説的な構図であり、もうひとつは、壁があらゆる機能も受け入れる空っぽの容器として「ヴォイド」的都市状況を生み出していたということである。これらの発見は翌年のエリア・ゼンゲリスらとの作品《エクソダス、あるいは建築の自発的囚人》(1972)における、壁によって隔離されたユートピアを創出する、ロンドンを舞台としたストーリーに引き継がれ、その後のコールハースの作品に通底する「ヴォイドの戦略」へと発展していく。
コールハースはベルリンの壁に、その物質性を越えた「ヴォイド」性を見出した。建築的なプログラムから自由であるがゆえに、どんな機能やアクティビティを受け入れることもできるタブラ・ラサ(白紙状態)としての壁は、現代において見失われがちな壁の本質を示しているように思えてならない。
後年コールハースは、ハンス・オブリストによるインタヴューのなかで、冷戦終結とともにベルリンの壁が積極的に取り壊されたことを受けて、次のように述べている。「80年代初頭に、われわれはベルリンの壁の崩壊を予期したコンペティションに参加し、壁の痕跡をすべて消し去らずに、新たに迎える〈壁の死後〉について提案した。(中略)壁に沿ったゾーンは公園として整備し、保存された〈都市の状態〉としてわれわれは提案を行った。結局、壁が崩壊してからその痕跡が跡形もなく真っ先に消されたことに、僕は愕然とした。」★5 コールハースはベルリンの壁の物理的なモニュメント性に価値を見出していたわけではなく、壁が生み出した「ヴォイド」的都市状況こそが、戦後のベルリンを特徴づける価値だと考えていたのだろう。
「壁」を捉える想像力
国境とは、国家の地理的な限界を示すと同時に、異なる文化や、人、モノが行き交う場でもある。ボーダースタディーズの研究者である川久保文紀★6 は、「壁については空間内部を遮断する実態という側面ばかりを強調するのではなく、ヒトやモノのモビリティを効果的にフィルタリングする『透過性(permeability)』をもつ装置として把握しなければ、現代のグローバル化における開放性とセキュリティ強化による閉鎖性の二重ロジックが同時に作用する構図を読み解くことはできない」★7 という。つまり、現代の壁は人やモノの「遮断」と「通過」の両義的な機能を持つものとして理解できる。
これまで見てきた試みは、いずれも壁が持つ機能的な両義性を捉え、そこに新たな価値をあたえることで、膠着した現代の「壁」に対し、ある種の批評性を獲得している。それは、「遮断」と「通過」という壁の機能を超えて、壁自体を創造と活動の場として読み替える視点である。ここで重要なのは、壁を分断の場とするのか創造の場とするのか、その想像力によって、壁をとりまく風景がまったく異なるものになるということである。
政治的な思惑によって壁が際限なく建てられていく状況にある現代においてこそ、壁と対峙し、空間の想像力によって壁に働きかけることが、建築家に問われているのではないだろうか。
註
★1 モロッコによって西サハラ地域を東西に分断するように建てられた軍事境界壁。1980年から1987年までに6つのフェーズを通して建設され、総長2千kmに及ぶ。壁建設の背景には、1976年にスペインが西サハラ地域の領有権を放棄した後に発生した、モロッコと独立を掲げる現地政府との領有権を巡る武力衝突があり、2019年現在も解決の目処は立っていない。川久保文紀「国境の壁とテイコポリティクス」『現代思想 2019年4月号』青土社、2018年、p.114 参照。
★2 E.Vallet and Charles-Philippe David, The (Re) Building of the Wall in International Relations, Journal of Borderlands Studies, Vol.27, №2, 2012, p.112
★3 Ronald Rael, Borderwall as Architecture: A Manifesto for the U.S.-Mexico Boundary, University of California Press, 2017
★4 東浩紀『ゲンロン0 観光客の哲学』(株式会社ゲンロン、2017年)
★5 http://www.artnode.se/artorbit/issue4/i_koolhaas/i_koolhaas.html (2019年8月20日閲覧)
★6 北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター境界研究ユニット共同研究員のひとり。
★7 川久保、前掲書、p.116