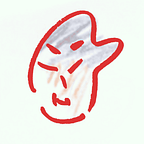お股ニキ著『セイバーメトリクスの落とし穴~マネー・ボールを超える野球論~』
タンパベイ・レイズの筒香嘉智のホームランは、小説家をどれだけ生み出すのか?(評者:渡邉朋也)
プロ野球は社会を映す鏡である。グラウンド上の選手たちがどう思おうが、社会の情勢や大衆の気分が、この国民的プロスポーツには溶け出していく。
日本がバブル経済に沸く1980年代後半、プロ野球パ・リーグでは森祇晶率いる西武ライオンズが席巻していた。現役時代にキャッチャーとして「V9の頭脳」との異名を取った森は、前任者で同じくV9時代のチームメートの広岡達朗が築き上げた「管理野球」をベースに、相手チームのプレイに関する綿密なデータ解析と、きめ細やかなチームマネージメントを導入。1986年の森の就任以降、9年間で8度のリーグ優勝、6度の日本一を成し遂げるほどの常勝軍団へとライオンズを成長させた。
そして、ライオンズがその黄金時代を盤石なものとしつつある1990年、セ・リーグに新監督が誕生した。ヤクルトスワローズの野村克也である。森同様にキャッチャー出身の野村は、スカウトたちが収集したデータに基づいて采配を振るう「ID(=Important Data)野球」を標榜し、野村の就任以前にはBクラスに低迷していたスワローズを、1998年の退任までの9年間で4度のリーグ優勝、3度の日本一を成し遂げ、球界の盟主・読売ジャイアンツと並ぶ強豪へと押し上げた。
同世代でキャッチャー出身かつデータ重視の采配、共通点の多い森監督と野村監督は、マスメディアから貼られたレッテルも共通していた。それはどこか冷たく陰湿なイメージである。森が監督を務めた同時期には、近鉄バファローズやオリックスブルーウェーブで仰木彬が監督を務め「仰木マジック」と呼ばれる奇策を連発し、野村の前には読売ジャイアンツを率いる長嶋茂雄による行き当たりばったりな「勘ピューター」が立ちはだかり、それぞれ一世を風靡した。華やかな「マジック」や「勘」の前に、彼らの野球に対するアプローチは、どこかネガティブなイメージが与えられることになったのだ。
データを重視するこの二人のプロ野球監督が躍進した時期は、奇しくも1995年のいわゆる「インターネット元年」以前の黎明期、具体的には電電公社の主導によりニューメディアブームが起こり、高度情報化社会の到来の足音が日増しに高まる時期と重なる。これから起こるであろう大変動を前に人々が希望を感じ取る一方で、漠とした不安を抱いたり、はたまた時代の潮流に取り残されるであろうものに対する旧懐の情を抱いたりすることは想像に難くはない。いまにして思えば、「データ」を重視する二人の監督に対するネガティブイメージの喧伝は、高度情報化社会を前にした人々の複雑な感情と無縁ではなかったのではないか──。
前置きが長くなってしまったが、本書はアメリカのメジャーリーグ(MLB)も含む今日の野球界を席巻する「セイバーメトリクス」を紹介するものである。
セイバーメトリクスとは統計学的な見地から野球を解析し、プレイを評価する方法論の総称である。例えば、ここ数年で一部の野球場のスコアボードに選手たちの打率や打点などと並んで表示されるようになった「OPS」も、セイバーメトリクスによって生み出された指標である。OPSは長打率と打率を足すことで算出できる指標で、打者の得点能力を表すものだ。打撃に関する指標に限ってみても、選球眼を表す「IsoD」や、長打力を表す「IsoP」、足の速さを表す「Spd」、得点増加貢献度を表す「wOBA」、プレーを取り巻く偶然性の要素の多寡を表す「BABIP」など、さまざまな指標が存在する。セイバーメトリクスの嚆矢は1970年代にまで遡ることができると言われているが、近年のセンシング技術の発達や、コンピューターの処理速度の向上、そして何よりも、MLBのオークランド・アスレチックスが2000年代初頭にいち早く導入して、プレイ、采配、球団経営といった野球を取り巻くあらゆる面で目覚ましい成果を挙げたことから、瞬く間に球界に広まり、現在も進化を続けている。
セイバーメトリクスでどのような成果が挙がるのか。つい先日、日本経済新聞でセイバーメトリクスの観点から送りバントの是非を検討した野球データアナリストの岡田友輔氏の記事が大きな話題になった。
- 実は手堅くない送りバント 「損益分岐点」は打率1割(日本経済新聞/2020年1月14日/執筆:岡田友輔)
送りバントというと堅実なイメージを持つ人も多いだろう。しかし、実際にデータを解析してみると、打者の打率が1割3厘を下回らない限りは、ヒッティングに出た方が得点する確率が高いという。したがって、バッティングの不得手な投手に関してははこの打率を下回ることも多々あるので、送りバントに出るのは理にかなっていると言えるが、例えば送りバントの象徴的な存在である川相昌弘は、生涯打率が2割6分を上回っており、プロ野球選手としては平均的かそれ以上の打力を持つわけだから、むしろヒッティングに出た方がチームの勝利に貢献できたということになる。もちろん、後続の打者がどのような打者なのか、またゲームの状況によって、この基準となる打率は変わってくるので、全ての川相の送りバントが無駄だったわけではない。
このようにセイバーメトリクスの発達と普及により、さまざまな指標が生み出され、さまざまなプレイが多角的に解析されている。その結果、送りバントのようにこれまで漠然と良いことだとされてきたプレイや戦術が、チームの勝利という観点から見たときに、必ずしもそうではないということが明らかになってきた。それと同時に、チームの勝利に貢献しやすいプレイも明らかになってきており、近年MLBで旋風を巻き起こし、日本でも話題になった極端な守備シフトや、ゴロよりもフライを打ち上げることを狙いにいく「フライボール革命」などはその最たる例である。
セイバーメトリクスの影響は、プレイヤーや球団関係者など野球に直接携わる者たちに留まらない。野球ファンの観戦行為にも大きな変化を与えている。選手たちのプレイを解析したデータが、FanGraphs.comなどのウェブサイト上に日々公開され、ファンたちがそれを解析し、選手たちを評価する。こうしたことが一部のファンの間では当たり前のことになってきており、プロ野球選手のトレーニングの方向性や、球団のスカウト活動にも影響を与えているようになっている。本書の著者であるお股ニキ自身も、かつてはそうしたファンのひとりであった。その後、膨大なデータに触れていく中で、野球経験がほとんど無いにもかかわらず、独自の理論や分析体系を構築し、挙げ句の果てには、現役メジャーリーガーで屈指の理論派としても知られるダルビッシュ有に技術的なアドバイスを与えるまでに至った。ダルビッシュが投げる変化球のひとつに「お股ツーシーム」と呼ばれるものがあるが、これはお股ニキのアドバイスによって生み出されたものであるという。このようにデータを媒介にして、プロ野球選手と野球ファンはおろか、野球未経験者とダイレクトに繋がることができる時代が到来しているのだ。
著者はセイバーメトリクスが普及した時代ならではのプロ野球とファンとの新しい関わり方を身をもって体現している第一人者のひとりだと言えるだろう。では、本書がセイバーメトリクスの詳細な解説書、あるいは入門書なのかというと、実は必ずしもそういうわけではない。もちろん、セイバーメトリクスについての概説が記されているし、バッティング/ピッチング/キャッチング/球団経営といったプロ野球を取り巻く各分野における潮流もセイバーメトリクスの観点からコンパクトに整理されており、今後のプロ野球観戦をより楽しむためのヒントが十分に得られるだろう。取り上げられたいくつかの潮流の中には先述の送りバントの是非にまつわるものも含まれているから、他のプロ野球ファンとの会話の話題にも事欠かない。しかし、セイバーメトリクスと具体的な戦術の関係性をより深く掘り下げたいのであれば、他にも適書はあるし、英語の文献にはなるがFanGraphs.comのブログで膨大な記事が無料で閲覧できる。
本書の特異性はタイトルにもある通り「セイバーメトリクスの落とし穴」を、それぞれの分野から示唆し続ける点にある。
著者は野球を「相反する要素の両立が多くの場面で必要とされる」スポーツであると定義している。試合中の事象を例にとると、フォアボールを選ぼうとしてボールを見過ぎた結果、三振になったり、三振を恐れてボールにバットを当てに行った結果、守備につく野手が前に出て却ってヒットゾーンが狭くなったり、というプレイがそれに当たる。落合博満のようなホームランを打つと決めたらホームランを確実に打つことができる超人的プレイヤーであれば、そうした相反する要素を振り切るようなプレイが可能かもしれないが、実際にそんな選手は落合以外に存在しない。
野球とはヒットやホームランの数を競うスポーツでもなければ、フォームの美しさを競うスポーツでもない。相手チームに勝てば良いのだ。またシーズンを通して言えば、全ての試合で勝つ必要もなく、とにかく優勝すれば良いのだ。セイバーメトリクスとは、野球というスポーツを局面ごとに抽象化して、それぞれに対して可能な範囲で最適な解を導き出す方法論、つまりはプレイごとや試合ごとの「大局観」を客観的に記述するための方法論だと言い換えることができる。著者は野球のルール上の特性を踏まえたうえで、相反する要素の両者のバランスを臨機応変に取っていくことの重要性を説き、そのためのガイドとしてセイバーメトリクスを捉えている。
しかしながら、現実は著者の訴えとは逆の方向に野球界、特にMLBは舵を切りつつあるようだ。野球にまつわるあらゆるデータの収集はますます加速し、軍事技術を転用して構築された「スタットキャスト」と呼ばれるデータ解析システムがいまやMLBの全球場に設置されている。そこで得られた、ピッチャーの投球の回転数や回転角度、またバッターが放った打球の角度や速度と言ったデータは、MLBのテレビ中継でも派手な視覚効果とともに表示されているので、見たことのあるひとも多いだろう。球場からの中継映像と打率や打点などの基本的な成績表示を組み合わせた従来のテレビ中継に比べると、こうしたデータは直感的に選手のプレーの質や個性に対する定量的な評価に繋げることができるため、一介の野球ファンとしては新たな楽しみとして歓迎する向きもあるのだが、本書では単純には喜べない異様な傾向を浮き彫りにする。
それはプレーが「ホームランか三振か」という極端な状況が生み出される傾向である。データの解析が進んだ結果、極端な守備シフトが流行した。日本でも古くは王貞治対策の「王シフト」、また近年も内野に野手を5人置く守備シフトがたびたび敷かれ、話題になっていたが、2010年代に入ってからMLBではそうした守備シフトを平均的な打者に対しても展開し、成果を挙げている。そして、そうした守備シフトを無化するべく近年流行しているのがゴロよりもフライを打ち上げることを狙いにいく「フライボール革命」である。フライを上げた方が得点につながる可能性、ひいてはチームが勝利する可能性が高いことが判明すると、こぞってこのアプローチを取り入れた。結果、MLBでは2016年ごろからホームランが目に見えて増加し始めている。本書刊行後の2019年シーズンは史上最多の6776本のホームランが飛び出した。
むろん、ピッチャーもこの状況を手をこまねいて見ているわけではない。フライボールを狙う打者に対しては空振三振が有効なのは明らかである。よって、それを確実に狙いにいくために、多くのMLBのピッチャーが「ピッチトンネル」と呼ばれれる直球と変化球の軌道の差をなるだけ埋めていく投球術の習得に励んでおり、そのために「スラッター」と呼ばれるスライダーとカットボールの中間の変化球が流行しつつあるという。もともと三振は、トレーニングの現代化によるピッチャーの平均球速の向上によって増加傾向にあったが、さらに増加し、こちらも2019年は史上最多の42,823個の三振が生まれた。こうして現在のMLBは、本書の刊行後も「ホームランか三振か」という状況をさらに加速させている。
- MLB finishes year with 6,776 homers, 42,823 strikeouts(News Tribune/2019年9月30日)
こうした傾向は大味な試合展開を生み出し、選手の個性もある方向に収束し、やがてチームカラーも埋没させる。一部のファンたちからはすでに不満の声も挙がっているという。著者はこれをセイバーメトリクスの過度な導入による、野球における「正解のコモディティ化」として捉えており、それこそが「落とし穴」だと指摘する。「正解のコモディティ化」とはマーケティング用語のひとつだが、まさにこの背景には、オーナー企業やファンといったステークホルダーの存在が巨大化し、MLBやそれを取り巻く文化そのものが過度に商品化されつつある現状がある。少ない投資で、チームを強化し、より高い価値を生み出す。そのためのマーケティング手段として、セイバーメトリクスが用いられているのだ。
本稿の途中で評者は、本書を「『セイバーメトリクス』を紹介するものだ」と記した。しかし、正しくはバッティング/ピッチング/キャッチング/球団経営において、どのようにセイバーメトリクスが活用されているかを紹介するとともに、それがどのようにして野球における「正解のコモディティ化」を進めているかを紹介するものである。言い換えるとそれは、野球というスポーツをテクノロジーによって抽象化し、分節し、解析する過程で、野球からどのような楽しみが奪われているのかを思索させるものであるとも言える。
野球は商品である以前に、スポーツであり、遊びである。目の前に相手がいれば理由も無く勝ちたいと思うし、思いついてしまった変化球や打法はそれが意味があっても無くてもとりあえず試したい。そこに正解は無い。そうした自由意志に基づくごく普遍的な行為が、トッププロでは以前にもまして成立しづらくなっているように感じる。本書が刊行されて間も無い2019年3月にイチローが現役を引退したが、その引退会見の席上、「現在の野球は、頭を使わなくてもできてしまうものになりつつある」と発言した。この発言の裏には、こうした現状への危機感があったのだろう。
現代は野球のようなスポーツであっても、大規模な経済活動の中に位置付けられれば、ビッグデータ解析を通じたコモディティ化の波からは逃れることができない時代だ。アートやデザインなどのクリエイターと呼ばれる人びとが関わる領域も無縁ではないだろう。実際、経済活動と比較的密接な位置付けにある広告デザイン、とくにユーザーの行動を解析しやすいウェブデザインの現場においては、「A/Bテスト」と呼ばれる大規模なユーザーテストを繰り返し試行することで、よりコンバージョンが高まるデザインを模索する手法が一般化し、大規模なECサイトなどではデザインのコモディティ化が進んでいる。またバナー広告や短時間の動画広告なども同様の傾向が強まっている。これからこうした傾向は広告のみならず、多くの領域に飛び火していき、やがてはストリーミング再生されやすい音楽の作り方や、オークションで高額で落札されやすい絵画作品の作り方なども確立されていくのかもしれない。私たちはこうしたコモディティ化の波の前で漫然とした不満を抱えながら、消費を続けていけばいいのだろうか?
ところで小説家の村上春樹は、デビュー前の1978年4月1日に神宮球場で開催された広島東洋カープ対ヤクルトスワローズ戦において、スワローズの内野手デーブ・ヒルトンが安打を放ち、二塁へと到達するのを目の当たりにした瞬間に「そうだ、小説を書いてみよう」と思い立ったという(村上春樹『走ることについて語るときに僕の語ること』2010年)。そうして出来上がったのが村上のデビュー作となる『風の歌を聴け』(1979年)であり、その後の活躍は周知の通りである。
プロ野球は社会を映す鏡である。グラウンド上の選手たちがどう思おうが、社会の情勢や大衆の気分が、この国民的プロスポーツには溶け出していく。だから、それを観るひとに突如として小説の執筆を思い立たせることなど造作のないことである。しかし、いまだに私たちは筒香嘉智のホームランが未来の小説家をどれだけ生み出すのかを知る術を持たない。
これからさらにテクノロジーが進歩していく。それに伴い野球を取り巻くあらゆる事象の解析もますます精緻なものとなり、そこから得られる知見の幅も格段に広がるはずだ。正解のコモディティ化の壁を突き破って、いつの日か、グラウンド上の選手のひとつのプレイが、観戦するひとたちを小説家や、大工、警察官に変貌させてしまう可能性をそれぞれ弾き出せるようになる時が来たりはしないだろうか。そうなれば勝ち以外の価値で野球を測ることができるだろうに。
_
書誌
著者:お股ニキ
書名:セイバーメトリクスの落とし穴~マネー・ボールを超える野球論~
出版社:光文社
出版年月:2019年3月