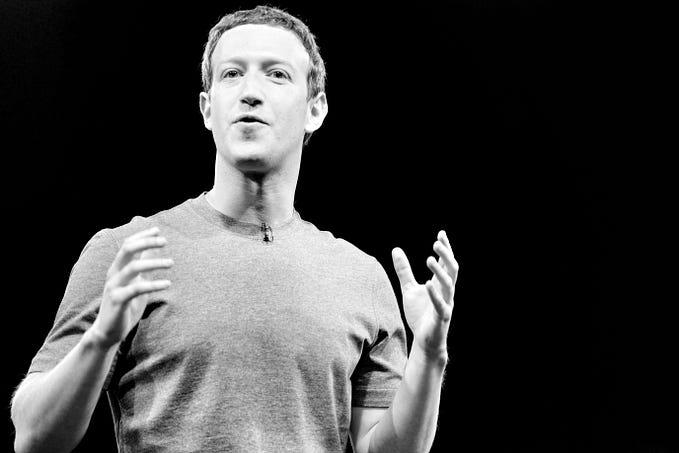報告|建築模型の歴史性と多義性
052|202102|特集:Model(ing)のゆくえ — 融解するフィジカルとデジタル
著者:建築と模型[若手奨励]特別研究委員会[嶋﨑 礼(委員長)、松井健太、 小見山陽介、安岡義文、 松本直之 、福島佳浩、天内大樹、岡北一孝、古賀顕士、岩田千穂、米村美紀、萩原まどか]

1. 建築と模型[若手奨励]特別研究委員会について
CGやコンピューターシミュレーションの発達した今日、模型は不要との声も聞かれる一方で、設計に加え構造実験、環境評価、教育、保存などの多様な分野で今なお模型が活用されている。歴史的に見ても、模型は必ずしも「スタディ模型」や「プレゼン模型」といった設計の副産物にとどまっていたわけではなく、多義的な広がりを持っていた。
本研究委員会は、各専門分野における模型についてのまとまった知見を得、議論を深めることを目的として設置された。建築史から環境や構造、教育、設計に至るまで様々な分野に携わる総勢12名の委員からなる本委員会は、現在までに3回のオンライン研究会を開催し、単なる設計の副産物に限られない模型の多義性が早くも見え始めている。
なお、本研究委員会とは別に、東大建築加藤耕一研究室で「もけけん」(模型研究会)を開催しているが、もけけんでは模型の事例集めや用語整理、マインドマップの作成などを行い、テーマを掘り下げるというよりは拡散させる方向性で活動している。(嶋﨑)
2. 西洋建築模型略史
西洋建築における模型の歴史は古代エジプトまで遡ることができる(註1)。以下ではその大まかな流れを簡単に確認する(註2)。
古代エジプトでは、理想の形を可視化・複製するための実寸模型や、縮尺を設定することなくグリッドを用いて任意の規模の作品を作るための模型が作られていた(註3)。また古代ギリシアにも模型を意味する「パラデイグマπαραδειγμα」(建物全体の模型)や「トゥポスτύπος」(装飾細部の蝋模型)といった用語が存在している。一方でウィトルーウィウスは、城壁模型を用いたカッリアスのプレゼンとその後の逸話に言及しつつ、「いかにも本当らしく見える」模型に過度に信頼することを牽制している(註4)。
中世時代の教会模型の多くは、施主へのプレゼンや施主あるいは神の力の誇示のためのものである。また中世建築家たちは、後に「マイクロ・アーキテクチャー」の語で呼ばれるようになる、教会を模した形態の説教壇や聖遺物容れなども作っていた(註5)。
ルネサンスが到来すると、模型は建築デザインそのものに大きく寄与するようになる。ルネサンス建築模型としては、フィリッポ・ブルネレスキによるフィレンツェのサンタ・マリア・デル・フィオーレ聖堂のクーポラ模型(制作は大工のバルトロメオ)がよく知られているが、金細工師出身のブルネレスキにとって模型は単なるプレゼン・ツールにとどまらず、デザイン構想のためのより実践的な役割を持っていた。そうしたスタディ模型の利用が定着していく中で、アルベルティは、「模型は精巧に仕上げ磨き光らせる必要はなく、飾らず簡明なもの」でよいと述べ、スタディ模型のシンプルさを強調することになる(註6)。16世紀になると建築家の実践的な模型利用は一層進み、ミケランジェロなどは図面よりも粘土製模型を使った彫刻的アプローチを好んだ。
17世紀には、ロンドン王立協会が設立されたイギリスで、建築模型が研究や記録のために活用された。その背景には、模型によって技術的問題の発見・解決を試みるという当時の科学的アプローチの方法論があった。現存する最古のイギリス模型はクリストファー・レンによるペンブローク・コレージ礼拝堂(1663)である。18世紀にはエティエンヌ・ルイ・ブレやクロード・ニコラ・ルドゥーといったいわゆる「幻視の建築家たち」の魅力的な二次元表現の台頭によって模型の重要性は低下していったが、イギリスではなおジョン・ソーンのように建築模型への熱を抱き続ける者もいた。
19世紀末にはアントニオ・ガウディのように構造模型を積極的に用いる事例もあったが、続く20世紀モダニストたちはプレゼンテーションという伝統的な模型利用へ立ち戻ることになる。ル・コルビュジエのヴォアザン計画やフランク・ロイド・ライトのブロードエーカー・シティの模型は、写真撮影や展示のためにわざわざ作られたものである。
しかし20世紀後半になると、建物の表象から改めて設計プロセスにおける積極的な要素としての模型の役割を掘下げようとする試みがポストモダニストたちによって提供される。1976年にニューヨークで催された展示Idea as Modelが問うたのは、建築という領域そのものの存立に関わるような模型の意味である(註7)。こうした思考の中に、「アクソメ模型」として知られるピーター・アイゼンマンのHouse Xの模型(1978)なども位置づけられる。
近年ますます関心の高まっている建築模型だが、その最初の通史的研究はマーティン・S・ブリッグスに求められる(註8)。一方で時代・テーマ毎により詳細な研究が進むのは20世紀後半以降であり、とりわけ近年ではザビーネ・フロンメルを中心とする中世・ルネサンス研究やマシュー・マインドラップによる現代に近い時代の研究などが注目される(註9)。(松井)
※本節の註は文末に記載
3. 浮かび上がる建築模型への問い
・模型とは?
異なる分野の専門家が集まる中、模型とはそもそも何なのかがまず問題となった。「異なる背景と問題意識、方法論を持つ研究者の共通言語を模索していく」(安岡)ことにより模型の定義や模型であることの条件、「模型性」(岡北)を考えていくべきとの声が聞かれた。
第2回研究会の構造模型についての議論の中で指摘されたのは、人間の理解との結びつきの重要性である。「一人の人間では手に負えない膨大な情報量を有する対象を、特定の観点からデータ圧縮することで扱えるようにするということが、模型にとって決定的に重要ではないか」(福島)。したがって、「機械学習での自動計算は、人間が理解できるかわからない。機械学習でできたモデルは模型という捉え方はされないのだろう」(米村)。情報の圧縮(縮減)であれ増幅であれ、「建築が出来上がった時のある側面を操作して模型にしていく」(岡北)という特徴が、構造模型に限らず模型一般に認められるのではないか。つまり模型性の議論においては、「どの観点からそれを見るか」を置き去りにして議論はできない。同じ物体が、ある人にとっては模型であると同時に、別の人にとっては模型でないということもあり得る」(福島)のであり、人間の視点が不可欠と思われる。第3回研究会での音響模型に関する発表でも、模型を用いた可聴化によって音響の主観的な評価が可能になるとの報告があった。
模型の「模す」という特徴も重要だと思われる。聖遺物箱のようなマイクロ・アーキテクチャーに見られるように「部分の引用と全体の引用があって色々と分類、議論できる。建築の中の彫刻でいうとアーチの連続体が多用されているように思われ、部分を見ただけを見ただけでも「教会だ」と感じられて、効果があったと思われる」(岩田)。「模型についての思考の最も一般的な出発点は、模すものと模されるものという二項関係に設定できるだろう。その最も基本的なかたちが、建物(建設されたもの)とスタディ模型の関係である。一方で日本語の「模型」には、モデルとしての前者を検討・表象するもの(模すもの)と、それ自体がモデルとなるもの(模されるもの)という双方の意味が包含されている。これはつまり、模すものと模されるものの関係が(容易に)反転する可能性を示唆しているのではないだろうか」(松井)。
・模型の多義性
「聖遺物箱は「箱」という機能があるが、聖なるものを入れるものとしてイメージの関連性からモチーフを使っている。概念の引用であって、ミニチュアを作っている感覚ではないのでは」(安岡)と、建築の実作品と対応していないマイクロ・アーキテクチャーの模型性に疑問が投げかけられた一方で、「建築を伝えるメディアという広い意味で考えれば模型とマイクロ・アーキテクチャーが一つの領域に納められる」(岡北)、「それが建築物と呼べるのか(彫刻ではないか)という問題を提起する一方で、建築模型が建築と他のディシプリンの対話・交流ツールとしての役割を果たすこと、異なるディシプリンの狭間で立ち上がることを示唆している」(松井)と模型の多義性に期待する声も聞かれた。なお、環境工学の実践においては「光、音、空気の間で転用ができたり意匠検討もできたりする」(米村)、多用途の模型もある。
・模型の未来
模型が計算機シミュレーションによって置換されていくのかどうかが気になるところだが、「光や音の伝播のように実建物で繰り返し実測できる対象については模型からシミュレーションへの置換がしやすいが、破壊現象のように発生頻度が低かったり不可逆的な変化を伴ったりする対象については、模型とシミュレーションの併用がいつまでも残るように思う。模型からシミュレーションへの置換のしやすさは分野によってかなり差があると考えられる」(福島)、「シミュレーションと模型のカバーしうる領域が、重なりつつも棲み分けられている」(米村)と、検討対象によっては模型も重要なツールであることが指摘された。
「現在では建築設計教育に模型が当たり前のように取り入れられているが、これは比較的新しいことのようである。フランス・アカデミー(ローマ支部を含む)も多くの建築模型を所蔵していたとのことだが、たいていはそれを観察・模写するものであり、設計プロセスのなかで活用されるスタディ模型ではなかった。一方でフランス・アカデミー以降の理論/実践教育(講義/アトリエ)の分担のなかで、理論と模型はどのような関係にあったのだろうか。そしてそれはバウハウス造形教育の中でどう変化したのだろうか」(松井)。建築教育における模型の役割については、今後の議論が待たれる。
4. 報告
委員が各自の専門に照らして模型の実例や利用法、将来の活用法等について研究発表を行っている。歴史研究と現代実践分野の専門家が同じ場所で議論することにより、模型に関するイメージを拡張するとともに、模型の意義や今後の可能性について討議してきた。以下に、各委員からの発表の論旨を紹介する。
古代エジプト文明の模型と関連するものについて|安岡 義文
古代エジプト人の模型に対するまなざしは、末期王朝時代の始まり(紀元前7世紀頃)を境として大きく変わる。古王国時代から第三中間期(紀元前2600~紀元前7世紀頃)までの模型は、葬祭建築の副葬品としての家屋模型、記念碑建築のプロジェクトに用いられたと考えられるスタディ模型、あるいは奉納物としてのプレゼン模型などが主であった。これに対して、末期王朝時代以降は、建築のディテールやプロポーションを吟味する目的で作られたと考えられる模型が支配的になる。エジプト人にとっての建築とは、絵画・彫刻作品を内包したアンサンブルであったため、彫像模型も同時代を境に多数出現するようになる。この末期王朝時代に起きたエジプト美術史上の変革は、同時代のアルカイック期ギリシア美術に大きな影響を与え、その後のギリシア・ローマ文明及び西洋文明全体にシュムメトリアの技法として継承されている。
今後は、末期王朝時代以前の絵画・彫刻・建築を対象に、建築模型が当時の社会の建築観をどのように反映しているかについて分析していきたい。
古代ギリシアの模型、あるいは模型のようなもの|岩田 千穂
クールトンによれば、古代ギリシアの建築設計・施工は、紀元前5〜4世紀ごろには、仕様書(syngraphai)に加え、必要に応じて建築家がパラディグマ(paradeigma)やアナグラフェウス(anagrapheus)を用意して行われたと考えられている。 パラディグマはしばしば「模型」と表現されるが、建設現場の職人達から見ると、「模範」や「手本」であり、目指すべき完成形であったと言えよう。アナグラフェウスはおそらく「型板」を指しており、例えばアッソス、アテネ、メッセネで標準瓦型が出土している。建設現場で製作した瓦を型に当てて検査が行われたと考えられている。
このほか、中世以降に比べると現存資料は少ないながら、建築の粘土模型や建築を模した形態の墓、彫刻に見られる建築など、建築的要素が使用される古代ギリシアの遺物・遺構を幅広く紹介し、それらの模型性について考えたい。各々がどのような目的で建築の-全体にしろ部分にしろ-どの側面を引用し、誰のために作られたのかに注目したい。
また、ギリシア建築はその発展の過程でエジプトや近東からの影響を受けており、ことエジプトからは石造建築技術を取り入れたとされている。安岡先生にご紹介いただいたエジプトの模型との関連性も考えてみたい。
【参考文献】
J.J.クールトン, 『古代ギリシアの建築家―設計と構造の技術―』, 伊藤重剛訳, 中央公論美術出版, 1991
ゴシック期のフランス・ドイツで作られた模型や模型らしきもの|嶋﨑 礼
フランスやドイツ周辺の地域では、プレゼンやスタディといった現代的な意味で建築模型と呼べるもののゴシック期の残存例は少なく、使用は限定的だったと思われる。一方で、建築の全体や一部分を模した形状を採用している聖遺物箱、実用品、彫刻等、いわゆる「マイクロ・アーキテクチャー」は多数制作された。
マイクロ・アーキテクチャーの意義としては、①ミニチュア建築が建築の形状を引用している理由を探ることにより、当時の建築の認識のされ方を検討することができる、②容易に移動できるマイクロ・アーキテクチャーの流通が、異なる分野のアトリエ間(建築、彫刻、金銀細工、ステンドグラス…)の対話やゴシックの形態の伝播に寄与した可能性が考えられる(形状の簡略化、抽出等による把握の容易化によるメディアとしての役割)。
このように、マイクロ・アーキテクチャーはそれ自体独立した作品であり特定の建築と結びついたものではないが、模型としてみることで模型の概念を拡張し、今後の議論につなげたい。
初期近代西欧の模型を考えるためのいくつかのキーワード|岡北 一孝
15・16世紀イタリアの建築模型から、差し当たり5つのキーワード(彫刻、実験、コレクション、コンセプト、プレゼンテーション)を抽出した。アルベルティ『建築論』の模型論がいまでもしばしば取り上げられるように、この時代の模型の実情やそれをめぐる議論は、いまの状況の源流ともいえるだろう。
ルネサンスの模型はそれらの5つの側面をあわせ持って成立しているが、その中でもとくに注目したいのは模型の「彫刻」性と「実験」性である。例えば、彫刻性が強い模型は、本研究会の一つのキーワードでもある「マイクロ・アーキテクチャー」の一種ともいえる。さらに、マイクロ・アーキテクチャーと建築模型を包括的にとらえて分析すれば、ルネサンス建築史を彫刻的側面から描き直すことが可能になるのではないだろうか。ルネサンスでは画家が建築家としても活躍することが多かったが、彫刻家が建築家へとキャリアを展開することもあった。この彫刻と建築の結びつきを、建築模型は媒介するのではないか。また一方で、ブラマンテが計画したサン・ピエトロ聖堂の交差部のスケールダウンとも言えるのがラファエッロによるキージ礼拝堂である。つまりそれは建築でありながらも縮小模型であるともいえる。建てられるべきもの構造や意匠を実験するするとき、オリジナルのスケールに近いものを扱ったほうがより精緻に確かめることができる。つまり、模型においてその実験性を強めていけば、それは自ずと建築へと近づいていく。
今後は17世紀、18世紀まで扱う時代を広げて模型を追いかけていきたい。キーワードの一つにあげた「コレクション」については、ルネサンスでは実例が少ないため多くを語れないが、その後の歴史的展開を踏まえると模型の重要な側面といえる。また、とりわけ18世紀以降になると建築模型が建築教育の中で重要な位置を占めるようになる。
海を渡った祭壇イメージとそのモデルを探る旅|古賀 顕士
2018年に世界遺産登録された「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」に見られる教会堂建築群は「日本」と「西欧」の建築・文化的要素が混交したユニークな建物が多い。それらの中には一見して伝統的日本建築ともみてとれる外観の建物もあるが、宗教的家具や建具を配し「祈りの場」として宗教的空間構成をもつ点でやはり教会堂の体をなす。現存する日本最古の教会堂建築である大浦天主堂はその改築の折、様式がゴシックに統一された。日本人大工棟梁溝口市蔵が改築を担当し、大祭壇もまた彼の手によるものである。同時期にフランス本土で制作された主祭壇に引けを取らない逸品を溝口は如何にして制作しえたのだろうか。この大祭壇の「模型」が溝口家の家宝として伝えられていたという。この他、大浦天主堂の大祭壇と似たゴシックの形態をもつ祭壇が長崎に点在する教会堂群に数多く据えられている点にも注目し、祭壇そのものが「模型」として形態の「模倣」に寄与した可能性を探っていきたい。

【参考文献】
・桐敷真次郎,『大浦天主堂』,中央公論出版,1968
・『三沢博昭写真集 大いなる遺産長崎の教会』,川上秀人解説,智書房,2000
・「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」構成遺産候補建造物調査報告書,2011
・Jean-Michel Leniaud, Les cathédrales au XIXe siècle,ECONOMICA,Paris,1993
模型と都市プロジェクト|松井 健太
模型の実践的機能のひとつにその還元性が挙げられる。アルベルテイが強調するスタディ模型の簡素性や本研究会で福島佳浩さんが指摘した構造模型の「縮減」の機能が示すように、模型は、対応する設計物の特定の側面を捨象することで、その他の側面の自由なシミュレーションを可能にする。これまでのところ本研究会の模型の議論は建築物単体にとどまっているが、以上の模型の還元性は都市の次元へと拡張することもできよう。都市プロジェクト(ここでは都市スケールの建造物から都市計画まで幅広く考えている)の構想においては、建物と都市の関係を把握するために、個々の建物の特性をある程度まで度外視しなければならない。この点において模型の還元的機能が大きな寄与となり得る。とりわけ1920年代のプラスティシン(図2)や1950年代以降のスタイロフォーム(図3)といった可塑的自由度の高い模型材料の普及は、時々の革新的な都市プロジェクトを生み出す要因のひとつであったと目される。

構造模型と構造工学|福島 佳浩
構造模型の特徴として①力学的相似性、②縮減、③物理的表現の3つに着目する。②縮減は、縮小化・部分化・省略化など、元の対象よりも情報量を減らす操作であり、①力学的相似性を保ったままデータ圧縮するプロセスとして構造模型を位置付けることができる。モデルへとデータ圧縮することで対象の把握が容易になる一方で、削減した情報の影響により対象とモデルの挙動に未知の齟齬が生じる可能性は常に残る。③物理的表現に期待されるのは、この未知の齟齬を予防する役割であり、幾何学的な相似性を保つことが最も有力な手段となる。以上を踏まえ、「構造模型=対象の力学的かつ幾何学的に相似な縮減」という定義を提案する(翻って考えるに、構造工学とは力学的相似性とは何かを扱う分野である)。構造試験体(縮減が少ない)、構造解析モデル(幾何学的に相似でない)、意匠模型(力学的な観点とは別の相似性を有する)などの模型性についても考察することで、縮減 Reduction と相似性 Similarity を軸にした模型論を展開したい。
音響工学と縮尺模型実験|米村 美紀
縮尺模型を用いた音響測定は、1960年代より音楽ホールの設計に用いられるようになり、日本では特に1980~90年代に竣工された多くの音楽ホールで、1/10ほどの縮尺模型を用いた検討が行われた。音を含む環境工学で用いられる模型の特徴は、構造模型のように模型の構造体そのものではなく、それが囲む空間をどのように計測するかに重点が置かれることである。音響分野では、縮尺に比例して計測対象となる音の周波数が高周波側にシフトするが、高周波数帯域における空気減衰(酸素分子・水分子によるもの)の影響を減じるために、模型内の空気を窒素で置換するという方法がとられることもある。近年は、音場予測のための理論計算(数値シミュレーション)の手法が盛んに研究されており、その検証のために模型実験が行われる事例が多い。複雑な形状をもつ空間や大空間の音場予測は計算量負荷が大きいため、模型実験を併用した研究が行われており、模型実験と理論計算が相補的な関係をもって音場予測に関する研究を支えているといえる。一方、模型実験には高コストであること、高周波数帯域の計測精度向上といった課題がある。今後は様々な研究事例を横断的に調査し、模型実験の適用可能性について考察を深めたい。

出典:T. Oshima, et al., Three-dimensional urban acoustic simulations and scale-model measurements over real-life topography, J. Acoust. Soc. Am. 135 (2014) EL324–EL330.
近代建築模型の構法・材料|松本 直之
日本の建築模型の材料・構法を大胆に概観すると,近世以前の木や紙に加えて,明治以降には石膏を扱う技術が応用されるようになり,1960年代以降には徐々にスチレンボードやアクリルなど広義のプラスチック・樹脂の使用が一般的になったと整理することができるだろう。現代につながる近代の模型技法として,左官彫刻や石膏彫塑に由来する石膏模型および,初等中等教育に用いられていた紙製・木製模型に着目して調査を進めている。
例えば前者の石膏模型は,その系譜を辿ってゆくと,近世以前の左官彫刻と近代の彫塑・美術教育の流れを汲んでおり,他方で戦後の専門模型業者の登場を準備したという点で,建築模型史において重要な位置を占めていることが分かる。戦前には,左官彫刻の流れをくむ技術者や彫刻教育を受けた美術家によって,様式建築を飾る石膏彫刻が盛んに作られており,石膏模型も類似する技法で製作されていたと推測されるが,戦前の専業の石膏模型製作者やその技法については未詳な点が多い。しかし戦後,1950年代には,モダニストの建築家が石膏模型を積極的に使い始めたこともあり,石膏を含む建築模型技法が注目を集め,雑誌記事や書籍の刊行が相次いでいる。この時期に活躍を始めた模型専門業者には,戦後の様式建築の退潮に伴って模型製造に携わるようになった建築石膏装飾業者が複数含まれていたことが明らかになっており,戦前の左官業,建築装飾業の職能の変化としても興味深い。その後,新たな材料の導入や建築家の需要への対応を通じて,建築模型業者は戦前とは異なる様相を示すこととなる。
石膏模型とその後のプラスチック系模型の構法的関連,戦前戦後の木・紙材料を用いた模型の構法の変化など,技法的な関連とその背景を系譜的にたどることで,戦前と戦後の建築模型を連続的に論じる視点を確立したいと考えている。
建築模型とコレクション| 天内 大樹
・模型独自の論理と魅力
大井川鐵道には「きかんしゃトーマス」のイベント列車がある。子ども達が抱くきかんしゃの心像に、実寸の感覚はないはずだ。彼らは千頭駅できかんしゃと写真を撮り、実物を動かさずに新金谷駅に戻る。駅脇の建物では「大きいけど動かない」実物の機関車より、玩具に集まる。
・収集対象
春日武彦『奇妙な情熱にかられて』はミニ酒瓶のコレクションを取り上げるが、建築模型も収集可能らしい(建築倉庫)。模型村(東武ワールドスクウェア)は、移動困難な建物を圧縮して収集し、意外な組合せを見せる。画家らのスクラップ帳で、本来の文脈から断たれた図像群が、想像と創造を喚起するのに似る。
・記録媒体
設計中の建築は酒瓶より頻繁に変貌する。微妙な曲面や空間の実証にせよ、手戻りの回避にせよ、模型は交渉時の原案として、また一設計プロジェクトの系内で構想の具現と保存として用いられる。修繕や解体の際に原状を再現する建築模型を想起すると、野外博物館(明治村)は実寸大の模型村であり、同時に建物や敷地の変更履歴でもある。
(未発表内容のメモ)
5. 展望&展開
今後は、隔月での研究会の継続、シンポジウムの開催(詳細は検討中)、2022年度日本建築学会大会でのパネルディスカッションの開催、各研究発表に基づく報告書の作成、データベースや模型の作成(検討中)などに取り組んでいく。
註(2 西洋建築模型略史 )
註1)日本建築模型史に関しては次のものが参照できる。藤村泉, 「建築模型の歴史」, 『文化財』, no. 226, 1982, pp. 12–19; 今村創平, 「日本建築模型小史」, 『JA』, no. 91, 2013, pp. 24–27; 山崎幹泰, 「古建築模型の製作と展示」, 『日本のたてもの―自然素材を活かす伝統の技と知恵』所収, 青幻舎, 2020, pp. 134–35.
註2)以下の記述は次の優れた通史的記述に多くを負っている。Martin S. Briggs, ‘Architectural Models-I’, in The Burlington Magazine for Connoisseurs, vol. 54. №313, 1929, pp. 174–83; ‘Architectural Models-II’, vol. 54. №314, 1929, pp. 245–52; Michael Ostwald, ‘Shifting Dimensions. The Architectural Model in History’, in Homo Faber. Modelling Architecture, Mark Burry, Michael Ostwald, Peter Downton, and Andrea Mina (eds.), Sydney: Archadia Press, 2007, pp. 142–57.
註3)古代エジプト模型の記述については安岡義文氏よりご教授いただいた。
註4)ウィトルーウィウス, 『ウィトルーウィウス建築書』, 森田慶一訳. 東海大学出版会, 1979, pp. 303–4.
註5)「マイクロ・アーキテクチャー」については次を参照。Bucher, François. ‘Micro-Architecture as the “Idea” of Gothic Theory and Style’, in Gesta, vol. 5. №1/2, 1976, pp. 71–89; Bucher 1976; Guillouët, Jean-Marie, and Ambre Vilain (eds.), Microarchitectures médiévales . L’échelle à l’épreuve de la matière, Paris: Picard, 2018.
註6)レオン・バティスタ・アルベルティ, 『建築論』, 相川浩訳. 中央公論美術出版, 1982, p.38.
註7)Richard Pommer and Christian Hubert (eds.), Idea as Model, New York: Rizzoli, 1982.
註8)註2を参照。
註9)Sabine Frommel and Raphaël Tassin (eds.), Les maquettes d’architecture: fonction et évolution d’un instrument de conception et de réalisation, Roma: Picard, 2015; Matthew Mindrup, The Architectural Model: Histories of the Miniature and the Prototype, the Exemplar and the Muse, Cambridge-Massachusetts-London: MIT Press, 2019.
※なお研究委員会は現在も継続中であり、今回はこれまでの成果を中間報告としてまとめていただいた(編)