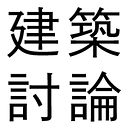批評|立体長屋ローヂの問い
055 | 202105 | 特集:建築批評《コンテナ町家》 /Review : Questions from the multi-story Nagaya Roji
不思議な立体路地
コンテナ町家を訪れたときの不思議な感覚を覚えている。平入りの屋根に木格子を付けた立面がやさしく出迎えてくれるものの、よく見ると軒は随分高いところにあるし、隣のマンション側壁に晒された通路を行けば、大きな鉄骨フレームに覆われた古い木造長屋が静かに現れ、最奥の祠を横目に鉄骨階段を登れば、小さな通路を確保したコンテナ群が並び、さらに階段を上がれば、大らかな屋根に切り取られた街区内外の長屋やビル群への眺望が開ける。もちろん誌面を通して計画の概要は知っている。目にするひとつひとつの要素も知っている。ただ、コンテナ群の合間をそぞろ歩きしながら見慣れたはずの要素が見慣れない関係で次々と展開する光景に戸惑った。素朴な立体路地で構成された魚谷さんの作品は一体何を成し遂げたのだろうか。その意義はどこにあるのだろうか。答えがでることもなく新鮮な体験だけが残った。
コンテナ町家の意義を考えていきたい。切り口は様々にあるだろう。まず京都における都市構造と生活文化の関係を捉えることから始めたい。そして、路地と町家、このふたつを軸に魚谷さんの歴史的パースペクティブをともなう問題意識に並走しながら、私なりの理解を与えてみたいと思う。
京都の都市構造:グリッドによる段階的な奥行き
島村昇らによる「京の町家」(1971)(図1)は、平安京以来1200年の歴史をもつグリッド状の街路構造と町家内で敷地奥へと連なる室や庭を連続して捉え、京都の都市構造を段階的な奥行きの構成として描いている。通りを挟んで向かい合う30戸ほどの家々による町内行事の様子、オモテと呼ばれる隣人たちの共同広場である通りの様子、対してウチと呼ばれる町家内での家族活動の様子、あるいはトオリニワに併置されるミセノマ・ダイドコ・オクノマといった室の段階が客人の親密度の段階に応じて使い分けられる様子など、連続する奥行きの段階を人々が日常生活のなかで巧みに使い分ける様が報告されている。1960年代後半というある時点を捉えた調査であることを差し引いても、京都の生活文化が都市構造と有機的に結びついて成立してきたことを生き生きと伝えている。
奥行きの段階に展開する生活を捉えようとする視点は、書物の章立てにそのまま現れている。調査概要の説明のあとに「トオリ、オモテ・カド、オチョウナイ、ローヂ、マチヤブロック、京の町家、マチヤユニット、トオリニワ、オイエ、ニワ、ウチ」とつづく各章で段階に固有の生活と設えの関係が検討されていく。町家という建物の領域が連続する都市構造の一部をなしていることもよくわかる。
立体化した「長屋ローヂ」
ここに「ローヂ」という章がある。ローヂとは路地の呼称である。グリッド状の街路構造は、大通りに対して街区を構成する幅6–7mの通り、時に街区を小分けにする幅2–3mの小路と徐々にスケールダウンしていく。路地はさらに一段階下がった幅1–2mの外部領域のことである。町家が軒を連ねるのは通りであるが、路地もまた町家と同じように通りに入口をもつ。それは幅半間か一間で隣の町家の二階が覆いかぶさるトンネル状になっている。路地は基本的に行止りであり、「一軒ローヂ」と「長屋ローヂ」がある。一軒ローヂは、間口が狭く奥行きの深い町家の敷地割を奥行き方向に二分したときにできる奥の敷地へのアクセスであり、いわゆる旗竿敷地のアプローチである。長屋ローヂは、通りに連なる町家群の背後、すなわち街区中央の空地に建てられた長屋へのアクセスである。
島村らはこのローヂを京都の都市構造のなかでも特異な存在と記している。通りをオモテ、内部をウチと呼びわける町内の人々が、その間の段階的な奥行きを使い分ける生活文化のなかで、ローヂは奥行きの段階の上では町家と同等でありながらいまだ外部だからである。とくに長屋ローヂは、町家が家族に対応することと比べて、ひとつの領域に複数の主体の生活が重なることで共同性が一段と高まる領域になる。写真とドローイングに記録された当時の長屋ローヂをみると、共同のトイレや流しとともに様々な道具が首尾よく置かれ、誰かのものに溢れた誰のものでもない領域になっている。
ここまでくるとあの立体路地を構成した不思議な要素の関係性に合点がいき始める。コンテナ町家とは、端的に長屋ローヂを今日的条件のなかで立体化したものである。計画敷地に赴いて長屋と路地の痕跡を残した駐車場をみたとき、ディベロッパーの目には450m2の更地にみえたかもしれないが、魚谷さんの目には長屋と路地跡をとり囲む奥行40mの空隙が長屋ローヂを展開する舞台にみえたはずだ。
都市構造に特異な奥行きを与え共同性を醸成する長屋ローヂの特質を、いま残された素材を用いていかに拡張するか。これがコンテナ町家の取り組んだ建築的課題といえる。その達成にあたりまずクリアすべきは事業収支と建築法規である。外壁を問わない500m2以下の2階建て事務所建築という選択は、この課題からいえば手段にすぎない。オモテに対して廉価なウラという奥行きの考え方が、長屋としてのコンテナを受け入れ、ウラを垂直に展開する無骨な鉄骨フレームを受け入れる。長屋は住居からテナントに変わったが日々複数の主体が共同で使う意味で変わらない。この作品に集められた要素は、奥行きの段階的構成へ寄与するかどうかだけが問われており、素材感および慣習的な使途やスケールといったそこに関わらない物質の差異は制御されることなく放置される。逆にコンテナと覆いの配列による通路の幅と抜けには細心の注意が払われる。その差異の作られ方が人々に奥行きの使い分けを可能にするという確信があるからだ。
コンテナ町家という立体路地には、都市構造によって京都の生活文化が支えられてきたという歴史認識に貫かれている。一介の訪問者に不思議で新鮮な感覚を与えた要因はこの辺りにあるようだ。しかしここでひとつの疑問も湧いてくる。これは町家ではない。コンテナ町家改め「コンテナ長屋ローヂ」と呼んでもよさそうな気さえする。魚谷さんはどうして「町家」と呼ぶのだろうか。
町家という型:都市の全体性を内蔵した部分
町家とは間口が狭く奥行きの深い敷地に建てられる都市住居の型である。もとより町家は京都の通りに連なる庶民住宅であった。中世までの町家は浅く街区中央は広い空地に過ぎなかったが、町人文化が花開く近世には町家は二階をもち奥行き方向へと伸びてゆく。その内部には土間の列と座敷の列が間口を二分して並ぶ。日本各地の現存する近世町家をみると間口が広く座敷を二列以上もつ例もあるが、京都のような高密都市では座敷が一列のものが多く、限られた間口にトオリニワによる細長い奥行とミセノマ、ダイドコ、オクノマと続く室群による奥行が併置される(図2)。
こうした特徴を備えた町家という型には、ふたつの点で都市との有機的な関係が内在している。ひとつは街路と連続した段階的な奥行きを構成するという点であり、もうひとつは街路に横並びに反復されて町並みを構成するという点である。島村らが捉えたとおり、京都は両者が相まって共通性のなかに個別性を備えた都市を成立させてきたといえるし、たとえ街道沿いの宿場町であっても、町家の集積が街路を活気づけ、線状の都市形態を生み出してきた。町家とはいわば都市の全体性を内蔵した部分なのである。
しかし近世町家が培ってきた都市の姿は、近代都市計画の導入や戦災からの復興をはじめとしたこの100年の出来事をとおして急速に更新されていく。特に戸建住宅の一般化により、住宅と都市を構成する秩序はばらばらになっていく。その分断が強まれば強まるほど、都市と建築を有機的に関係づける町家という型は、現代の建築家の形式的想像力を刺激するようになる。
香山壽夫は「都市住居考」(都市住宅1973)(図3)にて、ロンドンやフィラデルフィアといった世界各地の歴史都市にも奥行きの段階をそなえた優れた都市住居の型があると指摘している。京都の生活文化がその使い分けに展開していたように、各地の生活文化と町並みを有機的に関係づける都市住居の型の比較から、現代都市の住まいに役立つ知恵を取り出そうと試みている。その念頭には、たとえば団地住戸のスチールドアが開けた途端に室内奥まで視線が貫通するような段階のない内外の連結への批判がある。あるいは近年、東京都心部のように稠密に建物が建ち並び宅地が細分化されるなかで、間口の狭さと奥行きの深さという敷地割の共通性を手がかりに、町家として設計された建築作品がみられるようになる*4.5。ここでは街路から敷地奥へと奥行きを巧みに分節することで個別の都市生活を位置付ける一方で、両隣へと反復されるポテンシャルをもちながらそうならない限界を前に、都市と建築を有機的に構成する秩序をもちえない社会における共同性の欠落を問うものとなっている。
奥行きと町並み:有機的関係のふたつの位相
町家という型は、建築家の形式的想像力によって、建築から都市のほうへと関係性を再構築する手がかりとして用いられるようになった。話を京都に戻そう。路地の立体化を実現した魚谷さんの形式的想像力は、町家を介して都市に問いを立てたこれらの試みに似ているようにも思う。ただ、歴史的建造物としての町家を残し、街路構造と敷地割という明確な都市の基盤をもつ京都においては、この100年の近代化による建築と都市の乖離が、ほかとはちがった様相の問題として現れている。魚谷さんが言及する街区奥マンションという問題をみながら、コンテナ町家の意義を検討してみたい。
旧市街の街区内には島村らがローヂと呼んだ古い路地が残されている。街区奥マンションとここで呼ぶのは、自動車の普及をとおして街路が道路として確立するにつれ、幅1–2mは車両が到達できずに再建築不可となった敷地が、ひとまとまりに合筆されて建つ、駐車場に囲われた中高層マンションなどのことである。この現象の問題点をどう考えられるか。まず本稿が示してきたように、京都の歴史都市としてのアイデンティティを、段階的な奥行きとしての都市構造と段階を使い分ける生活文化の関係にみるならば、これは路地の消失以上に奥行きの段階の消失という取り返しのつかない問題といえる。マンションは個室の集合体であり、自動車という個室と直結されては段階が入り込む余地はない。そのような暮らし自体はあってもよいのだろう。しかし問題の核心は、都市構造があれば今日なりの生活文化を組み立てられるが、都市構造が消えればその可能性も消えるという点だ。マンションは簡単に壊せない。京都の都市文化にとって少しずつ不可逆的な損失がおきている。立体長屋ローヂの存在意義をここにはっきりと読み取ることができる。
この立体長屋ローヂは町家と名付けられたのだった。設計者にとっては何気ないことだったのかもしれない。路地と町家、このふたつはともに京都の都市構造に欠かすことのできないピースである。これらがひとつの作品に混在することの意味は何であろうか。路地は幅1–2mほどの外部として、町家は設えが連なる内部として、街路から連続する奥行きの段階を構成する。対して町家には街路に横並びに反復して町並みを構成するという特徴がある。奥行きと町並み、それは京都における建築と都市の有機的な関係があらわれるふたつの位相といえる。奥行きは各々の間口の向こうに体験されるものである。町並みは街路に立てば見えるものである。奥行きが日々の繰り返しのなかでしか捉えられないのに対して、町並みは一度見れば概要を捉えることができる。この有機的関係があらわれる位相の捉えやすさの違いは、そのまま私たちや社会の京都という都市の固有性への理解に対応しているように思われる。たとえば景観法である。内容はさておき、この制度の存在は、おおきくみれば建築と都市の有機的関係を社会が認めていることでもある。対して奥行きが忘れられているのは、オモテ・ウラという考え方以上に、個別の実践の価値を社会に共有しうる建築言語をいまだもちえていない、ということではないだろうか。魚谷さんの試みは、こうした都市が抱える建築的課題の縮図を、ひとつの作品にパラフレーズしているのではないか。路地と町家、奥行きと町並み、京都という歴史都市を建築の側から考えることを可能にするふたつの位相を同時に私たちの認識に投げ込んでくるところに、この作品のもうひとつの意義があるように思われる。
参考文献
1 島村昇ほか『京の町家 -生活と空間の原理-』(鹿島出版, 1971)
2 『日本の民家6 町家II』(学習研究社, 1980)
3 香山壽夫「都市住居考」(都市住宅1973.9)
4 塚本由晴「町家:まちをつくる家」(「日本の家 -1945年以降の建築と暮らし-」, 2017)
5 佐々木啓, 森中康彰, 能作文徳, 塚本由晴「奥行の分節と統合による町家型住宅作品の構成」(日本建築学会計画系論文集, 2015)