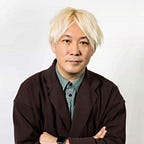2019年12月18日に開催された第3回あいちトリエンナーレのあり方検討委員会において、「『表現の不自由展・その後』に関する 調査報告書(案)」が発表されました。
最終報告については案が出てきたときに事実と異なるあるいは報告書として不適切な点について、修正を要求しています(が、こちらの要求はほとんど反映されていません)。修正の要求を行ったファイルを下記に置いておきますので、ご関心のある方はこちらからダウンロードください→http://j.mp/38QjOyE
最終報告書案ほか配付資料は下記からダウンロードできます→ https://www.pref.aichi.jp/soshiki/bunka/gizigaiyo-aititori5.html
また、検討委員会の内容は録画で見られるようになっています↓
僕から提出した参考資料を下記に置いておきます。
(1)「『表現の不自由展・その後』に関する調査報告書」に対する意見書
(2)記者会見の発言要旨
(3)美術専門家による意見 その①
(4)美術専門家による意見 その②
(1)「『表現の不自由展・その後』に関する調査報告書」に対する意見書
「『表現の不自由展・その後』に関する調査報告書」について、あいちトリエンナーレ芸術監督として補足的に述べることは下記のとおりです。
1.公平性の問題
「表現の不自由展・その後」に関する調査報告書は、芸術監督に責任を負わせるという結論ありきなのではないかとの疑いを生じさせるものであった。実際、調査報告書では、芸術監督に対する非難に固執する部分が散見される。2.整理の不徹底
検証委員会の報告書は、基本的に、「検証ポイント」「わかったこと」「備考」の三要素からなっている。この場合、「わかったこと」欄には検証の結果判明した事実を記載し、これに関連する検証委員の意見は「備考」欄に記載するのが相当である。しかるに、検証委員の意見に過ぎないものが「わかったこと」欄に記載されている例が散見される。3.展示を不快に思う勢力が妨害行為をしたくなるような展示を自粛することの当然視
検証委員会の報告書は、キュレーションに問題があったとして、これに関与した芸術監督と不自由展実行委員会を非難するとともに、不自由展のキュレーションには事務局もキュレーターチームも関与していなかったとしてその非難が及ばないようにしている。実際には、事務局のプロジェクト・マネージャーから指名を受けた愛知県美術館のアシスタント・キュレーターが一部とはいえ、不自由展のキュレーション業務をしているし、このアシスタント・キュレーターは、あいちトリエンナーレのキュレーターチームの会議や表現の不自由展実行委員会と芸術監督との会議にも出席している。したがって、不自由展のキュレーションには事務局もキュレーターチームも関与していなかったというのは真実から乖離している。また、不自由展が妨害を受けたことの原因をキュレーションの問題とするのは、キュレーションさえ正しければ「表現の不自由展・その後」の展示を不快に思う勢力が妨害を行うことはなかったということを前提とするものであり、彼らが妨害工作をするまでもないキュレーションにするように展示内容や展示方法に自主的に制約をかけることを当然視するものであって、今後行政が主催する芸術祭の展示企画に対する萎縮を招くという点で容認できるものではない。
4.因果関係の軽視
検証委員会の報告書は、不自由展が一時中止に追い込まれた原因を探求することよりも、責任を芸術監督に負わせることに照準を合わせたものであった。時間的経緯からいえば、あいちトリエンナーレ開幕直前に、「平和の少女像」が展示されることが報道された直後に、トリエンナーレ事務局に大量の抗議電話がなされて事務局の電話がパンク状態となり、また、放火を仄めかす脅迫FAXにしても「平和の少女像」を茶化したものと思料される絵が描かれていたのである。このことから、妨害行為や脅迫行為を行った人々のほとんどは、トリエンナーレの展示、とりわけ不自由展の展示を実際に見ることもなく、「平和の少女像」が展示されているという報道ないしSNSで得た知識だけで、妨害行為や脅迫行為を行うに至っている。したがって、不自由展において、どのような作品をどのように展示することにしようと、あるいは、展示作品に関する解説をどのようにしようとも、同様の妨害・脅迫行為がなされた可能性が高い。
しかるに、報告書では、芸術監督の作為・不作為に関するあら探しをすることに終始している。報告書において芸術監督はこのようにするべきであったということを行い、または、このようにするべきではなかったとされていることを行わなかった場合に、今回のような妨害ないし脅迫が避けられたとする合理的な根拠が見いだせない。
今回は、美術展における特定の作品について間違った情報がSNSや保守系メディアにおいて流布され、それが妨害・脅迫行為の原動力となったというケースであり、このような場合に誰がどのように対処をするべきであったかというのは、今後の美術展の運営にも役立つ現代的な課題である。しかるに、検証委員会は、芸術監督に責任を押しつけることに役立ちそうにない上記課題を検証しようとしなかった。
5.予測の共有
不自由展自体が「過去に妨害行為等を受けて展示中止に追い込まれた作品を集めたもの」という性質を帯びていること、しかも展示作品の中に「平和の少女像」が含まれていることから、極右勢力による妨害行為がなされうることは、あいちトリエンナーレの実行委員長である大村知事も、トリエンナーレ事務局も、事前に共有していた。検証委員会の報告書では、ネット社会に詳しい芸術監督のみが係る危険を予測していたのに実行委員会や事務局に告知しなかったかのような記述があるが、明らかに間違っている。展示を不快に思う勢力からの妨害に備えるのは、基本的には事務局の仕事であり、実際、事務局は、不自由展の実行委員らとともに、警察の指導を仰ぎながら、外部からの妨害に備える準備をしていた。事務局は警察や弁護士など専門家の助言を受け、抗議に対する準備をしていたが、一部の政治家やSNSが攻撃を煽るような発言を行ったことで想定を超える抗議や脅迫が殺到したが故に、不自由展が一時中止に追い込まれたのである。
本来であれば、外部からの抗議を煽った原因とともに、上記準備のどこに問題があったのかを検証すべきだったのであり、それは、極右勢力の不興を買うような作品を別の美術展で展示する際の教訓ともあり得べきものであった。しかし、検証委員会は、芸術監督に責任を負わせることに汲々としており、上記のような観点からの検証はなおざりとなった。
6.調整行為に対する非難
あいちトリエンナーレに向けた準備をするにあたっては、予算及び会場の都合と出展作家の希望とのギャップを埋めるために、芸術監督は様々な調整作業を余儀なくされた。このことは、不自由展に限られない。その結果、多くの作家があいちトリエンナーレに質の高い作品を出展し、過去最大の来場者数を記録することとなった。しかるに、検証委員会の報告書では、芸術監督のこれらの調整行為を口汚く非難するに至っている。出展作家の希望を容れて妥協したことと、展示を不快に思う勢力による妨害・脅迫行為との因果関係すら示せないまま、芸術監督による調整行為をこの報告書の中で非難するのは不適切である。
7.法律用語の不適切な用法
検証委員会は芸術監督に責任を負わせることを至上命題としていたためか、法律用語をその本来の用法と異なる意味で用いる例が散見される。たとえば、委任・準委任契約における「善管注意義務」とは、受任者が委任事務を処理するにあたって払うべき注意の程度を表した概念であり、具体的な委任事務の内容とは別に「善管注意義務」が生ずるわけではない。しかるに、報告書では、「大浦氏の新作映像の内容を知り、またその出品を5月27日に正式決定したにもかかわらず、作品リストに掲載せず、またその事実とそれがもたらす混乱の可能性やリスクを事務局やキュレーターチーム、会長に伝えないまま展覧会の開催日を迎えたこと(「善管注意義務違反」との批判は免れえないであろう)。」との記載がある。芸術監督としての委任事務の中に、展示作品の詳細が変更となった場合にその旨並びにそれがもたらす混乱の可能性やリスクを事務局やキュレーターチーム、会長に直々に報告するというものが含まれていない以上、そのようにしなかったことが善管注意義務違反となるはずがない(大浦作品の新作映像を不自由展の中で上映することとした点は、事務局に伝わっている。通常は、それをキュレーター、アシスタント・キュレーターないしはプロジェクトマネージャーから事務局経由で会長へ報告がなされるべきものであるが、あいちトリエンナーレ自体あるいは不自由展については展示内容について芸術監督自身が事務局や会長、キュレーターチーム等に報告する義務を負っているという話は少なくとも芸術監督には一度も説明されておらず、実際にそのような報告義務が課される合理的な根拠もなかった)。8.責任の切り離し
検証委員会の報告書ではガバナンスの問題として愛知県美術館の館長が事前に危機やリスクを察知し、会場として貸さない、あるいは条件付きで貸す等の措置をとりえたが、慣行上あいちトリエンナーレにおいては館長の権限が事実上行使できなかったと結論付けているが、事実と異なる。愛知県美術館館長は、同館で展示される内容について展示プランをチェックし、必要に応じてキュレーターチームに注文を付けることが可能だった。一例を示せば、同館8Fに展示されたタニア・ブルゲラの作品は当初「安全管理上問題がある」という理由で館内での展示が拒否された。その後館長の懸念を払拭するためのリサーチや展示プランの提示を行い、再交渉した結果展示が認められたという経緯がある。「表現の不自由展・その後」の企画についても事前に館長に共有し、チェックが入った上で館長から「展示自体は問題ない」と許可を得るプロセスを経ている。このことからわかるように「慣行上、あいちトリエンナーレにおいては館長の権限が事実上行使できなかった」という事実はなく、芸術監督一人に責任を負わすために導き出された架空の「ガバナンス上の問題」である。
9.県民からの理解
検証委員会の報告書には「県民からの理解が得られない」「県民や協賛企業からの信頼を失わせた」との記載が散見されるが、何ら根拠がない。なお、今回の騒動後に協賛を取り消した協賛企業は一つもなく、複数の協賛企業の担当者から「自分たちがこれによって降りることはないので、卑劣な脅迫や抗議に負けないでください」という趣旨の温かい言葉をかけていただいた。
検討委員会終了後、13時30分から愛知県庁県政記者クラブで記者会見を行いました。下記が発言要旨となります。
(2)記者会見の発言要旨
はじめに、僕の方から検討委員会についての最終報告についてコメントさせていただきます。まず、中止に至る今回の騒動で最も責任が大きいのは誰かといえば、いわずもがな展覧会を脅迫した人々、そして事務局機能を麻痺させるほど「電凸を煽った人々」にあるわけです。これに同意されない方は、この場にもほとんどいらっしゃらないかと思います。非常にシンプルな構図であり、本来検証されるべきは、脅迫や電話攻撃――電凸があった時にどのような対策が可能だったのか、という点であるべきだったのではないかと思います。
脅迫に対して速やかに対処できなかったのか、それは当初の警察の動きが鈍かったということが大きな理由であり、警察も愛知県内の組織であるわけですから、この対応のまずさについて突っ込んだ検証が必要だと考えますが、中間報告には検証がなく、最終報告でも1行ほどのわずかな文字数でふれるに留まっています。
電凸に対して事務局機能が破壊された。電話攻撃の初動対応に問題はなかったのか、どのような対策を取れば耐えることができたのか――大村知事が電話対応を変えた9月17日以降は、事務局機能が麻痺するようなこともなくなり、概ね問題なく電話抗議に対して対処できていた。このことを踏まえ、初動の電話対応についての検証をきちんと行うことが、今後の運営に対しても、日本中の公立文化施設に対しても有用であるにも関わらず、この点についても十分な検証ができていません。
中間報告から大きく結論を変えられないという話をヒアリング中に聞きましたが、そうした前提を崩せないため、本来検証されるべきことが隠れてしまったなという印象です。
基本的な話として、妨害を受けるなどして展示が中止された作品を集めた「表現の不自由展」を参加作家として含め、その中の出品作品として平和の少女像を展示することとした時点で、一定の妨害工作を受けることは誰しもが予測していて、僕そして事務局及び警察はその前提で対処していたわけです。
しかし、苦情電話を受ける事務局の抗議電話対策が想定を超える量が来て破綻してしまったということと、非常に凄惨な「京都アニメーション放火殺人事件」が起き、それと同種の犯行を匂わせるFAXが届きます。報告書ではなぜか、芸術監督の僕だけがその混乱の大きさを予測できたという話になっています。企画が決まった6月以降の日韓関係の急速な悪化を予想し、公職にある政治家の皆さんが一自治体の文化事業の内容にあれほどまでに干渉してくると予想し、そして京都アニメーションの放火殺人事件を予想できるものでしょうか?
僕は超人ではないので、そんなこと予想できません。というより、世界中の誰もこれほどまでの事態を事前に予想できないと思います。
であるにもかかわらず、検討委員会は、僕がこれらのことを予想し得たとして、僕だけを責任追及することに終始しているかのようです。一体検討委員会はこの最終報告で何を検証・検討し得たのでしょうか。
そもそも、そうした混乱を予想できたとして、僕は安全対策に関する業務は委託されていません。一般的な芸術祭においても、芸術監督が会場の安全対策まで責任を負うという例は聞いたことがありません。今回のようなイレギュラーな事態を引き起こしてしまった上でこう言うと誤解があるかもしれませんが、それでも基本に立ち返ると、通常「芸術祭運営上の安全対策」というのは本来、事務局や県が中心となって行うべきものだというのが一般的な感覚ではないかと思います。
その上で、これほどまでに騒動が大きくなったのですから、警察はきちんと対応するべきだったということは重ねて強調しておくべきだったのではないでしょうか。僕の方に警察が動いてくれないという話が伝わってきて、必要に迫られてやりましたが、なんで脅迫のFAXを分析して店舗を特定したり、脅迫メールを送る踏み台にされた宗教団体に連絡を取ってIPアドレスを提供してもらったり、僕自身に殺害予告がなされた通報があったにもかかわらずその連絡が愛知県警から直接なかったばかりか、東京の住所地の警察から「被害届は出さないと愛知県警から聞いたが本当か」と言う電話を受けなければならなかったのかと。
そもそも「表現の不自由展」が参加作家に加わる発表をしたのは、3月末の時点です。その時の発表文章にも不自由展にどのような作品が並んできたかは明記してありました。
しかしみなさんご承知の通り、あいちトリエンナーレにおいて「平和の少女像」が展示されることが、改めて7月31日付けの新聞各紙朝刊にて報じられるやいなや、電話攻撃が始まりました。その日の午後には事務局の電話回線がパンク状態となるわけですが、この時点で一般市民は「表現の不自由展・その後」の実際の展示どころか、あいちトリエンナーレ自体を観られていないはずなので、上記大量の電話攻撃は、「表現の不自由展・その後」のキュレーションとは無関係になされていることを、僕は繰り返し指摘してきました。
その後、8月1日ころに大浦氏の映像作品の一部が煽動的な文言とともにネット上にアップされると、翌8月2日ころから大浦映像作品に関する抗議の電話も増えていきますが、大浦映像作品を展示したことに抗議している人々のうち、実際に「表現の不自由展・その後」において上映されている大浦映像作品を観た上で抗議をしている人はほとんどいませんでした。すなわち、これらの抗議活動は、「表現の不自由展・その後」の外で得た情報に基づいてなされていることが明らかです(デマ情報を鵜呑みにした抗議も多い時期でした)。
ところが検証委員会の報告書は、「表現の不自由展・その後」の展示会場内でしかるべきキュレーションをしていれば、これらの抗議活動を抑えることができたという前提にあくまでも立っているように見えます。抗議電話をかけてきた人々のほとんどが「表現の不自由展・その後」の展示会場を訪れていない以上、上記展示会場内でどのようなキュレーションをしようが彼らに届かないことは明白であるにもかかわらず、です。
そのため、上記報告書内で「こうすれば良かった」「こうするべきであった」ということがいくら指摘されていても、すべて現実離れしたものとなってしまっています。「こうすれば良かった」「こうするべきであった」という話は、そのようにしていれば混乱を避けることができた蓋然性が相当程度高い場合にのみ言えるはずですが、上記報告書は、そのようなものにはなっていません。
「表現の不自由展・その後」は、元々種々の抗議活動を受けて展示が中止された作品を集めて展示する企画であり、その中に「平和の少女像」が含まれている以上極右からの抗議を受ける危険があることは想定されていたし、その旨はトリエンナーレ実行委員会及び事務局にも共有されていました。
5月23日に、トリエンナーレ事務局がその顧問弁護士に相談した際に、「脅迫や爆弾予告などが理由で催しを中止したり、万が一、事故が起こっても、それは脅迫や爆弾予告をする人間に非があり、作品を展示する側には非がない」というアドバイスを受けているのが何よりも証左です。だからこそ、トリエンナーレ事務局と不自由展実行委員会とが警察の指導を仰ぎながら安全対策を練っていたわけです。
再度整理すると、大浦映像作品が認知される前から大量の抗議電話が寄せられていました。また、脅迫FAXも「平和の少女像」について向けられたものであって、大浦映像作品に向けられたものではありません。
検討委員会による報告書は、大浦映像作品を展示することを僕が報告していなかったことを特に問題視しようとするものですが、大浦映像作品を展示しようがしまいが、相当程度の抗議活動を受けることは想定した上で事務局を中心に対策を講じてきたわけです。しかし最終報告書は、事務局における安全対策の不備の責任を、一方的に僕に押しつけようとするものと言わざるを得ません。
大浦作品の新作映像を不自由展の中で上映することとした点は、事務局に伝わっていました。通常、作品展示に関する進行で問題がある場合は、それをキュレーター、アシスタント・キュレーターないしはプロジェクトマネージャーから事務局経由で会長へ報告がなされるべきものです。しかし展示の内容に関しては、芸術監督はじめ、キュレーター、アシスタント・キュレーター、プロジェクトマネージャーにも報告の義務はなかったと承知しています。
少なくとも、あいちトリエンナーレ自体あるいは不自由展については展示内容について僕自身が事務局や会長、キュレーターチーム等に報告する義務を負っているという話は僕には一度も説明されておらず、実際にそのような報告義務が課される合理的な根拠もありませんでした。報告書ではそのことをおいたまま、それを後付け的に責任を取らせるという構造になっています。
元々、僕を始めとするキュレーターチームは、個々の出品作品の内容について実行委員会や事務局に報告する義務を負っていないし、基本的にそのようなことは「表現の不自由展・その後」以外の作品についても行っていません。それは、アシスタント・キュレーターや、ほかのキュレーター陣の認識も同一であるということが報告書の記載によってわかりました。したがって「表現の不自由展・その後」において大浦映像作品を展示することが決定したからといって、その旨及びその作品の内容を実行委員会や事務局に直に報告する義務は僕にも、キュレーターにもなかったということです。
つまり、「表現の不自由展・その後」において大浦映像作品を展示することやその内容をことさら僕が秘匿していたわけではなく、そもそも芸術監督である僕自身が事務局や実行委員会に報告する義務自体がなかったわけです。だから、そこに「善管注意義務」なんてないのです。
しかし、報告書では、「大浦氏の新作映像の内容を知り、またその出品を5月27日に正式決定したにもかかわらず、作品リストに掲載せず、またその事実とそれがもたらす混乱の可能性やリスクを事務局やキュレーターチーム、会長に伝えないまま展覧会の開催日を迎えたこと(「善管注意義務違反」との批判は免れえないであろう)。」との記載があります。この善管注意義務の内容がなんで、それがどこから出てきたか、皆さんわかりますか?
意見書でも書かせていただきましたが、検討委員会は法律用語を不適切に利用して、個人攻撃を行っています。「善管注意義務」もそうですが、ヒアリングの際に、僕が「参加作家の制作費や滞在費の足しになれば」と思い「参加作家発表後」に「ギャラリー経由で」購入したトリエンナーレ参加作家の作品を購入した行為をある委員から「インサイダー取引」と言われたことにも驚きました。インサイダー取引って例えば業務上過失致死より重い、めちゃくちゃ刑罰の重い犯罪なんですけど、人をそんなカジュアルに犯罪者呼ばわりして大丈夫かと思いました。
そして、皆さんにご報告しておきたいのは、今日の検討委員会で配られた僕の最終報告に対する意見書がありますが、これは上山副座長によっていったん内容が拒否されています。僕個人の意見書であるにも関わらず、委員への個人攻撃を含むので認められないと、このままこれを公文書に残すことはできないと言われました。
削除されたのはこの部分です。
「表現の不自由展・その後」については、吉村洋文大阪府知事が「「公権力を行使した明らかな反日政治活動である展示」などとの批判をしていた。その大阪府の特別顧問である上山信一氏が検証委員会の副座長を務めたことは、検証委員会の中立性に対する信頼を害し、僕に責任を負わせるという結論ありきなのではないかとの疑いを生じさせるものであった。実際、調査報告書では、僕に対する非難に固執する部分が散見される。
これは、個人攻撃でしょうか? 事実を摘示して、このような疑いがあると述べただけです。しかもこの削除指示が副座長案としてきていたのですが、なぜ座長案ではなく、副座長案だったんでしょうか。それは検証委員会を事実上副座長が取り仕切っていたので、副座長の独断でこういう指示を行えるということなんでしょうか。検討委員会がどのような力関係だったのかは僕のあずかり知らぬところなので、記者の皆さんにはぜひ取材していただければ幸いです。
というか……個人攻撃というならありもしない善管注意義務違反という不適切な法律用語を用いて個人を断罪するこの最終報告書自体が個人攻撃なんじゃないか? と思います。
上山さんは検証委員会がヒアリングしている最中に、大阪府の吉村知事とほぼ同じような批判を不自由展に対して、検証委員会の副座長という公的立場にありながらツイッターで行っています。僕自身もツイッターで検証途中であるにも関わらず「津田はあざとい人間だ」と、それこそ個人攻撃されました。
「個人攻撃が含まれてるから意見書には載せない」というのは、ご自身のやってきたことを踏まえれば、いかがなものかと言わざるを得ません。
最終報告書案を貫くのは、とにかく責任を僕のみに押しつけたいという強固な意思です。このため、今後の教訓となる内容は含まれていません。
問題は、
①特定のイデオロギーを有する人にSNS等で煽動がなされた場合にどう対処するべきか、
②粗暴な内容の抗議電話が大量になされたり脅迫等がなされた場合にどう対処すべきかということであって、これに対してどのセクションの対応に瑕疵があったか。これを検証するのが検討委員会の仕事であると思います。
しかし、最終報告書は、とにかく責任を僕のみに押しつけたいということに終始してしまっているため、そのような抗議電話や脅迫をされてしまうような展示をしたこと自体が問題であるという方向で報告書案を作成してしまっています。
これは、芸術祭等においては、今回抗議活動や脅迫等をしてきた人たちを怒らせないようにしなければならないということを前提とするものであって、表現の自由という観点からも、美術業界の現場にも、今後の行政が開催する文化事業のあり方にも禍根を残すものになるでしょう。
この「禍根」は、文化庁の不交付問題とも密接に関わります。
文化庁は「補助金申請者である愛知県は、展覧会の開催に当たり、来場者を含め展示会場の安全や事業の円滑な運営を脅かすような重大な事実を認識していたにもかかわらず、それらの事実を申告することなく採択の決定通知を受領した上、補助金交付申請書を提出し、その後の審査段階においても,文化庁から問合せを受けるまでそれらの事実を申告しませんでした」との理由で、愛知県への補助金を付交付する旨の決定をしており、愛知県の大村知事はこの決定について不服申立てをする意向を示しています。
そのような状況を鑑みて、展覧会の開催にあたり、来場者を含め展示会場の安全や事業の円滑な運営を脅かすような重大な事実を認識していたにもかかわらず,それらの事実を申告しなかったとして、僕を糾弾する内容の最終報告をするということが、どのような効果をもたらすのか、理解されているのでしょうか。
繰り返しになりますが、トリエンナーレ事務局は、5月23日にトリエンナーレ事務局の顧問弁護士に相談した際に、「脅迫や爆弾予告などが理由で催しを中止したり、万が一、事故が起こっても、それは脅迫や爆弾予告をする人間に非があり、作品を展示する側には非がない」というアドバイスを受けています。それは、法的には正しい判断であり、脅迫や爆弾予告などが理由で催しを中止したりした場合に、犯人をしてそのような犯行に至らしめるような作品の展示をする側に非があるということになれば、自分が気に入らない作品が展示された場合に脅迫や爆弾予告などをしかねない人々を刺激するような作品を展示することを回避することにつながってしまうからです。そして、それは、特定の種類の作品が展示されたことについて一度脅迫や爆弾予告等をしてしまえば、別の展示会で同種の作品を展示することをも抑圧することにつながり、脅迫や爆弾予告などをする人々に大きな報酬を与えることになってしまいます。
検証委員会の中間報告書や、最終報告書を見る限り、大量の電話攻撃や脅迫を引き起こすような展示をしたことに問題があり、その責任が僕にあるという方向で結論付けをしていますが、それは、今回、大量の電凸や脅迫を仕掛けた側を喜ばせ、今後もどこかの美術館等で気に入らない作品が展示された場合には大量の電凸を仕掛けたり脅迫をしてやろうというインセンティブを彼らに与えることになると思います。
そして、この最終報告書は、抗議者・脅迫者だけでなく、行政手続きとして著しく問題の大きい不交付を決めた文化庁や、費用の不払いを検討している河村名古屋市長を利する結果をもたらすことになってしまいますが、それは、あえて検証委員会を作ろうとした大村知事の意向に反しているようにも思います。
なぜこのような最終報告書になったか。中間報告に対しての異議申し立てをしたあとのヒアリングの場で上山さんが「でも中間報告でそう言っちゃってるからなぁ」と発言されたことを、僕は聞き逃しはしませんでした。そのことは今回の最終報告書が「愛知県には一切瑕疵がなく、芸術監督個人の責任を追求することで愛知県を守る」内容になっていることをよく示していると感じます。
個人的に最終報告書でもっとも受け入れがたいのは、一連の騒動を「ガバナンスの問題」と称して、事務局が“素人集団”だったからこれが起きたというトーンで評価し、プロフェッショナルを入れることで再発を防ぐという解決策を出しているところです。現場、事務局の職員は間違いなく「事務職のプロフェッショナル」としてアーティストや僕から出てくる面倒な要望、難題を不満も言わず実現するため必死で動いてくれました。充実した芸術祭をつくるという一点で、現場のスタッフたちはつながっていました。優秀な愛知県職員たちがいなければ、あいちトリエンナーレ2019の内容面での高い評価や、国際芸術祭として異例の動員も記録することはできなかったでしょう。このことは疑いがありません。彼らの名誉のためにも、最終報告を訂正してもらいたいと思っています。
僕個人としては、検討委員会のヒアリングには最大限協力してきましたし、真摯に問題を検証した報告書が出るものと信じていました。その点で大変残念な思いでいっぱいです。自分の責任についてはこの身で十二分に思い知っていますが、このように本当の問題を覆い隠す検証報告では問題の本質がまったく伝わらないと思いますので、今後もこの問題について個人として検証を行っていきたいと思います。
最終報告書では「不自由展のキュレーションに問題があったから騒動が起きた」というトーンで貫かれていますが、キュレーションの内容を評価する2人の美術専門家の意見を最後に掲載しておきます。
(3)美術専門家による意見 その①
検証委員会による中間報告を一読し、一キュレーターとして大きな違和感を持ちました。一言でいえば、それは「現代美術におけるキュレーションの無理解」です。
「通常のキュレーションであれば」、「正攻法をとるならば」、「もし専門家だったならば」という仮定がことごとく的外れであると言わざるを得ません。
「表現の不自由展・その後」は、チャレンジングな企画であり、全く新しいキュレーションの方法論を試行せずして、実現することはできません。それが「実現できた」という点を最大限評価するならまだしも、実現できたにも関わらずその瑕疵を指摘し、その後発生した諸問題の原因をキュレーションに帰結させるというのは、論理的な無理が生じています。
展覧会は、アーカイヴ的なアプローチであると同時に現在時における企画展でもありました。左派的なものもあれば、そうでないものもありました。美術史的に重要な作品もあれば、ささやかな一個人の表現もありました。
つまり、イデオロギーに収まらない多様性が「誰の意図にも収斂せずに」存在していた。鑑賞者の政治意識や倫理をいい意味で分裂させ、反省させしめるような多義性があった。日本のアートシーンが見過ごしてきたもの、等閑視してきたものを批判的に検討する空間が生成していた。このような状況をして、私は一段上の、クオリティの高いキュレーションが実現されたと捉えています。津田氏のキュレーションを「素人仕事」、「クオリティが低い」とする意見は、現代美術が現在おかれているアクチュアルな状況が見えていない、呑気な言葉であると私には思えます。
キュレーターがその強いコンセプトによって全体をコントロールするというロールモデルが成立するのは、せいぜい過去30–40年程度のものです。過去を扱う美術館的なキュレーションに比して、現代美術のキュレーションは、その基盤が脆弱である。であるがゆえに不断の技術的更新を必要とするものです。とりわけ、現代美術の価値が根源的に問われている今、キュレーションはそれに応える実験精神を発揮しなければならない。そういった意味で、中間報告の指摘は、未来のキュレーターに対して表現の萎縮を生じさせるものだとも言えます。
遠藤水城(キュレーター、ビンコム現代芸術センター芸術監督)
(4)美術専門家による意見 その②
あいちトリエンナーレのあり方検証委員会による2019年9月25日付・中間報告を拝見いたしました。私はあいちトリエンナーレに直に関わる者ではなく、同トリエンナーレと津田大介芸術監督とのあいだの組織上の関係の妥当性について判断できる立場にありませんが、同中間報告で同氏が手がけた「表現の不自由 その後」について、ジャーナリストとしての個人的な関心を優先するあまり、税金でまかなわれる施設を使用するに足る分別を欠いた展示になっているとの指摘があり、その点について一批評家として違和感を持ちましたので、ここに意見いたします。
第一に強調しておきたいのは、わが国で現在、「表現の自由」をめぐって起こりつつある問題を、個々の事例を通じて広く共有し、多様な議論を交わす機運を作り出すことは、今後、日本の文化・芸術が向かう行方を左右するほど大事な、喫緊の課題であり、決して個人的な関心に偏向したものでも、芸術祭としての公益性を欠いたものでもない、ということです。問題の本当の所在は、にもかかわらず、こうした企画が美術館など具体的な表現を扱う公的な施設で開かれる機会がないまま、現在に至るまで推移して来てしまっていることにあり、国際的な文化・芸術の水準と照らしてみても、そちらのほうがはるかに異常なのはあきらかです。
私も会員として所属する国際美術評論家連盟・日本支部(AICA JAPAN)では、このような事態に対応するため、2016年にシンポジウム「美術と表現の自由」を開催いたしました(7月20日、東京都美術館)。本シンポジウムは、ろくでなし子氏の作品をきっかけとする逮捕と身柄の拘束、それに続く一連の裁判、愛知県美術館に展示された鷹野隆大氏の展示に対する愛知県警察からの撤去指導、東京都現代美術館での会田家の展示への改変要請をはじめ、表現の自由が問われる出来事が近年、立て続けに見られるようになったことを受けて企画されたもので、その発端を1986年、富山県立近代美術館で起きた大浦信行氏の作品へのあからさまな毀損にまでさかのぼって論ずるというものでした。
シンポジウムは、同連盟の主催する定例事業としては異例な盛況で迎えられ、想定を超える関心の高まりと、多くの人が感じている共通の危惧を実感いたしました。が、同時に多くの課題を残しました。実際には、そこで論じられた案件は氷山の一角に過ぎず、類似した事例は報告だけでも増加の一途をたどっているからです。より公的な場で、さらに広く問題を共有し、議論を深める機会が必要なのは、誰の目にも明白でした。
今回、「表現の自由」をめぐる問題を扱う展示が、津田芸術監督の発案で、あいちトリエンナーレのような公的な場で実現されたことは、第一義的には高く評価されるべきことであって、そのことを置いて、展示の仕方やキュレーションについての部分的な瑕疵や不備を指摘することに終始してよいはずがありません。わが国が置かれた「表現の自由」をめぐる困難な現状を見据え、より大局的で公正な検証と判断を期待します。
椹木野衣(美術批評家)