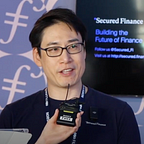Event Report
DeFi meets TradFi:Web3が変える金融の未来
〜 パネルセッションの一部を紹介 〜
2023年4月21日、CoinDeskジャパン主催のイベント『DeFi meets TradFi』が開催されました(紹介記事・イベントレポート)。Web3が日本の成長戦略として注目される中、今回のイベントはDeFiに特化した初の試みとなりました。自民党web3PTをリードする政治家、Web3を牽引する創業者、世界を代表するDeFiプロジェクト、大手金融機関、法律家など、各分野のエキスパートが一堂に会し、テクノロジーと規制の両面から意見交換を行いました。本記事では、盛り上がったパネルセッションの後半部分をご紹介いたします。(English transcript here)
登壇者・モデレーター(敬称略)
菊池 将和:Secured Finance AG Founder & CEO
工藤 秀明:野村ホールディングス株式会社 デジタル・アセット推進室 エグゼクティブ・ディレクター
河田 雄次:株式会社 三菱総合研究所 主任研究員
増田 雅史:森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
金光 碧:株式会社bitFlyer Head of Crypto Strategy Dept.
DeFi普及の道筋について
金光)ここからは日本におけるDeFi普及の道筋というテーマでお話をしていきたいと思います。実際に普及させるフェーズになった際には、今工藤さんに一部お話いただきましたが、どういうことが必要になるのかというのを皆様のそれぞれのご立場からお話いただければというふうに思っております。まず、あの菊池さんにお話しいただきたいんですけど、そもそも菊池さんにとって、その日本においてDeFiが普及するってどういうことか、というところを含めて、その普及という定義があったところで、そこに行くために何が必要かみたいなところをお話しいただければと思います。
菊池)そうですね、日本においてDeFiが普及するというのは、DeFiを何としても普及させたいというわけではないんですけれども、まあ新しいアセットクラスとして、暗号資産というのは非常にユニークな特徴を持ってますし、非常に魅力的な運用の対象だと思うんですね。で、そのエクスポージャーを取りたいという投資家の方がいます。エクスポージャーを取るために金融機関さんはそれを何とかして商品にラップする。僕らストラクチャラーからするとどんな形でもいいんですよ。預金でもいいし、債券でもいいし、ファンドでもいいし、ダイレクトのあれでも何でもいいんですけれども、ただお客さんとしてこういうリスクプロファイルが欲しいよねって時に、それをどのように調理して出すかっていう問題であって。
日本というのは非常に面白いマーケットで、長期にわたってものすごく低金利にあえいでいるので、少しでも金利が高いとそれがものすごく魅力に映るというところがあります。ということで、非常に証券会社さんですとか、工夫されていろいろな売り出し債とか、いろいろな形の債券を出されていて非常に人気ですよね。そういった形で、エクスポージャーを今あるフォーマットに乗せて売るっていうのは一つのあり方であって、そういうことは可能になってくるのかなと思ってます。
で、もうちょっと一般的な、具体例をと思っていますと、僕は結構これ料理に例えるんです。料理って別に自分でマーケットに行って、りんごとか野菜とか買ってきて自分で手料理作って食べられますよね。それってダイレクトにマーケットにアクセスして勝手に取引する世界観なんですよね。それはそれでうまいですと。ですけど、かといってレストランが全部潰れるわけないですよね。やっぱりそれを組み合わせておいしいタイミングで一番おいしい料理を出す人がいると、そういう感じで、やっぱりプロフェッショナルとして、そういうサービス、金融サービスの提供者として、今後はやっぱり日本は日本のマーケットをよく熟知した日本の金融機関さんとかが、きっちりとしたレギュレーションを持って広く商品を普及させることは可能なんじゃないかなと思ってます。
金光)なるほど。とするとTradFiの方々に期待をする部分も大きいというところですが、今の話を聞いて、工藤さん、いかがですか?
工藤)そうですね。はい、そのように思います。
金光)ありがとうございます。そういった世界観になっていく上で、これ、増田先生にお伺いしたいんですけど、日本の規制当局であったりルールを作る側の人達ってのは、どういう風に今考えていて、ここどうなっていくと思われますか?
増田)難しいご質問ですね。まあDeFiっていうもの自体は止めることもできないし、どんどん発生していくだろうと。しかもまあ、魅力的な商品に加えて、魅力的なインターフェースが出現した瞬間にキャズムを超えていく可能性が高いのではないかと、私も考えているところなんですね。 で、そうなると当局としては、本来その規制したい目的である、例えばマネロンの防止とか、そういったものを、一体どうやったら実現できるだろうかという風に考えるわけですよね。既存の金融規制っていうのは、その例えば登録とか免許制とかを敷いて業者を把握して、その業者に、その犯罪収益移転防止法上の、その取引時確認義務とかを課すことによってコントロールをするという、そのコントロールをするポイントというものをしっかり押さえて、そこに義務を課すことによって統制していくというやり方を取っているわけですよね。これって、そのいわゆるインターネット規制で言うとこの、ポインツオブコントロールみたいな話であるわけですけれども、金融の世界では昔からずっとやってますと。これがDeFiになった瞬間に消滅してしまうのではないかという恐怖感が、おそらく当局にはあってですね。
私も2018年から2020年までいた時にですね、2019年の春先にですね、あの韓国の当局者が集まって、DeFiの規制について、いわゆるRegTech的な話をするカンファレンスに呼ばれて、アメリカに行ったことがあるんですけれども、そこであの、結局、ポインツオブコントロールをどうするか、重要だと思うけれども、皆さんどう考えているのって言ったら、もうみんながシーンとしてしまうという場面があってですね。正直、どうやって規制したらいいのかわからないぞというのが、当時からあった話でございました。で、私今も、そういう意味では、私の中にも答えがないし、当局自身も答え持ってないんじゃないかというふうに思うんですが、一つ言えることは、インターネットと同じで、すでに存在する仕組みでもあるし、それ自体止めることはできないので、プロトコルを規制するものではないだろうと。そうであれば、アプリケーションレイヤーの話になるんだが、アプリケーションレイヤーの中で一体どこを捕らえれば、規制が効果的に行うことができるのかということを、当局自身がこれから追求していかなきゃならないので、放っておけばこう発展してしまうその民間に対して、当局がどんどんキャッチアップして先回りしなきゃいけないんで、非常に苦しいのだろうなというふうに想像はしています。
グローバルなDeFi規制の現状
金光)ありがとうございます。ここはもうぜひ、河田さんにお伺いしたいんですけど、松尾先生や牛田さんがBGINなどで、あのDeFiの研究会をずっとやってらっしゃって、まさにそのプロトコルではなくアプリケーションレイヤーをだったりですとか、私の知ってる限りでは、あのDIDがこういったDeFiの規制に役に立つんじゃないかとか、いろんな議論がされてると思うんですけれども、あの増田先生がミーティングに出られた2019年から今、そのグローバルで、DeFiをどうやって規制していけばいいのか、みたいな、そのどういうふうに今捉えられ、考えられ、議論されてるんでしょうか。
河田)私が参加していた会議中心に、金融安定理事会を中心になるんですけれども、状況はですね変わったかというとあんまり変わってないです。未だにどうしようかなという形です。ただ、議論はですねもうちょっと、多分精緻に考えなくてはいけなくて、今、DeFiですよ、僕たちDAOだよとか言っててもですね、実態を見るともう非常に中央集権型っていうのもたくさんあるわけですよね。なので、ある当局はいやいや、これはね、いきなりその規制対象がいなくなったわけじゃなくて、もうエンフォースメントをやるかどうか。あとは、オフショア事業者、昔からあるオフショア事業者に対してどうやっていくかと、こういう問題にすぎないんだよって言う当局もございます。ただし、当然ながらいやいや、そうではなく、それはそれといいんだけれども、じゃあ完全に分散化した場合、その場合にどうするのかというのはまさに今年、その基本的な考え方が金融安定理事会等々で議論されて、来年ぐらいにおそらく公表されて、国際スタンダードができて、それは各国には直接適用されませんので、そこからそれを参考に、各国が国内法を整備していくという形かと思います。
この時にポイントがいくつかあってですね。国際的な会議で、なんか前提があってですね、私知らなくて、最初FATFですごい苦労したんですけど、その、まず最初はさっきの話、結構近いんですけれども、テックニュートラリティ、テクノロジーニュートラリティ、テクノロジー中立性、技術中立性、これ何かというと、規制っていうのは、技術に対してはかけないと、技術を使ったサービスに対してかけるものだという。これはもう非常に強い、これはインターネットから来ているんですけれども、非常に強い大前提がございます。でもう1つは、セーム・アクティビティ、セイム・リスク、セイム・レギュレーションという考え方です。これはG20のコミュニティでよく言われるものですけれども、同じ活動、同じリスクであれば同じルールを適用するというものでございます。例えばデリバ 取引であれば日本だと原産に関わらず同じ金商法が適用されるとかですね。まあ場合によっては暗号資産交換業者のこういった規制と他のね、例えば金商法な行為を行えば金商法業者のこういった規制はもう全く同じであると。こういったように同じ規制を適用するんだ、TradFiとDeFi関係ないよ、ていうのが技術に関わるですね、それがもう一つの考え方です。
であと2つですね、そのもう一つはプロポーショナリティですね、比例原則。リスクに応じて比例して規制は重くしていくべきだと。これはですね各国によってリスクの評価が結構違ってですね、日本はかなりリスクが一時期あったかなと思っています。ただし他国ではですね、まあそもそも2018年頃はそこまで大きな金融システムでも影響もなかったので、そこまでじゃあないよね、みたいな話だったんですけれども、もう昨年、金融安定理事会は正式にこれは金融安定に対する脅威になり得るということでリスクプロポーショナリティとはいえですね、相当きついレベルが今要求されています。最後は、アヴォイド・プリスクリプティブ、細かい国際的なルールで国際スタンダードのレベルで細かく書き込まないと。細かく書くとですね、だいたい皆さん規制アービトラージしちゃうんですね。あ、書いてないからいいやとかですね。なので細かく書き込まない。また、それは各国が実際に国内法を作っていくにあたって柔軟性を確保すると、そういうためにも必要になります。このちょっとこういった4つの原則にさらにセクター別に今度はまた別な、加えて考え方が入ってきます。例えばFATF、マネロンを見るFATFですとここはもうキャッチオール。一切抜けがあってはまずいので、マネロンとか経済制裁はですね、基本的に全ての範囲、だからFATFの定義の暗号資産が一番広いんですけれど、もう全てもう捕まえると。マルチシグで事業者がちょっと動かせなくても基本的にはそれも全てVASPだとという非常に広い考え方を持っていたりします。ここはバーゼル銀行監督委員会とかですねIOSCOとかIAISとかですね、証券、保険、等々によってちょっと考え方は変わってきます。
そういった形で先ほど申し上げた通り技術者、単にこう技術を作ってですね、技術開発してデプロイして、で金融サービスを特にやっていなければですね、その方が何か金融規制の対象になるというのはまず考えにくいです。ただし業としてやってるとかですね、業として デプロイした後に何か金融サービスもずっと継続的に提供しているとかですね、何かしら収益を当然どこから収益持ってきて継続的にやるとかですね。こういう場合は金融規制の対象に入ってくる。この金融規制の対象の範囲のことをよく規制ペリメタ、レギュラトリーペリメタというんですけれども、ポイントオブコントロールと同じです。レギュラトリーペリメタをどこに置くか、例えばユニスワップの場合はユニスワップラボが開発していると。デプロイしてやっている。ガバナンストークンも一応あるものの、多くはですねファウンダーの方々であったり開発チームが結構持っていると。相当集中してるわけですよね。そうするとユニスワップラボっていうのが場合によってはポイントコントロール、規制ペリメターに入りうる。ですけれども、ご案内のとおり別にユニスワップラボ自体は特に金融サービス提供していませんので、じゃあどうしようか、場合によってはDeFiは、ちょっと直接やるよりも、通常の取引所、よくオンランプをオフランプと、よく皆さんおっしゃいますけどオンランプ、オフランプのところで、やっぱり規制、今の通りでもうちょっと強い規制をかけていくのもあるんじゃないかとかですね。こういった議論が今、ただ今正解はなくてですね、この辺り先ほど申し上げた通り、ユニスワップラボを例えばペリメタに含めるていうのはテックニュートラリティに思いっきり反するので、ちょっとですね、これはなかなか先が今見通せない、かなり悩ましい問題でございます。それが今の世界の現状です。
DeFiはTradFiの脅威となるのか
金光)ありがとうございます。大変私も勉強になりました。お二人ともありがとう ございます。まあ、ちょっと普及するためというところでいきますと、私はさっきのセキュアードファイナンスさんの話をすごく面白かったし、すごく今後普及してほしいなと思ったんですけれども、ちょっと三人の方にお伺いしたいんですけど、工藤さんからご覧になって、これTradFiの立場から見ると、そのセキュアードファイナンスっていうのは、既存のTradFiの何かを奪いうるものなのか、何かその脅威になるものなのか、それとも全く新しいお客さんが来るものなのか、どういう風にTradFi場合の立場からご覧になられるんでしょうか。
工藤)これはもう全く新しい領域というか、何でしょう、今のTradFiとDeFiは文字通りといいますか、まあ両極端だと思うんですよね。で、DeFiは極端だと思いますし、ある意味TradFiも極端なんですよね。現実的には。ですのでやはりまあ、そこの間をやっぱり埋めに行くっていうことが起こるんだろうと思ってます。で、イールドカーブ、さっき見てすごいなと思ったんですけれども、やっぱりこういう事例もそうですし、リアルワールドアセットですか、こういったのもですね、どんどん出てきてですね、やっぱり実例を重ねていく、のがまず一つ。次が信頼を重ねていく。今はまだやっぱり信頼を積み上げていこうとしているフェーズだと思うんですよね。で、それが積み重なっていくことでお互いが近づいていくんだろうなと。で、そこに新しいマーケットが広がるということで、TradFiの領域が何か取られるというのではないんじゃないかなというふうに思ってます。
金光)ありがとうございます。これは菊池さんどういう風に考えてますか。
菊池)そうですね、あの全く食い合うっていうのもないですし、拡大の一つのチャンスだと思います。なのでむしろお互い、ウェルカムでもうちょっと歩み寄ってほしいなと思いつつですね。で、私あのやっぱりイールドカーブとかマーケットを作るってなった時に、自分もともと金融機関で働いていた時って、結構皆さん日々の業務で忙しいんですよ。なので日々メイクマネーするだけで、そんなに深く、なぜこのマーケットはこんな風になってるのか?ていうのはわからないままなんですけど、いざ作る側になってくると非常に違った見方で、そもそもDeFiってどんな性質だろうと結構思って、そもそもクリプトカレンシーって何なんだろうなっていうのに、ものすごくその立ち向かうというか、向き合ったことがあって。
で、一つ気づいたのと、トラディショナルなのとの共通点を見出したのは、これ僕の味方なんですけれども、捉えどころなさそうに見えるクリプトカレンシーなんですけど、めちゃくちゃ似てる市場あるよねっていうのに気づいたんですよ。それってユーロカレンシーマーケットなんですよね。で、ユーロカレンシーマーケットってカレンシーのユーロじゃなくて、要するにその本国にない通貨なんですよ。ユーロ円っていうのは日本にない円のことですし、ユーロ円債とかあるじゃないですか。で、ドルも米国にない、米国の規制を受けないドルってのがあって、ユーロドルによって実はインターバンクマーケットってほぼそれなんですよ。トレーダーはみんなそっちの方がいいんですよ。なぜならば、そういう人為的なルールとかによってプライスが歪められたりとかないんで、最もニュートラルで、最も効率的な、エコノミックにメイクセンスするマーケットを求めるんですね。そうした結果、実務上ものすごく重宝されてきていて、役に立ちますし、コストも低いっていうんで。
なので規制が届かないからといって全部潰してしまえという議論は一瞬あったかもしれませんが、もう何十年も議論されていて、今や皆さんもう使ってますよね、ということで非常にこの類の議論というのは、我々が今、クリプトをどう規制するのかっていう時に応用できるものかなと思ってまして。おそらくまあ、完全な解は多分ずっと議論をこうやってやり続けていくことに僕らはなると思うんですけれども、その中でもやっぱり実務上の着地点を見つけながら取り扱っていくのかなと思ったりしてます。先ほどのオフショアマーケットじゃないかっていうのはまさにその通りだと思いますし、じゃあ国内なり各国の規制との折り合いというのも、じゃあ、オフショアのマーケットはこのようになってるから、それをオンショアにローカライズする努力を規制を通して安全に、お客さんに提供するという、トラディショナルなマーケットの成り立ちというのは、全く適用できるかなと思っていて、そういうふうに発展していくのかなと思ってます。
DeFiのマスアダプションに向けて
金光)ありがとうございます。面白いですね。確かに ユーロカレンシーマーケットが似てるというのは新しい発見。ちょっとこれ増田先生にお伺いしたいんですけれども、セキュアードファイナンスあのすごい伸びていてユーザーの方も5万人とかいらっしゃるというところでこれが何でしょうね、マスアダプションを多分していくために規制側は何をしなきゃいけないと思いますか、マスアダプションを例えばしちゃった時に。
増田)まあそうですね、やっぱり気になるのはマネロンなんでしょうし、その仕組みはマーケット自体が存在するにしても、取引をする人が一体そこにどうやって関与していくのかということはまず気になるところですよね。で、やっぱりアンホステッドウォレット持って直接そこで取引したいとまさにDeFi的な世界だと思うんですけれども、そうなった時に一体誰がそれをコントロールできるんですかっていうのは鋭く問われるようになるだろうなというふうには思います。さっきの話の繰り返しになっちゃうんですけれどもね。
菊池)鋭く問われるのは非常にあの歓迎と言いますか、我々、規制の考え方を非常にリスペクトしてまして。非常にそのおかげでマーケットは発展してきたなという部分もあるので。例えばそのBISのレポートなんかでもEmbedded Supervisionと言いますか、その埋め込んでいく、要するに開発する側、僕はラッキーなことにTradFiでもエンジニアでもあるので、規制の意味合いを汲み取って、本来達成したいものを掴み取って、ソースコードに埋め込んでいくとかですね、そういった、どうすればマーケットとして最も安全なマーケットになっていくんだという工夫をですね、セルフレギュレートする形でやっていくっていう姿勢を見せていかないと、やっぱり歩み寄りということにならないのかなと思ってます。あと規制でいうと、逆にブレーキを踏むだけが規制じゃないなと結構思ってまして。実際にですね、インターバンクマーケットといいますか、インターディーラーマーケットってちょっと面白いルールが あって、トレードがダンする前に相手の情報を知っちゃいけないんですよ。これ禁止。なぜならそれを悪用してとか、いろいろ要するに、健全な市場形成、健全な価格形成、マーケットインテグリティが損なわれてしまうから、逆に相手情報知っちゃだめなんですよね。ダンしたら知る。結構、逆じゃないですか。そういったルールがきっちりとあることで、要するにまあ本当に透明性を高めたトレードの環境ができていくのかなと思っています。
増田)一点付け加えたいのが、あの規制当局というか国家ができることは、規制だけではないのだというのはまさにおっしゃる通りだと私も思っていて、適切なインセンティブ誘導を測るのがまさに法制度の役割なんですよね。例えば、アンホステッドウォレットの利用を前提としつつ、その本人確認を経ているという例えば、Soul Boundトークンでも何でもいいですけどが入っていて、かつ取引時にその2段階認証で確実に本人確認しているようなものだけを受け入れるようなDeFiが登場したとします。そういったところで取引しているものに関しては税優遇をするとかですね。そういった形でプラスのインセンティブ誘導をすることによって、そっちに政策的に誘導していくみたいな、そういう経済的インセンティブを利用したコントロールのあり方というのは当然あって、そこは規制当局が考えることというよりは、もう少し上のレイヤーの人が、インセンティブをどう構成すべきかを考えるべき世界観なのかなというふうには思います。
今後のDeFiへ期待すること
金光)非常に面白いお話をありがとうございます。最後のパートになっちゃうんですけれども、近未来的な部分というところと、あと皆様が結局そのDeFiをどのようにとらえていらっしゃるかというところを、お一人ずつ、ちょっとずつ語っていっていただきたいなというふうに思っているんですけれども。いろんな捉え方があると思っておりまして直近のそのシリコンバレーバンクの破綻とかで暗号資産が値上がりしました、DEXのボリュームが増えましたというところで、いわゆるアンチ中央集権としてのDeFiみたいな捉え方もあると思いますし、DeFiの先ほどのインターオペラビリティの補強みたいなところもあると思っています。皆様がそのDeFiに何を期待してこれからDeFiがどうなっていくと思うか、あと日本においてというところも含めてですけれども、お一人ずつお話をしていただけるとありがたいなと思っております。順番は工藤さんからお願いします。
工藤)なかなか難しいところですね。そうですね、やっぱり新しい金融ですので、私は金融領域を切り開いていってほしいなという期待を持っています。既存金融はやはりこれまでの歴史の中で非常に練り上げられた精緻な構造になっていて、その上での法規制もそうですし、慣習もそうです。そういう中にあるがゆえに、なかなか次の一歩が出ないっていう状況にあるのも事実だと思います。そういった中で、DeFiが勃興してきて、新しい見方が広がっています。今はまだ技術面がどうしても先行していると思いますが、やっぱりここにサービスが乗って拡大していくんだろうと思います。その先に、まずは一部のTradFi側の似たようなサービスが、そちらに乗って、単にクリプトカレンシーじゃなくて、サービスやプロダクトとして乗っていくと。その先に中間領域の本当のマーケットが出てくるんじゃないかなというところで、本当に期待を持って見ているということですし、それも視野に入れつつ、弊社もこういった領域に今入っていこうというところでいます。
金光)これは個人的な興味なんですけど、あの、あのご所属されているところは本当に金融機関の日本における代名詞のようなところでいらっしゃいますけど、非常にいろんな取り組みをされていて、Komainuもそうですよね。あの、いろいろやられてると思うんですけれども、そのお話いただける範囲で構いませんけれども、その全社的にどのような位置付けをされて、戦略的にどういう風に捉えられていらっしゃるんでしょうか。このクリプトアセット、デジタルアセット、DeFiといった領域についてですね。
工藤)そういう意味ではDeFiについてはまあクリプト領域ということでちょっと含めさせていただきますけれどもデジタルアセットについては新領域というところで、まさに私がデジタルアセット推進室というところで今推進しているところであります。つまり次のビジネスの一角として狙っている領域でありますというとこで、その上でできるところからまず使っていこう、というところで国内についてはセキュリティトークンを活発に進めておりますし、暗号資産についてはですね、スイスに子会社を昨年設置しております。もうサービスも、もうじき始まるというフェーズでありますので、ここからですね、まあしっかり事業として取っていくという、そういった考えを持ってます。
金光)ありがとうございます。河田さん、世界のその規制、金融規制に詳しいお立場からですね。DeFiに河田さんご自身が何を期待してるか、そしてそれに対して規制当局がどのように動いているかというところの話をいただければと思います。
河田)はい、あのですね、DeFiここでは暗号資産を含めたDeFiで考えてみますと実際にマーケット見てみますと昨年のTerraが崩壊した時はですね、バイナンスUSDとかですね、テザーとかですね、早速値を下げてしまっていたんですけれども、今回のシリコンバレーバンク、その前にシルバーゲートバンクが先ですから、シルバーゲート、シグネチャーでシリコンバレーですけれども、そこのところをきっかけにして、今度は逆にですね、USDコインが値を下げて、バイナンスとかテザーが上がってくるという形で、やっぱりセーフヘブン、あるいはTradFiに対する安全地帯と、それも時々、ある時はバイナンスだし、ある時は違うね、USDかもしれないという暗号資産の安全資産の逃避先というシステム、役割というのは引き続き出てくると思います。ただですね、やはり繰り返し申している通り、やはりセーフガードが全然ないと、顧客の資産はあまり保護されないと、レバレッジも結構かけますよね。担保ってどんどん、どんどん再チェーンできていきますので、担保の連鎖が生じてしまって、レバレッジの程度って、はっきり言って、多分正確なDeFi市場全体のレバレッジの程度って、あんまりよくわかんないんですね、という意味で、やっぱりリスクが高すぎると。おまけに担保の清算って一気にアルゴでやるじゃないですか、そうするとそこってセーフガードも何もない、まあプロトコルによりますけどね、まあそういう状況だと、なのでやはりセーフガードをしっかり作っていく必要は、まず第一に、それはあの投資家の方々がですね、より安心して使っていただくためには必要かなと思っています。
で、DeFiの機能ってですね、今日いろんな、すごくお話楽しいお話を聞かせていただいたんですけれども、基本的には、TradFiのやってることを、言い方はあれなんですけども、ちょっと仕組みを変えてやっていると、取引であったり融資であったり、レンディングですね、保険とか資産運用とかですね。ということで、既存のやはりTradFiの機能をやっているというところ、実はちょっとやり方が違ってですね、例えばレンディングだと担保でしかできないので、相手は匿名なので、そうするといつも担保掛け目で、過剰担保をしないと借りれないとかですね、そうすると結局お金ある人しか使えないってことになって、正直今のDeFiの利用者の多くは先進国の機関投資家ではないかなというふうに一般的には言われています。それはやはりビットコインとか、もともとのですね、DeFiのポテンシャル、もっとグローバルに使われて、金融包摂とかですね、いろいろ使われるという用途をちょっと阻害しちゃっている。また取扱いのアセットもやっぱり、暗号資産とかステーブルコインにやっぱり限定されてしまう。そのために現実世界のリアルワールドアセットですね、現実世界のアセットを使えるようになれば、さらにユースケースが増えていくということで、DeFiがさらに発展していくには、まずこの現実世界の様々なトークンを使えるようにすることで、そのためには法規制側は所有権の移転でしたり、対抗要件の確定とかですね、法整備をしっかりやる必要があります。その上でDeFi側としてはもう今すでに始まってはいますけれども、もうちょっと信用リスクも評価できるようにして、きめ細かい評価ができるようになると、資産プールにポンと入れてっていうのではなく、もうちょっと細かい制御ができるようになると、さらに発展していくかなと思っております。最後にTradFiの機能を完全にシミュレートするだけではなくて、例えば私はすごいと思っているのはフラッシュローンですけれども、ああいったやっぱりDeFiならではの機能でですね、悪いことにたくさん使われてるんですけど、ただDeFiの例えばこういったTradFiではちょっと考えられないような全く新しい機能っていうのをですね、DeFiでしかできないというのができると、TradFiとは別にDeFiは、同じ機能があればね、通常だったらロットの大きい流動性の大きいTradFiをみんな使うと思いますので、じゃなくて、流動性が低いところでやると思いますけど、さらにここでしかできないという機能があるとすごくいいだろうなというふうに考えております。
金融の未来への取り組み
金光)ありがとうございます。増田先生ちょっと総括的なコメントをいただければというところ、あと増田先生は私も昔から存じ上げておりますけど、やはりこの領域に関して非常に情熱を持って取り組んでいらっしゃって日本のこの強化を牽引してくださってるなと本当感じておりまして、その先生をその動かしているモチベーションは何なのかというところと、増田先生がそのDeFiに何を期待されているのかみたいなところ、あと今後の日本にどういった働きかけをしていきたいかというところも含めてお伺いできればと思います。
増田)なんかどんどんハードルが上がっていたのを感じるんですが、そうですね、およそ金融というものに期待するという気持ちがまずあって、金融ってその文字からも察せられる通りですね、何らかの価値の尺度となるものを利用して世の中を滑らかにするという機能なんだというふうに理解しています。それこそあの銀行の信用創造から始まってですね、経済が大きくなるですとか、資金がないところに資金を融通するみたいなそういった機能から始まってですね、様々な領域に金融が染み出していくことによって世の中が滑らかになり、経済が大きくなっていると。で、まずその障害の一つになっているのが例えばその真ん中にその事業者が存在したりすることによってコストがかかるとか非効率が生じるとかそういった部分であるのを見事に取り払おうと挑戦しているのがDeFiの分野なのかなというふうに理解しています。例えばセキュリティトークンが世に出てきた時にもいろいろ言われたのが、これまで証券化できなかったようなものも、どんどん証券化できるようになると、いわゆる何でもかんでも流動化みたいな話から始まり、さっきのあのマサさんの話にもありましたけれども、プライシングできるものっていうのは全て金融商品化し得るのだという話っていうのを、まさにそのこれまで金融が届いていなかったところまでこう世の中がガッと広げていってより一層経済を滑らかにしようという機能の発現なのだろうなというふうに思っています。そういったふうに、あまねくですね、DeFiによって金融がさらに世の中に広がっていくことによって、我々の経済社会というものはより一層大きく滑らかになっていくのではないかという期待を持っています。で私自身はそういったテクノロジーによるその人類社会のそのなんていいますか、ウェルスの向上というものをすごく信じていてですね、そういったその新しく出てくるテクノロジーに奉仕することに喜びを感じているという人間であるので、まさにこういった新しいものに感謝です。これからも応援する立場でいろいろと関わっていければなというふうに思っています。
金光)大変ありがとうございました。ではこういったお話を受けて、まさにチャールズさんがおっしゃったTrue DeFiでもあると思いますけれどもセキュアードファイナンスの菊池さんに今日のお話を振り返っての感想などいただければと思います。
菊池)そうですね。今日は非常に有益な話ができて非常に刺激的な内容だったんですけれども、結構DeFiの話をずっとしてきていて、今回そのテーマとしてWeb3が変える金融の未来ということで、少し視野を広げまして、そのWeb2からWeb3、それで金融がどのように変わっていくのかっていう話も少しさせていただきたいなと思っていて。僕としましてはまあこう、ここから先新しい時代が開けるということのためにはですね、やっぱり新しいツールですね、トークンの理解は非常に必要だと思います。あと技術の理解もすごく必要だと思いますね。トークンというのは増田先生おっしゃいましたけれども、非常にインセンティブをエンジニアリングするためのものすごく便利なツールですし、僕は株の上位互換だと思っています。非常にうまくやればですね、パワフルですし、上手に使えば非常に発展の可能性があると思います。技術に関しましても、先ほどBGINの話が出ましたけれども、最近のBGINの話ですと結構テクノロジーを使って新しいKYCをやっていこうみたいな話もあって、Decentralized KYCですとかZK(Zero Knowledge)でゼロ知識証明を使った、匿名性を担保しつつも、それが真実であるということを証明しながらうまくそのKYCを新しいものにできないかというのがすでにBGINでも議論と言いますか研究がされているということで、非常にテクノロジーの理解とこういった新しいツールの理解が重要だなと思ってます。
もう一つはですね、やっぱりその今Web3ということでキーワードでめちゃめちゃ広がっていて、僕もそこのパッションに惹かれてる部分というのは、アーキテクチャーの変更だなと思っていて。Web2からWeb3っていうのはまあITの世界でまず起きましたよね、テックジャイアントがデータをモノポリー化して悪用してしまったということで、分散化して我々の手に力を、みたいなことがあって。これに近しいことが僕の中では金融業界でも起きてまして。僕はもともと金利の世界なんですよ。なので記憶に新しいというか、記憶にある方もいるかもしれませんが、LIBORスキャンダルというのがあったんですよね。で、これはもう人間に任せたら間違いを起こすじゃないか、ということで非常に僕も反省しましたし、金融業界の人みんな反省すべきだと思っていて。だから人間に依存しないで、技術ですとかプロトコルでフェアにやれる環境が必要じゃないかということで、それでWeb3の技術に真に興味を持ったっていうところがあるんですよ。やっぱりそういったそのフェアな技術でもって人に依存しないで、ちゃんとそのトラストする部分が減っていってっていうような動きっていうのが非常にWeb3的な流れでいう金融で起きることなのかなと思ってまして。非常にその技術の理解とインセンティブ、この辺をキーワードにして、我々は次の金融を作っていけるんじゃないかなと思ってます。
質疑応答
金光)ありがとうございます。それではここから質疑応答に進んでいきたいと思います。質問のある方は書き込んでいただければと思います。先にいただいてたあの質問がありますので、ちょっと一つ読みたいんですけど。DeFi x KYC/AMLについては国別に支配的なKYC/AMLソリューションが出てきて、それを各国が使用する流れを想定しています。DeFiへの規制を含めこのKYC/AMLの将来に関する皆様の見解をお伺いしたいですということで、これまず河田さんからお願いできますでしょうか。
河田)はい、そうですね。特に最近では、トラベルルールがFATFの分野でございますので、トラベルルールに関する技術的ソリューションというものが暗号資産ガイダンスが改定されて2019年から、いろいろ民間でソリューションが育ってきつつある状況です。これ最初は、民間の方々、絶対これできないっていう風に散々言われてたんですけど、それをFATF側もアウトリーチ会合を開いたり、さらに細かいガイダンス出したり、年次のインプリメーションモニタリングとか、いろいろ出しておりまして、徐々に、まだ完全ではないんですけど民間ソリューションが育ってきているという状況でございます。
KYCとCDDとかのソリューションはもうすでに既存のものがあって、eKYCも含めてですね。なのでちょっと、ごめんなさい、ご質問の意図があんまりよくわからなかったんですけれども、いずれにしろですね、今後も暗号資産はやはりマネロンに使われうるという考え方は非常に危険性は高いのでですね、DID、場合によってはDecentralized Identityということで分散型でしっかり本人を確認できるような、例えば機能をウォレットに入れようとか、こういった新たなツールを用いて、プライバシーを保護しつつ必要なAML/CFT規制を満たすというソリューションは今後も引き続き出ていくかなというふうに思っています。
ちょっと最後に、先ほどBGINの紹介を振っていただいて忘れてしまったのでちょっと申しますと、特にアンホステッドウォレットって難しいんですね。個人が使ってますので、先ほど申した通り、業で扱っていない個人が規制対象になることはないと。じゃあその場合、結局P2P取引、Peer-to-Peer取引ってFATFが出すデータというのがですね、トラベルルールの進捗状況とかを見ている年次の報告書があるんですけれども、そこで私が実際に各ベンダーとかに色々聞いてみるとですね、実はP2Pの取引はすごいばらつきがあるんですけれども、半分以上取引やってるんじゃないかという見解でございました、全体のですね。その場合じゃあ結構、アンホステッドウォレット、セルフホステッドウォレットは非常に重要なポイントになります。これをいかにセーフガードを設けるかとか、不正に巻き込まれないようにするか、ただこれは規制当局だけでは解決できない。基本的には金融規制の対象外ですよね。さらに開発者の方々、ウォレットの開発者の方々のご協力も必要である。もちろん民間の暗号資産交換取引業者の皆様のご知見も必要であるということで、日本は非常に早く、2019年のG20で議長国だった時に、BGIN(ブロックチェーンガバナンスイニシアティブネットワーク)というのを立ち上げまして、マルチステークホルダーアプローチ、様々な人と利害関係者と皆で集まって、今後の特に金融規制が難しい部分について検討していこうという取り組みを進めております。
金融庁は、今ステークホルダーの一員として参加しています。その中では今申し上げた新たな技術的なソリューションというのも議論がされております。ご関心がありましたら、ぜひ一度ご確認いただければと思います。
金光)BGINは本当に誰でも入れるんですよね。私も一度入ってみたことがありますが結構深夜だったので寝てしまいました。
河田)時間帯がね。菊池さんもそうですもんね。
菊池)はいそうですね。オープンソースですし、オープンなので皆さん参加できます。
金光)非常にテクニカルな質問があって、伝統的なデリバティブ金融の世界ではISDAを中心とした証拠金管理のシステムが支配していますが、将来のロードマップでブロックチェーン業界との競合との親和性について、その証拠金管理のところですかね、意見を伺いたいです。ということでこれ、菊池さんお願いします。
菊池)ISDAのコンセプトを非常に僕も良いと思っていて、結構ISDAコンパチブルなDeFiということで、元々やってたんですよね。ただそれって契約関係にあったりするので、ちょっとDeFiにフィットする形で僕たちはやってます。そもそも、セキュアードファイナンスの名前って、基本的にはあらゆるクレジットリスクがセキュアされてますと、担保を取ってその上でやってくださいっていうような話なんですよね。なので担保管理は、例えばISDAですと、コラテラルのネッティングのルールがあったりとか色々細かいルールがあるのを、そこから学んで実際プロトコルに落とし込んでいるというところがあるので、まあそういう意味では親和性はものすごく高いのかなと思います。
金光)ありがとうございます。次は最後の質問ですね。大手企業が今Web3に参入することを考えると、先行者利益の獲得が目的の一つになると思いますが、これは中央集権的なのでは?そもそも先行者利益を目的にすることが 誤っているのかこれについてのお考えをお聞きしたいですと。これ工藤さんお願いします。
工藤)多分、今段階でその先行者利益っていうのは、なかなかちょっとわかりませんけれども、どうなのかなというふうに思います。よくあるパターンはですね、先行者利益と言いつつ先行者コストということも普通によくある話なのでここはやっぱり各事業を含めてですね自分たちはやっぱ強みにしてるところと自分たちの強みに生きるところ、ここを掛け合わせれるのかどうかを見てから、やっぱ入っていかないといけないんだろうというふうに思います。
金光)ありがとうございます。それでは エンディングに移りたいと思います。今回ですねグローバルDeFiマーケットで戦うセキュアードファイナンスの菊池さん、あとは日本のファイナンスのジャイアントの立場からTradFiのお立場からDeFiを見られている工藤さん、あと世界のですねグローバルの金融規制にお詳しい河田さん、あとは日本のWeb3のですねホワイトペーパーをリードされたお一人であります増田先生にお話を伺いましたが、今回の皆様のお話を伺っての感想を一言と、何か話し足りないなということがあれば一言いただければと思います。じゃあまず菊池さんからお願いいたします。
菊池)やっぱりそのWeb3は新しいものなので、金融にしても本当にもうどんどんトライするのがいいのかなと思いました。で、先ほどの質問のあれでちょっとだけなんですけれども、そのおそらくですね、Web2的じゃないか、中央集権的じゃないか、というのは、多分ですね、Web2的なのは、いかにお金を集めてきて中央に集めてきて誰かが得するか、みたいな思想にあるのに対し、Web3ってプロトコルでインセンティブをうまく利用して収益を集めるんだけどもどのように分配するか、という全く違う感じで、Web2はトライアングルみたいな感じでピラミッド型なんですけど、Web3は結構フラットになっていて、どんだけ分配するかみたいな考えなんですよね。なのでそういう意味においては、まあ先行者利益は全部奪ってやるんだみたいなのは確かにちょっと中央集権かもしれないですけど、アーリーアダプターであることには非常に良いと思うので、どんどんチャレンジしてもらいたいなと思いました。
金光)ありがとうございます。続きまして工藤さん、一言お願いいたします。
工藤)今日のこのイベントのタイトルがこのDeFi meets TradFiということなんですけれども、私の立場からするとですね、こう逆でして、TradFi meets DeFiという風に実は読み替えて見ておりました。で、まあ途中でも申し上げましたように、まだまだ距離はあるというふうに思っていますけれども、そう遠くないところでお互い握手できるようになるなというふうに信じておりますので、そこに向かってですね、私たちも私自身もですけれどもコミュニティにですね、積極的に貢献していきたいなというふうに思っております。ありがとうございました。
金光)ありがとうございました。では 川田さんお願いいたします。
河田)はい、あの今日のお話は皆さん方すごく面白くて、有意義でした。私の話は国際的な規制のお話が中心だったんですけれども、暗号資産で、いろんな世界的なニュースを見てみるときに背景が分かると、やっぱり楽しいと思いますので、参考になればと思います。1点ですね、話し忘れていたのがございまして、今後のさっきのそのDeFiの将来を考える時には、ですね、実はいろんな動きも多分考えなくちゃいけない。さっきの菊池さんのおっしゃる通り視野を広げる必要があるかなといつも思っています。
例えば、CBDCは今も動いていますよね。イギリス、ECBは2025年ぐらいには発行するんじゃないかとかですね、動きが出ている。元々、2019年のリブラショックを受けて、ですね、金融安定理事会をはじめ主要国は今、クロスボーダー決済改善という、既存のクロスボーダー決済システムを改善していこうと、コストも下げてね、効率性も上げていくんだ、というもう6年以上の超巨大プロジェクトをやっています。こういった動きもございます。最近ですと、私一番衝撃を受けたのはチャットGPTですね。やっぱ生成系のAI、いろんなの出てるんですけど、こんなインパクトのあるのが突然ボーンと出てしまうと。というので、あの将来というのはいろんなインパクト、インシデントの形でかなりいろいろ変わっていくかなというふうに個人的には思っています。
今、私自身が個人的にすごく関心があるのはチャットGPT、生成系AIです。Web3ですとちょっとリソースが載せられないからWeb2しか使えないかな、みたいな話もございますけれども。これがですね、DeFiに対してどういう影響を与えるか。スマートコントラクトの作成が楽になる、監査が楽になるとかですね、ブロックチェーン分析が対話型にできるとかです。いろんな使い方は多分山ほどあって、私が以前ユニスワップで大変衝撃を受けたみたいに、なんかすごく新しい使い方をされる例が出てくるんじゃないかなというふうに期待しております。
金光)河田さん、ありがとうございました。最後に増田先生お願いいたします。
増田)はい、先ほど申し上げた通り、私はテクノロジーが人類にもたらす未来を信じる立場としていろいろと活動しているわけですが、まさにブロックチェーンやDeFi、といったものもそれに類するものだと考えています。だいたい、技術者や技術とその政策決定者側との間の分断が生じるとですね、そこでイケてない規制が生まれる、というのはこれまで人類が長く経験してきたことでもあって、そういったことは避けたいというふうに私も考えて、常にその間に立って、世の中を滑らかにするためにこれからも活動していきたいなというふうに思いました。今日は大変刺激的なお話、いろいろとありがとうございました。
金光)増田さんありがとうございました。私もこれからもですね仕事ではまだまだDeFiを触れる日は遠いかもしれませんけれども、1ファンとしてずっと動向を見続けていこうというふうに思います。大変面白かっ たです。ありがとうございます。それではここで本セッションを終了とさせていただきます。会場の皆様ご視聴いただいた皆様どうもありがとうございました。
[拍手]
アーカイブ動画
イベント全編、キーノートを含めて、アーカイブ動画でこちらからお楽しみいただけます。是非ご覧下さい。