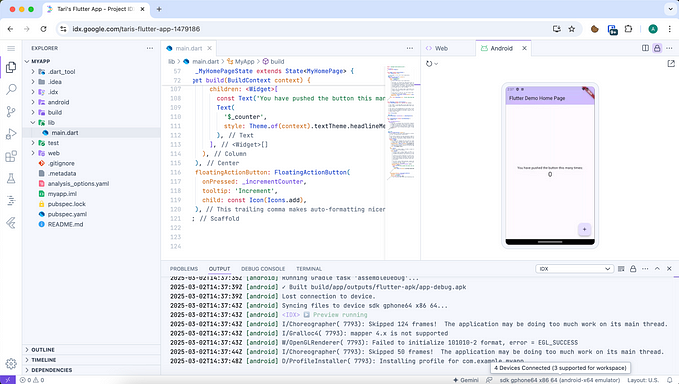ZEPPELINでは来年度から給料を自己申告にすることにした。
自分の給料を上司や誰かが評価によって決めるのでも、年功序列で決めるのでもない。給料の上げ幅(下げ幅)に制限もない。
自分自身で自分の給料を決め、全員とその内容を共有する新しい取り組みがはじまった。
そしてまさに今、その給料決定プロセスを進めている真っ最中なのだけれど、非常に有益だと思える要素を多々感じるので、できるだけZEPPELINで起こっていることを書き残しておきたい。
なぜ、全員が自分で自分の給料を決められるようにしたのか?については、
- 一人一人の自主性・自立を最も尊重する組織づくり
- 誰かが誰かを管理するというのは幻想。全員が自分で自分を律することができる組織づくり
- 誰かと比較しない、過去の自分を乗り越える。という組織づくり
を目指す。というのがその理由であり、
それらの根本は、
- ZEPPELINがよりクリエイティブな組織になること
- 一人一人が最高に幸せで生き生きと毎日を過ごせること
というZEPPELINの思想からきている。
このような組織を目指すために、一人一人のクルー(※ZEPPELINでは社員のことをクルーと呼ぶ)が自分で裁量を持ち、自分で自分の働き方を決めることができ、自分で選べる。そういう組織をつくろうとクルー全員で話しながらやってきた。
昨年度までは評価で給料を決めていた
これまでのZEPPELINにおける給料の決め方を振り返ってみる。
昔は、上司が部下を評価し、最終的に役員が給料を決める。という一般的なプロセスを採用してきた。
その後、フラットな組織づくりを実現するべく役職を廃止。
それに伴い、360度評価を導入し、他のクルーが評価した上で、最終的な給料は役員が決める。というプロセスを採用。
そして来年度より給料自己申告を導入することとなった。
昨年度までは、上司や他のクルーなど他者が評価し、役員が最終的な給料の決定をしていた。
ただ、評価というのは、する側もされる側も『気持ちが悪い』。
何年もずっとそう思ってきた。
どのようなところが気持ちが悪いのかというと、
- 評価するということは何かしらの基準が存在する。その基準を設定してしまうことで、評価軸を超えた個人の成長、が生まれにくい。成長に制限をかけてしまう。クルーの可能性と自主性に蓋をしていた。
- 評価を経たことでクルーの自主性やモチベーションが上がることはなかった。むしろ真逆のことをやっているようにしか思えなかった。(なぜ自主性やモチベーションが上がらないのか?についてはまた今後書いてみたい。)
- またほとんどの場合、評価される側は納得できない。という問題もある。際限なくクルーの給料を上げることができればいいが、上げられる幅には限界があるため、全員が納得できる給料額を会社が提示し続けることは不可能である。
だからやめた。気持ち悪いことは続けていてもしょうがない。何も未来に繋がらないと思った。
クルーとも正直に話をして、来年度からは新しいプロセスを導入しようということになった。
それが自分自身で自分の給料を決めるプロセスだ。
どういう給料設定プロセスを設計すればよいのか?
では、そもそもどのようなプロセスを設計すればよいのか?
半年かけて慎重に練って、下記のプロセスでやってみることにした。
- 前提として、給料の金額は公表せずに、現在の給料からの『ベースアップ比』(ex. 110%)を全員で共有することにした。
- 各個人の前年度と来年度の役割、成果、WHY(それをなぜやろうと考えているのか?)を記入する。
- 来年度の自分の給料のベースアップ比をある特定の場所に送る(この時点では他の人からは見られない)。
- 全員がベースアップ比を出した後に、全員で時間を取り、本音で話をする。
- 話し合いの後、再度自分のベースアップ比を算出し提出(必要であればこれを繰り返す。)
- 給料確定
まずはこのプロセスを慎重に一度やってみて、不具合があればそれを改善していくことにした。
『給料上昇バブル』になる可能性
このやり方はクルー自身の自主性と働き方を尊重し、クルーの自立を促すはずである。今後のZEPPELINの生き方にとても合致する。しかし、当然ながらクルーの給料が際限なく上昇してしまう可能性がある。
似たようことをやっている企業を見つけた。そこには似たようなことをトライしていく上で『給料上昇バブル』になった。と書いてあった。
何の制約もなしに個人が好き勝手に給料を決めてしまうと、自分の思い思いのベースアップ比率を決定してしまう。気がつかないうちに際限のない給料の上昇が発生してしまう可能性がある。
ZEPPELINのようなソフトウェアサービスを設計開発する会社はコストの大半が社員の給料だ。その給料が無条件に上昇すればコストが増大する。
何か策を打たないといけない。
給料最終決定までのプロセスに時間をかけて、慎重に進めることが重要そうだそう考えた。
(→ここで思いついたプロセスや、プロセスにおける重要事項については次回に記したいと思う。)
クルーが初めて自分で自分の給料を描いた瞬間
そして、今日、クルーから様々なベースアップ比率が出てきた。
想定していた数値もあれば、なかなかチャレンジな数字もある。見た瞬間の率直な気持ちは、ワクワクした。
ZEPPELINのクルーが初めて自分で自分の給料を描いた瞬間だ(この時点ではまだ最終的に決定してはいない。全員で話をした後、再度検討して最終的に決める)。
自分自身の給料を考えるには、過去の自分が会社にどのように貢献し、今後自分自身がどういうことを成し、どういう成長を遂げるといった「個人の視点」だけでなく、その結果ZEPPELINがどういう風に成長し、いくらぐらいの売上と利益を出し、何に投資するのかといった「会社の視点」の両方を踏まえて、自分の給料はいくらぐらい出せるのか?を考えないといけない。
自然とそういう思考になるのではないか?新たな組織の段階への足がかりになると考えている。
次回は全員で話をした後、どうなったかを記して行きたいと思う。
追記)
もしベンチャー企業の方がこれを見ていきなりこれと同じことをやり始めたらおそらく大変なことになると思う。
自立・自走する組織になるためのステップを設けながら、少しずつ時間をかけてやらないと組織が崩壊しかねない。
いつか時間があったら、そのステップも書いて見たいと思う。